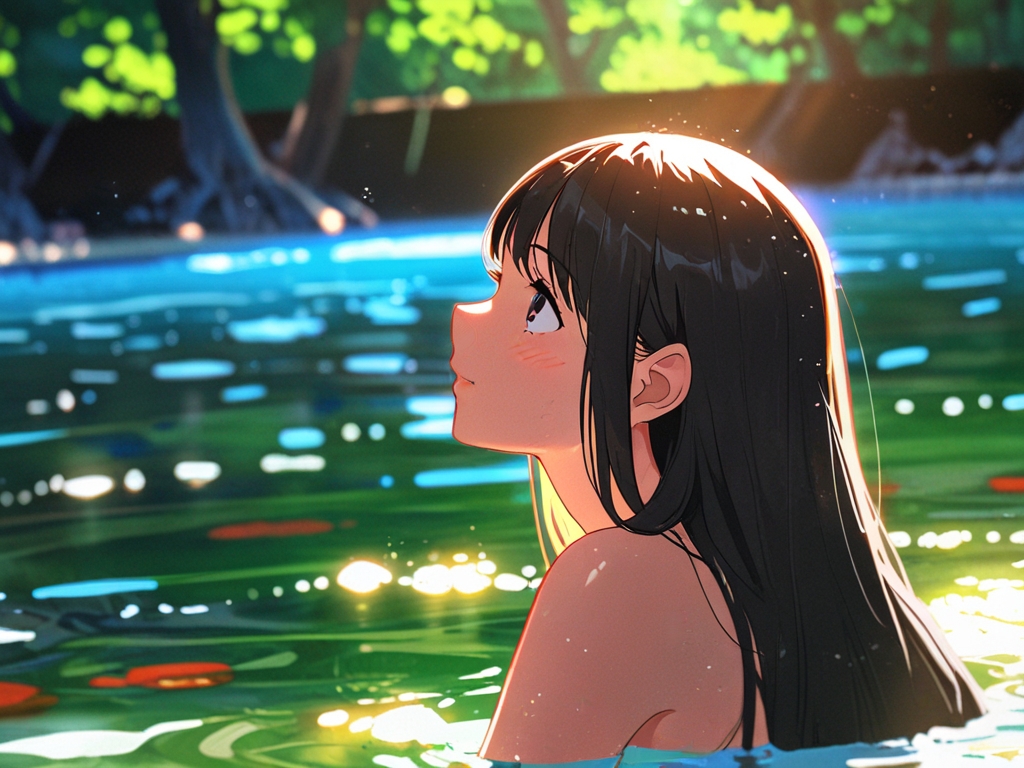「毎月の給料からは社会保険料や所得税が引かれているのに、住民税が6月だけ引かれるのはなぜなのか?」と不思議に思ったことはないだろうか。6月になると、給与明細に突然“住民税”の天引き欄が登場するため、「え、先月までなかったのに?」「しかも結構高い!」など、驚きと疑問を感じる人も多いはずだ。
本記事では、住民税が6月だけ引かれるのはなぜなのか、そのしくみや理由を徹底的に解説する。読めば「住民税ってどう計算されているの?」「そもそも住民税はいつ納付するのが普通なの?」といった疑問がスッキリ晴れるはずだ。また、住民税の具体的な計算方法やスケジュール、6月に引かれないケースなど、気になる点を網羅的に扱う。最後まで読めば、納得と同時に「なるほど、こういう仕組みだったのか!」というちょっとした感動(?)を得られるかもしれない。
住民税に関する知識をしっかりと身につけるメリットは大きい。理由を理解しておくと、給与明細の見方が深まるだけでなく、「来年はいくらぐらい引かれるか」や「いまのうちにどれくらい貯金しておくべきか」など、お金にまつわる計画が立てやすくなるからだ。
「住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?」という疑問に、この記事がきっと答えてくれる。さっそく、詳しい世界へ飛び込んでみよう。
1. 住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?~大前提の仕組み~
まず大前提として、「住民税が6月だけ」引かれるという表現は少し誤解をはらんでいる。実際には、住民税は6月から翌年5月まで毎月(給与支給のたびに)引かれる仕組みになっている。だが、5月までの給与明細には住民税の天引き欄がなく、6月給与明細で初めて住民税が天引きされているので「6月だけ」突然引かれているように感じるわけだ。
この「6月スタート」というスケジュールは、前年の所得に基づいて当年度分の住民税が決定されるというルールと深い関係がある。下記のような流れをイメージしてほしい。
- 1月~12月:前年の所得が確定する期間(つまり、この間に稼いだ金額が住民税の基準となる)
- 翌年1月~3月:各自治体が個人の所得などを確認し、住民税の課税額を計算・決定する
- 5月頃:各自治体が「住民税の税額通知書」を各勤務先(特別徴収義務者)へ送付
- 6月:住民税の特別徴収(給与天引き)が開始される
「6月だけ」という表現は、このタイミングのズレによって生じている。つまり、5月までは前年の住民税を払い終わっており、6月から新しい年度の住民税がスタートしているのだ。
2. 住民税の計算方法と納付スケジュール
住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?という疑問をもっと深く理解するために、まずは住民税の計算方法と納付スケジュールを押さえておこう。
2-1. 住民税の計算方法
住民税は大きく分けて均等割と所得割の2種類から構成される。
- 均等割:所得の多い・少ないにかかわらず、一律に課される金額
(都道府県民税・市町村民税がそれぞれ定額で課される) - 所得割:課税対象所得に応じて計算される
(所得に応じて税率が掛かり、都道府県民税・市町村民税を合わせた合計額が決まる)
具体的な金額は自治体によって多少異なるが、一般的には都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円の合計4,000円が均等割(標準額)といわれる。ただし、各自治体で上乗せがある場合もあるため、詳細は住んでいる地域の役所で確認してほしい。
所得割は、(所得 – 各種控除) × 税率 で算出される。税率も自治体ごとに微妙に異なる場合があるが、多くは約10%前後(都道府県民税4%、市町村民税6%など)だ。
2-2. 納付スケジュール:普通徴収と特別徴収
住民税は、次の2パターンのいずれかで納付する。
- 普通徴収:自分で納付書により支払う、もしくは口座振替などで納める
- 原則として、6月、8月、10月、翌年1月の年4回払いが多い。
- 特別徴収:給与支給時に天引きされ、勤務先がまとめて納付する
- 原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて給与天引きされる。
会社員のほとんどは「特別徴収」に当てはまる。特別徴収の場合、納付スケジュールは毎年6月から翌年5月までとなる。このため、5月分までの住民税は前年分、6月からの住民税は当年度分となり、ちょうど6月が“切り替え”のタイミングになるのだ。
3. 給与からの特別徴収が始まるタイミングについて
「住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?」を理解するうえで外せないのが、給与からの天引き(特別徴収)がなぜ6月スタートなのかという点である。
3-1. 前年分の所得確定後に税額が決まる
先述したとおり、住民税は前年の所得をもとに計算される。給与所得者(会社員・パート・アルバイトなど)の場合は、年末調整や確定申告を経て前年1月~12月分の所得が確定する。自治体がそれをもとに税額を算出し、5月頃に勤務先へ通知が送られる仕組みだ。
3-2. 6月以降に引き落としが始まる
通知を受けた勤務先は、6月給与の支給時から翌年5月の給与支給時まで、毎月一定額を天引きして納付する。これがいわゆる住民税の「特別徴収」であり、会社員にとっては自分で納付書を使わずに払える便利な仕組みといえる。
しかし、この仕組みこそが「住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?」という印象を与える元凶(?)だ。5月までは前年分の住民税が引かれ終わっているため、明細には住民税が反映されない。ところが、6月の給与から突然、住民税の項目が登場してガツンと天引きされる。「あれ、今月から急に?」と思われるのも無理はない。
4. なぜ「6月」に住民税が引かれることが多いのか?
前章の流れを見れば分かるように、住民税の特別徴収(給与天引き)は6月に始まることが「多い」というより、全国的に原則として6月にスタートする。この背景には、国が示す一定のルールと実務上の都合がある。
- 自治体が前年所得を確認するのに時間がかかる
- 前年分の確定申告や年末調整の情報を集計し、税額を算出するには少なくとも1~3月は必要。
- 5月頃に事業所へ通知書が届く
- 4月~5月に「特別徴収額の決定通知書」が事業所へ到着し、6月の給与から天引き開始できるタイミングとなる。
こうした手続きが全国的に同じ時期に行われるため、「6月=住民税の新年度スタート」はごく自然な流れなのだ。
5. 6月分は高く感じる?その理由も解説
「住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?」と同時に、「6月の住民税、やけに高くない?」と驚く人もいるだろう。実際、住民税の額は人によっては月々数万円になることもあり、所得税と同等かそれ以上に「痛い出費」に感じる場合がある。
5-1. 住民税は多くの控除が終わった“後”の課税
給与所得者の場合、年末調整で社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除などが適用された後の金額(課税所得)に対して、均等割+所得割がまとめて課される。また、住民税の計算式は所得税よりもシンプルだ。所得税は累進課税で税率が細かく変動するが、住民税はほぼ一律の税率(概ね10%前後)となるため、「住民税の方が思ったより高い」と感じる人が出てくる。
5-2. 所得が増えた場合、住民税も一気にアップ
前年から所得が上がると、当然住民税も増える。昇給やボーナスアップ、転職で給与が上がるなど、喜ばしいできごとの裏には、翌年の住民税がアップするというオマケ付きなのだ。これにより、5月までは安かった住民税が6月の切り替えでさらに高くなることもあるため、一層「6月だけ高い!」という印象を持ちやすい。
5-3. 支給額が大きい月に初回天引きが来るとインパクト大
企業によっては**6月に賞与(ボーナス)**を支給するケースがある。ボーナス支給月と住民税の天引き開始が重なると、なおさら「今月はなんだかものすごく引かれてる…」となるわけだ。賞与に対しても住民税は課されるため、ボーナスが増えた分だけ天引きも増えるということを覚えておきたい。
6. 6月に住民税が引かれないケースはある?
ここまで「住民税は6月から天引きされる」と説明してきたが、場合によっては6月になっても住民税が引かれないケースがある。どんな場合だろうか?
6-1. 勤務先での特別徴収が始まらない(手続きミスなど)
本来であれば5月頃に事業所へ特別徴収額の通知が届くが、事業所での対応が遅れたり、自治体とのやり取りに問題があったりして、6月の給与支給までに手続きが間に合わないことがある。その場合、7月以降にまとめて天引きが開始されるか、あるいは本人に普通徴収の納付書が送られてくることもある。
6-2. 前年の所得が0円、あるいは非課税限度額以下
前年の所得が非課税限度額以下だった場合、住民税そのものがかからない。たとえば、失業期間が長かったり、学生でアルバイト程度しか収入がなかったりするケースでは、6月になっても住民税が天引きされないことがある。
6-3. 住民税を「普通徴収」で納めている
会社員でも特別な事情があって、普通徴収にしている人がまれに存在する。この場合、給与天引きではなく、自分で納付書を使って年4回に分けて支払うため、給与明細には住民税の天引きがそもそも登場しない。そのため、6月であろうと天引きはされない。
7. 住民税にまつわるQ&A
ここでは、読者が疑問に思いそうな点をQ&A形式でまとめてみる。
Q1. 住民税の金額はどこで確認できる?
A. 住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)を見るのが一番正確だ。会社員の場合は勤務先経由で配布されたり、個人宛てで届いたりするので要チェック。また、給与明細を見れば月々の天引き額を確認できる。
Q2. 転職したら住民税はどうなる?
A. 住民税の支払い方法には、前の会社での支払いを継続(特別徴収を継続) する場合と、普通徴収へ切り替わる場合がある。転職時期や前職の処理状況によって異なるので、新しい会社の総務担当者に相談するとよい。
Q3. 自分が住んでいる自治体の住民税率を知りたい
A. 各自治体の住民税率や均等割の金額は、自治体の公式ウェブサイトで公開されている。詳細を知りたい人は「○○市 住民税」と検索すればOK。信頼性の高い情報としては、総務省のサイト(総務省公式サイト)なども参考になる。
Q4. 住民税を安くする方法はあるの?
A. いわゆる「節税」の一環として、ふるさと納税や所得控除(医療費控除、寄附金控除など)を利用することで、翌年の住民税が結果的に安くなることはある。ただし、すでに特別徴収が始まっている年度分を途中で下げるには、追加の確定申告や修正申告が必要になる場合があるので注意が必要だ。
8. まとめ:住民税が6月だけ引かれるのはなぜ?
最後に、記事の要点を振り返ってみよう。
- 「住民税が6月だけ引かれる」というのはあくまで見え方の問題。実際には6月から翌年5月まで毎月引かれている。
- 住民税は前年の所得をもとに計算され、税額通知が勤務先に届くのが5月頃。そのため、6月から新しい年度の住民税がスタートするのが一般的。
- 住民税には均等割と所得割があり、前年の所得に応じて支払う。所得が増えればその分住民税もアップするため、6月の給与明細で「こんなに高いの!?」となりやすい。
- 6月に天引きが始まらないケースもあるが、主に普通徴収を選択している場合や非課税限度額以下の場合、または事業所と自治体の手続きミスなどが考えられる。
住民税が6月だけ引かれるのはなぜか、その疑問は「住民税が前年所得を基準として6月から翌年5月までの12か月間で特別徴収される仕組みだから」と整理できる。つい先月まで天引きがなかった人にとっては突然の出費に感じられるが、「どの時期にどれくらい引かれるのか」をあらかじめ把握しておくことが家計管理には有効だ。
もし自分の住民税について「高すぎるのでは?」「計算が合わないのでは?」と疑問があれば、市区町村の税務課や会社の総務担当に確認するのが確実だ。いざというときのために正しい知識を身につけ、賢く対応していこう。
この記事がみなさんの「そもそも6月だけ引かれるのはどういうこと?」というモヤモヤを解消し、明るく家計管理をする一歩となれば幸いである。たしかに税金は痛い出費かもしれないが、知ってしまえばそこに謎のストレスは感じなくなる。謎が解ければ、あとは少しでもお得な控除や節税策を探すという、前向きな行動につなげるのみだ。