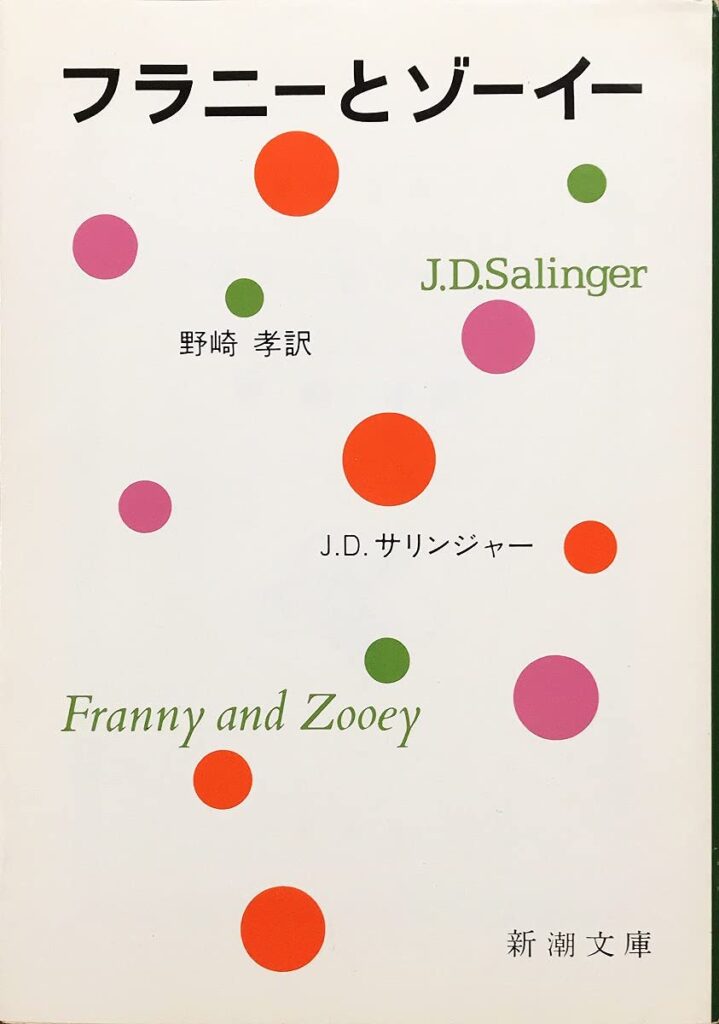太宰治の「もの思う葦」は、1940年に発表された短編作品で、人間の弱さと矛盾を鋭く描写した自伝的作品です。主人公である「私」は作家としての活動に悩み、自らの無力さや逃避願望に葛藤しながら日々を過ごします。家族や他人との関わりを通じて孤独を深め、さらに自分の弱さを許容できないまま苦しみ続けます。
タイトルの「もの思う葦」はパスカルの「人間は考える葦である」に由来し、人間が考えることゆえに悩み、苦しむ姿を象徴しています。作中で主人公は自らの矛盾に気づきつつも、それを克服できない無力感を抱え続けます。
- 太宰治の「もの思う葦」の概要
- 主人公の葛藤と人間の弱さ
- 「考える葦」の意味とその象徴
- 主人公が抱く無力感と孤独
- 自伝的要素を含む太宰の作風
「もの思う葦(太宰治)」の超あらすじ(ネタバレあり)
「もの思う葦」は、太宰治が自己の弱さと人間の矛盾を鋭く描き出した短編作品です。
物語は、主人公であり作家の「私」が、自らの精神的な脆弱さや世間との葛藤に苛まれながら、日々を過ごす様子を描いています。この「私」は、太宰自身を投影したような存在であり、周囲からの期待と現実の自分の狭間で揺れ動く姿が物語の中心となります。
物語の序盤で、「私」は自らの作家としての活動に関して、非常に深い不安と自信喪失を抱いていることが明かされます。
彼は「文学とは何か」「自分は何のために書いているのか」という根本的な問いに対して、答えを見出せずに悩んでいます。
周囲からは「作家」としての期待を向けられますが、それに応えることができない自分に強い嫌悪感を抱き、自らを責め続けます。
特に、作品を世に出してもその価値を信じられず、自分の創作活動が無意味であるかのように感じ、どこか逃避的な心情を持つようになります。
さらに、「私」は家庭生活においても多くの葛藤を抱えています。
家族との関係はどこかぎこちなく、彼は家族に対して表面的には優しさを見せるものの、内心では自分が期待されている役割を果たせないことへの疎外感と自己嫌悪に苛まれています。
彼の妻や周囲の人々は、「私」に対して一定の理解を示しつつも、心の奥底にある孤独や不安を完全に理解することはできません。
このようにして「私」は家庭内でも孤立し、誰にも理解されないという感覚を深め、ますます心の中で自己崩壊を感じるようになります。
作品の中盤から後半にかけて、「私」は幾度も「逃げたい」「楽になりたい」という衝動に駆られるようになります。
しかし、同時にその逃避の衝動に駆られる自分を「卑怯」だと断罪し、自らを否定してしまいます。
このような「逃げることへの葛藤」は、彼の心の中でますます強まっていきます。彼は自分自身を見つめ直すことで、その「弱さ」を認めつつも、それを許容することができません。
周囲の人々が抱く「作家」としての理想像との乖離に苦しみ、自分が持つ「弱さ」をどうしても受け入れることができないため、彼はますます孤独を深めていくのです。
物語の終盤、「私」はふとした瞬間に「人間は考える葦である」というパスカルの言葉を思い出します。
人間はただの脆弱な存在に過ぎないが、考えることができるがゆえに苦しむというこの言葉に、彼は自分の姿を重ね合わせます。
彼は、考えること、苦しむことそのものが人間としての本質であることを悟り、そしてその苦しみが自分の存在を定義していることに気づきます。
しかし、その気づきは決して救いには至りません。
彼は「考えること」をやめることもできず、「弱さ」を認めることもできないまま、自己矛盾の中で生き続けることを選ぶのです。
こうして、「もの思う葦」は、主人公が自らの矛盾や脆さに気づきながらも、それを克服することなく、ただそれに苦しみ続ける様子を描いています。
太宰治特有の内省的で繊細な筆致が、主人公の心の揺れを丁寧に描き出し、「考える葦」としての人間の本質を示唆する作品となっています。
考えるがゆえに苦しむ「人間の弱さ」と、「逃げることもできない自分」に対する無力感が、切実に綴られているのです。
「もの思う葦(太宰治)」の感想・レビュー

太宰治の「もの思う葦」は、短編ながらも人間の深い内面と矛盾を描き、読み手に強い印象を与えます。この作品の主人公「私」は、太宰自身を投影した存在であり、彼の作品にはしばしば登場する「自己嫌悪」や「逃避の願望」に彩られています。作家としての期待やプレッシャー、そしてその期待に応えられない無力感に苛まれながらも、主人公は逃げることができない状況に陥っています。
作中で「私」は、作品を書くことに対する迷いや恐れを抱え、「作家」としての理想と現実の自分の間で揺れ動きます。自分が世間の期待に応えられないことや、創作活動の意義を見失ってしまうことへの葛藤は、太宰自身の実体験が色濃く表れているように感じられます。特に、創作に対する苦悩や周囲の期待に対するプレッシャーが、主人公の精神に重くのしかかっている様子は、読者に太宰自身の苦しみを投影させています。
また、「私」が家庭内で抱える孤独や疎外感は、彼が一人で生きているような感覚をさらに強めます。家族や友人が彼を理解してくれるとは限らず、表面的な関係の中で、主人公はますます孤立していきます。作品全体に描かれている抽象的な人間関係は、どこか距離感があり、親密さを感じさせない点が印象的です。
タイトルの「もの思う葦」は、パスカルの「人間は考える葦である」に由来しています。主人公は「考える」という行為によって苦しみ、「弱さ」を許容できない自分に苦悩します。人間はただ考えるだけでなく、それゆえに葛藤を抱え、さらには自己嫌悪に陥ってしまう。そのような「考える存在」としての弱さが、主人公の生き方に重くのしかかります。考えることが人間の本質であると悟りつつも、その苦しみが解消されない状況に、彼は「逃げ場のない自分」を感じ続けるのです。
結末では、主人公が何か解決策を見出すことなく、自らの矛盾を抱えたまま生き続ける様子が描かれます。読者としては、この「解決しない」という選択に戸惑いを覚えるかもしれませんが、それこそが太宰が描きたかった人間の姿なのでしょう。彼は、人間が抱える「弱さ」や「矛盾」は本質的に解決不可能であり、それを抱えて生きていくしかないというメッセージを込めています。
全体を通じて、「もの思う葦」は太宰治の自伝的要素が強く、彼の内面に潜む「逃げ場のなさ」や「人間の無力さ」を見事に描き出しています。
まとめ:「もの思う葦(太宰治)」の超あらすじ(ネタバレあり)
上記をまとめます。
- 1940年発表の短編作品である
- 主人公は作家としての悩みを抱えている
- 自らの無力さに深い自己嫌悪を抱く
- 家族との関係に孤独を感じている
- 主人公は「逃避願望」を抱き続ける
- タイトルはパスカルの名言に由来する
- 人間の弱さと矛盾を主題としている
- 自己矛盾の中で生き続ける結末である
- 抽象的な描写が多いのが特徴である
- 太宰治の自伝的要素が強く反映されている