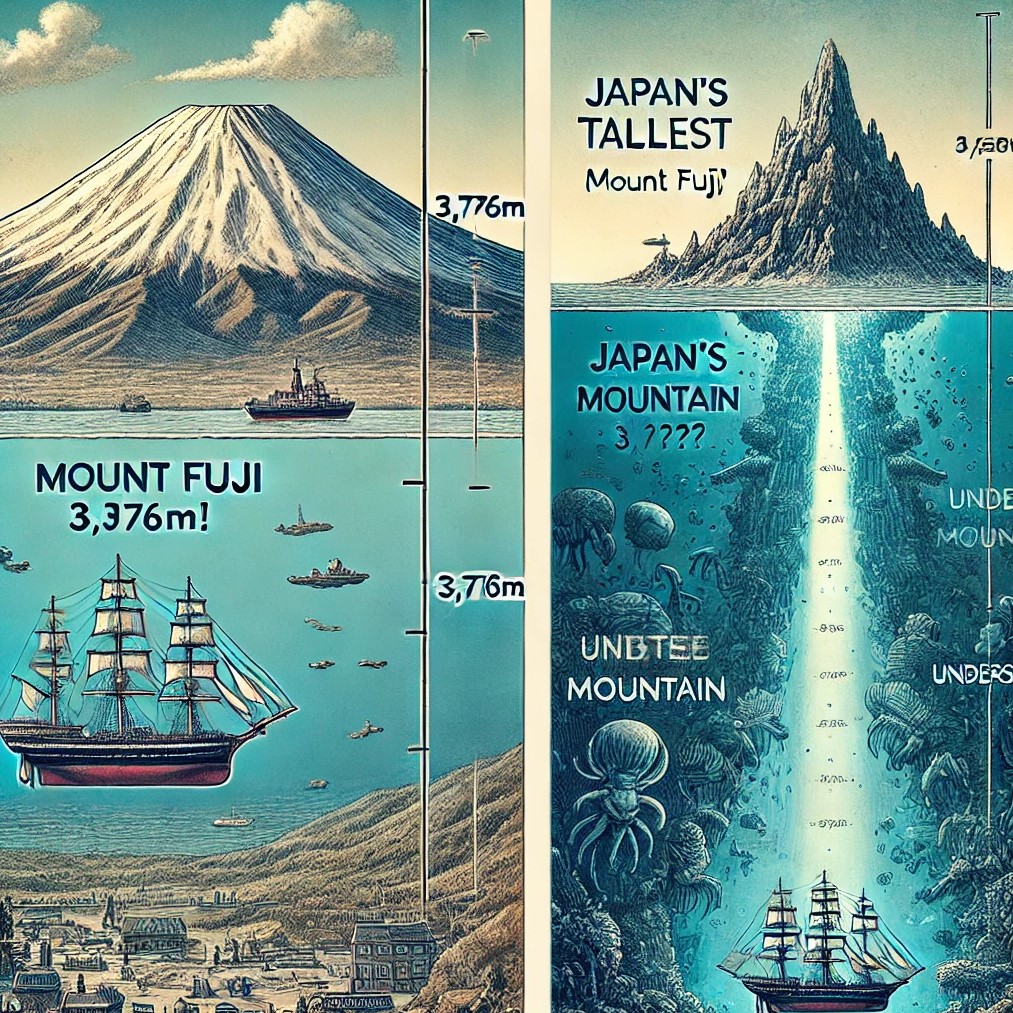台風のニュースで「大型で非常に強い勢力の台風が…」と聞くと、身構えてしまいますよね。でも、昔の日本人が、この嵐をどう呼んでいたか知っていますか?実はそこには、自然を恐れ、敬い、時には美しささえ見出した、日本人の豊かな心が隠されています。
この記事では、「台風の古い呼び名」をキーワードに、単なる気象現象ではない、日本の文化や歴史に深く根ざした「風の物語」を紐解いていきます。「野分(のわき)」という美しい言葉から、農民の祈りが込められた「二百十日(にひゃくとおか)」、そして私たちが当たり前に使う「台風」という言葉の意外なルーツまで。この記事を読み終える頃には、空を渡る風の音が、これまでとは少し違って聞こえてくるかもしれません。
-
平安時代の貴族が愛した風の呼び名「野分」の美しい世界
-
農家の祈りと知恵が詰まった厄日「二百十日」の意味
-
「台風」という言葉がどこから来たのか、その意外な語源の旅
-
沖縄の「カジフチ」など、日本各地に残るユニークな風の呼び名
-
嵐を神様として崇めた「風神信仰」と、芸術に描かれた風の姿
「野分」に込められた美意識【台風の古い呼び”名”の代表格】
今でこそ秋の嵐は「台風」ですが、昔、特に平安時代の文学の世界では「野分(のわき)」という美しい名前で呼ばれていました。この言葉は、ただの天気を表す言葉ではありません。そこには、日本ならではの美意識や季節感がぎゅっと詰まっています。ここでは、台風の古い呼び名の代表格である「野分」の世界を探ってみましょう。
「野分」とは?- 風が野を分ける詩的な風景
「野分」という言葉の響き、なんだか雅やかだと思いませんか?その意味は、漢字の通り「野の草を分けるように吹く風」です。秋の野原に生い茂った草むらを、強い風がざわざわと吹き分けていく。そんな光景が目に浮かぶような、とても詩的な表現です。
この「野分」は、季節を問わない「嵐」とは区別されていました。特に、稲刈りの時期と重なる旧暦8月頃(現在の9月から10月頃)に吹く、秋特有の強い風を指していました。
そして面白いことに、「野分」にはただ「怖い」「破壊的」というイメージだけではなく、どこか物悲しい風情や、しみじみとした趣、つまり日本の古典的な美意識である「あはれ」や「をかし」といった感覚が結びついていました。激しい自然現象の中にさえ、はかなくも美しい何かを見つけようとする、昔の日本人の繊細な感性が表れていますね。
『源氏物語』と『枕草子』に描かれた「野分」
この「野分」という言葉を、日本の二大古典文学である『源氏物語』と『枕草子』は、それぞれ全く違う視点から描いています。
『源氏物語』のドラマ装置「野分」
『源氏物語』には、そのものずばり「野分」というタイトルの巻があります。物語の中で野分は、ただの背景ではありません。登場人物たちの運命を大きく動かす、重要な役割を担っています。
主人公・光源氏が36歳の秋、屋敷を激しい野分が襲います。この風が、いつもは閉ざされている御簾(みす)を吹き上げ、源氏の息子である夕霧は、父の最愛の妻・紫の上の姿を偶然見てしまうのです。その美しさに衝撃を受けた夕霧の心は、大きく揺れ動きます。このように、野分は人間関係の壁を壊し、隠された想いをあぶり出す、物語の起爆剤として使われました。
『枕草子』の美的対象「野分」
一方、『枕草子』の作者・清少納言は、野分に対してまったく違う見方をします。彼女は、嵐が吹き荒れている最中ではなく、その翌朝の景色にこそ面白さがある、と言いました。
野分のまたの日こそ、いみじうあはれに、をかしけれ。
(野分が吹いた翌朝こそ、本当にしみじみと心惹かれる趣がある。)
倒れた仕切りや、めちゃくちゃになった庭の草花。大きな木の枝が萩の上に横たわっている様子。そんな無秩序な風景を見て、清少納言は「思いがけなくて面白い」と感じるのです。特に、格子戸に木の葉がまるで誰かがデザインしたかのように貼り付いている様子を、興味深く観察します。破壊の跡に新しい美を見出す、とてもユニークな感性ですよね。
俳句に詠まれた「野分」と日本人の感性
「野分」は、秋の季語として俳句の世界でも愛されてきました。多くの俳人が、この言葉で風の持つ力を表現しようとしました。
吹飛ばす石は浅間の野分かな 松尾芭蕉
この句では、野分の力が、浅間山の火山噴火という、もっと巨大な自然の力と結びつけられています。石ころさえ吹き飛ばす風の強さが、ダイナミックに伝わってきます。
大いなるものが過ぎ行く野分かな 高浜虚子
こちらは具体的な描写をせず、「大いなるもの」という言葉で野分を表現しています。目に見える風の姿だけでなく、その背後にある何か計り知れない存在への畏敬の念を感じさせる、深い句です。
これらの句を読むと、昔の人々が「野分」という言葉で、雨や洪水よりも、風そのものの持つ力や音、風景を変えてしまう作用に強く惹かれていたことがわかります。科学的なデータで語られる「台風」とは違う、もっと身体で感じる「風の体験」が、この古い呼び名には刻まれているのです。
暮らしと共存した恐怖【農耕文化と台風の古い呼び名】
平安貴族が「野分」に詩や物語を重ねていた頃、日本の多くの人々、つまり農民にとって、秋の嵐は全く違う意味を持っていました。それは生活を根こそぎ破壊しかねない、現実的な恐怖そのもの。ここでは、美的な世界から一転、農耕社会が生んだ、切実な台風の古い呼び名と文化を見ていきましょう。
なぜ怖い?厄日「二百十日」と稲作
農家の人々が台風をどれほど恐れていたか。それを象徴するのが「二百十日(にひゃくとおか)」と「二百二十日(にひゃくはつか)」という日です。
これは、春の始まりである「立春」から数えて210日目(今の暦で9月1日ごろ)と220日目(9月11日ごろ)のこと。昔からの経験で、一年で最も台風が来やすい「厄日(やくび)」として、カレンダーに刻まれるほど警戒されていました。
なぜなら、この時期は稲が花を咲かせる、一年で最もデリケートなタイミングだったからです。もしこの「稲の開花期」に強い風雨に襲われると、花が落ちて受粉ができず、お米が実らなくなってしまいます。一年間の苦労が水の泡となり、食べるものにさえ困ってしまう。だからこそ、この二つの日は「農家の三大厄日」と呼ばれ、固唾をのんで過ごす日だったのです。この知恵は非常に重要視され、江戸時代の公式なカレンダーにも記載されるほどでした。
風を鎮める祈り「風祭」と「おわら風の盆」
「厄日」をただ恐れるだけでなく、人々はその災いを避けようと、様々な儀式を生み出しました。それが「風祭(かざまつり)」または「風鎮祭(ふうちんさい)」と呼ばれる、風の神様を鎮めるお祭りです。
これらの祭りは、二百十日の前後を中心に、今も日本全国で行われています。その目的は、荒れ狂う風の神様をなだめ、作物をなぎ倒す「荒風」を、実りをもたらす「恵みの風」に変えてもらうことです。
代表的な風祭
-
おわら風の盆(富山県富山市)
編笠を目深にかぶった人々が、哀愁のある音楽に合わせて静かに踊り歩く、幻想的なお祭りです。風に逆らうのではなく、その力を優雅に受け流すような踊りは、風を鎮めたいという祈りを体現しているかのようです。
-
大谷風神祭(山形県朝日町)
神輿や山車が練り歩き、豊作を祈願する賑やかなお祭りです。
また、もっと直接的なおまじないもありました。屋根の上や竿の先に鎌を取り付け、刃を風の来る方角に向ける「風切り鎌」という風習です。鋭い刃が、目に見えない風を断ち切ってくれると信じられていました。農具という身近な道具で、巨大な自然の力に対抗しようとした、人々の切実な願いが伝わってきます。
経験が作った知恵 – 「厄日」から「防災の日」へ
「二百十日」が持つ「災いの日」という記憶は、現代の私たちにも繋がっています。
1923年9月1日、日本を襲った関東大震災。この未曾有の災害が起きたのが、偶然にも二百十日の当日でした。このことは、この日が持つ不吉なイメージを決定的なものにしました。さらに、戦後には伊勢湾台風という大きな災害も経験します。
これらの教訓から、日本政府は1960年、関東大震災が起きた日であり、伝統的な厄日でもある9月1日を「防災の日」と定めました。これは、昔ながらの経験と信仰に基づいた「厄日」という考え方が、科学的な知識に基づいた「防災」という現代的な行動へと姿を変えた瞬間でした。
今、私たちは9月1日に避難訓練をします。それは、かつての人々が風祭で神様に祈ったように、形は変われど、自然の脅威に備えようとする共同体の心が、現代にも受け継がれている証なのです。
「台風」という言葉の誕生【意外と知らない台風の語源】
私たちが当たり前に使っている「台風」という言葉。実は「野分」や「二百十日」といった日本古来の言葉とは違い、近代日本のグローバル化の中で生まれた、比較的新しい言葉です。その言葉がどうやって生まれ、定着したのか。その道のりは、まるでミステリーのようで、日本の近代化の歴史そのものが隠されています。台風の古い呼び名から、現代の呼び名へのバトンタッチの物語です。
語源はギリシャ語?「typhoon」を巡る旅
「台風」が英語の「typhoon」とそっくりなのは、誰もが気づくことでしょう。では、その「typhoon」はどこから来たのでしょうか?これにはいくつかの説がありますが、現在はギリシャ・アラビア語をルーツとする説が最も有力です。
-
ギリシャ・アラビア語源説(最有力)
もともと、嵐や洪水を意味するアラビア語の「ṭūfān(トゥーファン)」という言葉がありました。これが大航海時代、海の商人たちによってヨーロッパに伝わり、英語の「typhoon」になった、という説です。さらに、ギリシャ神話に登場する巨大な怪物「テュフォン(Typhon)」のイメージも影響したと考えられています。
-
中国語源説(俗説)
「大きな風」を意味する中国語「大風(タイフン)」や、「台湾から来る風」が語源だ、という説も有名ですが、学術的には少し疑問視されています。
面白いのは、「颱風」という漢字表記です。これは、西洋から伝わった「typhoon」という音を聞いた昔の日本人が、その音に合う漢字として「颱風」を当てはめた「当て字」だった、という説が有力です。つまり、「颱風」が「typhoon」になったのではなく、「typhoon」の音に合わせて「颱風」という言葉が日本で作られた、というわけです。言葉のグローバルな旅の果てに、私たちの使う言葉があると思うと、なんだか壮大ですよね。
明治時代に定着した「台風」という言葉
明治時代になり、日本が近代的な気象観測を始めると、暴風雨を指す公式な言葉が必要になりました。最初は「颶風(ぐふう)」という難しい漢語が使われていましたが、あまり一般的ではありませんでした。
そんな中、当時の中央気象台長だった岡田武松という人物が、「颱風」という言葉を積極的に使い始めます。国の機関である気象台が使う言葉として、また、国際的な「typhoon」とも通じる言葉として、「颱風」は急速に社会に広まり、標準語として定着していきました。
そして戦後、難しい漢字を簡単な字に改める国語改革が行われ、「颱」は同じ音の「台」に置き換えられました。こうして、今私たちが使う「台風」という表記が誕生したのです。
台風の名前はどう決まる?番号からアジア名へ
言葉の統一と同時に、一つ一つの台風を区別するための名前の付け方も変わってきました。
|
時期 |
命名方法 |
特徴 |
|
~1999年 |
番号+災害名 |
「台風第1号」のように番号で呼び、大きな被害が出たものだけ「伊勢湾台風」のように後から地名をつけた。 |
|
~1999年 |
米国式英語名 |
アメリカ軍がつける英語名(キャサリン、アイダなど)が国際的に使われていた。 |
|
2000年~ |
アジア名 |
日本を含むアジアの14の国と地域が提案した140個の名前を順番に使っている。 |
2000年からは、アジア各国が協力して決めた「アジア名」が使われています。日本からは「コイヌ(こいぬ座)」や「ヤギ(やぎ座)」、「コト(こと座)」など、星座にちなんだ、穏やかで中立的な10個の名前が提案されています。この名前のリストは繰り返し使われ、大きな被害を出した台風の名前は引退(除名)となり、新しい名前に交代します。
詩的な「野分」から、科学的な「台風」へ。そしてアメリカ主導の英語名から、アジアで協力するアジア名へ。嵐の名前の移り変わりは、日本の社会や国際的な立ち位置の変化そのものを映しているのです。
日本各地のユニークな風【地域に根付く台風の古い呼び名たち】
国が「台風」という言葉で統一する一方で、日本各地には、その土地ならではの風の呼び名が、今もたくさん息づいています。それらは、風がその地域でどんな「顔」をしているのかを教えてくれる、生きた文化遺産です。ここでは、公式な名前の裏に広がる、豊かでユニークな「ご当地風」の世界を覗いてみましょう。台風の古い呼び名を探す旅は、ローカルな世界へと広がります。
沖縄「カジフチ」と鹿児島「うかぜ」
台風の通り道として知られる南西諸島や九州には、標準語とは違う、独自の呼び名が古くから伝わっています。
-
沖縄の言葉
-
カジフチ: 沖縄の方言「ウチナーグチ」で、伝統的に台風や暴風を指す言葉。「風吹き」という意味で、風が吹くという現象をそのまま名前にした、力強い言葉です。
-
テーフー: こちらは標準語の「台風」が沖縄風の発音になった、比較的新しい言葉。古い「カジフチ」と新しい「テーフー」が一緒に使われているところに、沖縄の歴史が感じられますね。
-
-
鹿児島の言葉
-
うかぜ: 九州の南端、鹿児島では、台風を「うかぜ」と呼ぶことがあります。これは「大風(おおかぜ)」という言葉の音が変化したもので、沖縄の「カジフチ」と同じように、風の強さを素直に表現した名前です。
-
これらの言葉は、ただの方言というだけではありません。それぞれの地域の人々が、自分たちの暮らしの中で台風と向き合い、それに名前を与えることで、その記憶を次の世代に伝えてきた証なのです。
日本三大悪風「やまじ風」「広戸風」「清川だし」とは
台風のような広い範囲の嵐とは別に、特定の地域だけに吹く強い風「局地風(きょくちふう)」があります。中でも、特に風が強く、被害をもたらすことから「日本三大悪風」と呼ばれる風があります。
局地風のいろいろ
-
やまじ風: 愛媛県東部で、法皇山脈から春と秋に吹き下ろす南寄りの強風。
-
広戸風(ひろとかぜ): 岡山県北部で、那岐山のふもとに吹く北寄りの暴風。
-
清川だし: 山形県庄内地方で、最上川の谷を抜けて吹く南東の強風。
この他にも、夏に東北地方の太平洋側に吹いて冷害をもたらす「やませ」や、冬に関東平野を吹き抜ける乾燥した「からっ風(上州空っ風)」、阪神タイガースの歌で有名な「六甲颪(ろっこうおろし)」など、日本には数えきれないほどの局地風があります。これらの名前は、その土地の地形や暮らしと深く結びついており、地域のアイデンティティの一部となっています。
漁師たちが使う風の言葉「ならい」「あいのかぜ」
海で生きる漁師さんたちは、船の安全や漁の結果を左右する風に対して、陸に住む人とはまた違う、専門的で細やかな言葉を持っています。
-
ならい: 主に冬に吹く北風や北西風のこと。日本海側で広く使われます。
-
あいのかぜ / あゆのかぜ: 夏に沖から陸へ吹く、穏やかな東風や南風。船を出すのに都合が良いため、恵みの風とされていました。
-
こち: 春を告げる東風。和歌にも詠まれる美しい響きの言葉です。
-
はえ: 南風のこと。西日本で広く使われます。
漁師さんたちは、風を方角や季節によって細かく分類し、それぞれに名前をつけていました。これは、彼らにとって自然と共存するための「生きるためのマニュアル」そのものだったのです。
これらの地域ごとの言葉は、気象庁が発表する科学的な情報とは別に、人々が自分たちの環境と対話しながら育ててきた、もう一つの知識体系の存在を教えてくれます。「台風」という公式な言葉と、地域ごとの呼び名が共存している現状は、日本の文化の奥深さを示しているのかもしれません。
神か、妖怪か【風神信仰にみる台風の古い呼び名の背景】
科学で解明できなかった時代、人々は台風のような巨大な力を、単なる自然現象とは考えませんでした。それは神様の仕業であり、妖怪のしわざであり、芸術家たちの想像力をかき立てる不思議な存在でした。ここでは、風が人々の心の中でどのように神や怪物、そしてアートになっていったのか、その精神世界を旅してみましょう。この旅は、台風の古い呼び名が生まれた背景にある、日本人の根源的な信仰心に触れることになります。
風の神を祀る「龍田大社」と風神信仰
コントロールできない風の力は、古くから神様として崇められ、信仰の対象となってきました。この風神信仰の中心地として、昔から大きな力を持ってきたのが、奈良県にある龍田大社(たつたたいしゃ)です。
ここでは毎年、風を鎮めるお祭り「風鎮祭」が行われます。その祝詞(のりと)には、古代の日本人の切実な願いが込められています。それは、作物をダメにする破壊的な「荒風」を、稲の実りを助ける穏やかな「和風(にぎかぜ)」に変えてください、という祈りです。
この風神様への信仰は、農業の守り神だけにとどまりません。風が船の帆を動かすことから、船旅の安全、さらには現代では飛行機の安全を祈る人々も訪れます。風という見えない力を理解し、それとどうにかうまく付き合っていきたいという、人間の根源的な願いが、この風神信仰には表れています。
怪物としての風 – 妖怪「一目連」と龍の伝承
恐ろしい気象現象は、時に超自然的な存在、つまり妖怪や龍の仕業だと考えられました。
-
一目連(いちもくれん): 三重県に伝わる、神様でもあり妖怪でもあるような存在。旅に出る時に嵐を巻き起こす一方で、人々が祈ればその災いから救ってくれる力も持つとされています。嵐がもたらす「破壊」と「救い」という二つの顔を、一身に持った存在です。
-
龍(りゅう): 東アジアでは、龍は水と天候を操る神聖な生き物です。激しい嵐や、海上で渦を巻く竜巻は、まさに龍が天と地を行き来する姿そのものだと考えられていました。
これらの伝承は、怖い自然現象に具体的なキャラクターや物語を与えることで、それを理解し、心の中で整理しようとした昔の人の知恵でした。同時に、「自然を甘く見てはいけない」という、防災意識の原型ともいえる教訓を、物語として語り継ぐ役割も果たしていたのです。
芸術になった嵐 – 俵屋宗達「風神雷神図屏風」
目に見えない風の力を、どうやって絵に描くか。この難しい挑戦に、日本の芸術家たちは見事な答えを出しました。
その最高傑作が、国宝にもなっている俵屋宗達の「風神雷神図屏風」です。宗達は、風の神様を、大きな風の袋を抱えて空を駆け巡る、力強い鬼のような姿で描きました。これは、ただのシンボルではありません。風そのものが持つ、荒々しくコントロール不能なエネルギーが、人格を持った姿として描かれているのです。
この傑作は、後の芸術家にも大きな影響を与えました。江戸時代の絵師・酒井抱一は、宗達の屏風の「裏側」に、風に揺れる秋の草花を描きました(夏秋草図屏風)。表の風神(原因)と、裏でなびく草花(結果)がセットになることで、見る人は目に見えない風の力を、よりリアルに、詩的に感じることができます。自然現象に対する、これ以上なく洗練された芸術的な表現と言えるでしょう。
まとめ:風の音に耳を澄ませば、日本の心が見えてくる
「台風の古い呼び名」を巡る旅、いかがでしたか?
詩的な響きを持つ「野分」、農民の切実な祈りが込められた「二百十日」、そしてグローバル化の中で生まれた「台風」。これらの言葉の移り変わりは、ただの単語の変化ではありません。それは、日本の社会が、自然とどう向き合い、どのように世界と関わってきたかという、壮大な歴史そのものを映し出しています。
また、沖縄の「カジフチ」や各地の「〇〇おろし」といった地域ごとの呼び名は、それぞれの土地の人々が、自然と対話しながら生きてきた証です。風の神を祀る信仰や、風を描いた芸術は、目に見えない力に意味を与え、共存しようとしてきた日本人の豊かな精神世界を物語っています。
次に台風のニュースを聞いた時、あるいは秋の強い風が窓を揺らす音を聞いた時。この記事で紹介した言葉たちを、少しだけ思い出してみてください。いつもの自然現象が、もっと深く、豊かな物語を持つ、文化的な存在に見えてくるはずです。
そしてぜひ、あなたがお住まいの地域に伝わる、特別な風の呼び名や言い伝えがないか、探してみてはいかがでしょうか。きっとそこにも、先人たちが残した面白い物語が隠されていますよ。