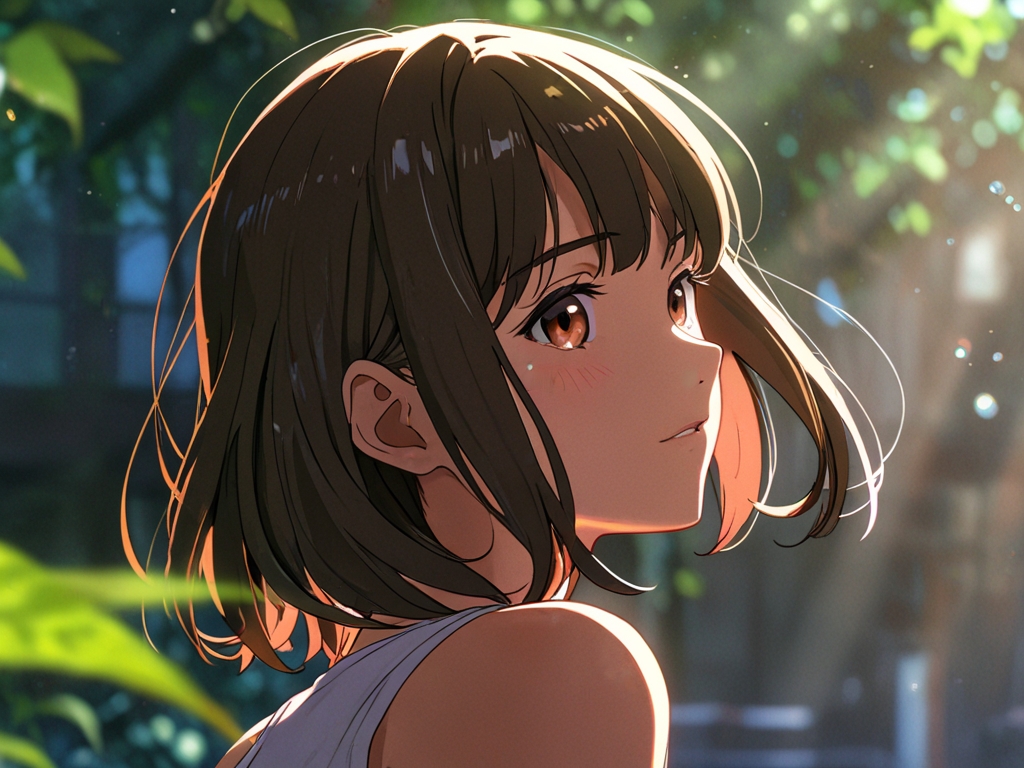みんな大好きなラーメン。誕生日や給料日など、特別な日に「ごちそう」として食べる人も多いのではないでしょうか。では、そんなラーメンそのものに記念日があることはご存知ですか?
実は、7月11日は「ラーメンの日」という記念日なんです。この記念日、単なる語呂合わせではなく、そこには日本のラーメン文化の奥深い歴史と、業界のちょっとした戦略が隠されています。「なぜ7月11日なの?」「誰が作ったの?」そんな疑問が次々と湧いてきますよね。
この記事では、「ラーメンの日」にまつわるあらゆる情報を、歴史の裏話から最新の業界事情まで、まるっと解説していきます。この記事を読み終わる頃には、あなたもラーメン博士になっていること間違いなし。そして、次の一杯がもっと美味しく、もっと楽しく感じられるはずです。さあ、一緒にラーメンの奥深い世界へ旅立ちましょう。
-
ラーメンの日は毎年7月11日
-
由来は「レンゲと箸」の見たてと「水戸黄門の誕生日」
-
夏のラーメン消費を増やすという商業的な目的がある
-
「日本初のラーメン」には水戸黄門より古い室町時代の説も存在する
-
ラーメン業界は様々な課題を乗り越え、技術革新と共に世界へ広がっている
ラーメンの日とは?いつ・なぜ制定された記念日なの?
ラーメン好きなら知っておきたい「ラーメンの日」。まずは、この記念日がいつで、どのような由来で制定されたのか、基本的な情報から見ていきましょう。一見単純な記念日に見えますが、そこには遊び心と歴史への敬意が込められています。
ラーメンの日は毎年「7月11日」
結論から言うと、ラーメンの日は毎年7月11日です。この記念日は、ラーメン産業の発展を目指す一般社団法人日本ラーメン協会によって2017年に制定され、日本記念日協会に正式に登録されました。比較的新しい記念日ですが、ラーメン業界を盛り上げるための大切な一日と位置づけられています。
なぜこの日が選ばれたのでしょうか。その理由は、ラーメンを食べる私たちにとって、とても身近でユニークな発想から来ています。次の項目で、その面白い由来を詳しく見ていきましょう。
私が子供の頃には「ラーメンの日」なんてありませんでした。ポッキーの日(11月11日)のように、企業や業界がマーケティングのために記念日を作る流れが、ここ10年ほどで一気に加速したように感じます。ラーメンの日もその一つですが、単なる販促イベントで終わらせず、日本の食文化として根付かせようという意志が感じられるのが興味深い点です。7月11日が、将来バレンタインデーのように誰もが知るイベントになるかもしれませんね。
なぜ7月11日?2つの面白い由来
ラーメンの日が7月11日である理由は、主に2つあります。一つはユニークな見たて、もう一つは歴史上の人物へのリスペクトです。
一つ目の理由は、ラーメンを食べるシーンを数字で表現した、見事な言葉遊びです。数字の「7」を、スープをすくう「レンゲ」に見立てています。そして「11」を、麺をすする「箸(はし)」に見立てています。7と11を並べると、まるでラーメンセットのように見える、というわけですね。この覚えやすくてキャッチーな発想が、記念日を広める上で大きな役割を果たしています。
二つ目の理由は、歴史的な裏付けです。「日本で最初にラーメンを食べた」とされる人物、水戸藩主の徳川光圀、通称「水戸黄門」の誕生日にちなんでいます。彼の誕生日が、旧暦ではなく新暦で1628年7月11日なのです。国民的なヒーローである水戸黄門と国民食のラーメンを結びつけることで、記念日に物語と権威性を持たせているのです。この2つの由来を知ると、7月11日という日付がとても特別なものに感じられませんか?
【裏話】ラーメンの日が作られた本当の理由
「レンゲと箸、そして水戸黄門」という文化的で面白い由来を持つラーメンの日。しかし、この記念日が作られたのには、もう一つ、非常に現実的で戦略的な理由が存在します。ここでは、ラーメンの日が制定された、いわば「大人の事情」に迫ってみましょう。
夏のラーメン需要を増やすためのマーケティング戦略
なぜ記念日を作る必要があったのか。その最大の理由は、夏の売上低下というラーメン業界が抱える深刻な課題を解決するためです。暑い夏になると、多くの人々はそうめんや冷やし中華、そばといった、さっぱりとした冷たい麺類を選びがち。その結果、熱々のスープが基本のラーメン店の売上は、どうしても落ち込んでしまいます。
そこで日本ラーメン協会は、「夏のラーメン消費量を拡大する」ことを明確な目標として掲げ、7月11日を「ラーメンの日」と定めました。これは、夏にもラーメンを食べるきっかけを作り出すための、意図的なマーケティング戦略なのです。「夏の暑さを吹き飛ばす 日本のパワーフード」といったキャッチコピーは、ラーメンを夏バテ防止のスタミナ食として再定義(リポジショニング)しようという狙いの表れです。記念日制定は、単なるお祭りではなく、業界全体の課題に立ち向かうための重要な一手だったのです。
全国のお店でお得なキャンペーンも!
この戦略を成功させるため、ラーメンの日当日やその前後には、日本ラーメン協会に加盟する多くの店舗で、様々なキャンペーンが実施されます。
🍜 ラーメンの日キャンペーンの例
-
特別メニューの提供: 夏向けの冷やしラーメンや、その日限定の特別ラーメンが登場する。
-
無料トッピング: 味付け玉子やチャーシュー、メンマなどのトッピングが一つ無料になるサービス。
-
麺の大盛りが無料: 通常は追加料金がかかる麺の大盛りが、無料で楽しめる。
-
割引サービス: ラーメン一杯が100円引きになるなど、直接的な割引。
このようなお得なキャンペーンは、消費者にとってラーメン店へ足を運ぶ強い動機になります。私も数年前のラーメンの日に、近所のお店で「味玉サービス」の貼り紙を見て、ついフラフラと入ってしまった経験があります。普段は頼まないトッピングを追加できると、なんだか得した気分になりますよね。こうした小さなきっかけ作りが、夏のラーメン市場を盛り上げる大きな力になっているのです。
-
公式サイトをチェック: 一般社団法人日本ラーメン協会のウェブサイトで、参加店舗のリストやキャンペーン情報が公開されることがあります。
-
SNSで検索: X(旧Twitter)やInstagramで「#ラーメンの日」と検索すると、各店舗が発信するリアルタイムのキャンペーン情報を見つけられます。
-
お気に入りのお店の情報を追う: 普段からよく行くラーメン店のSNSアカウントや公式サイトを、7月上旬にチェックしてみましょう。
ラーメンの歴史を深掘り!「ラーメンの日」の由来は本当?
ラーメンの日の由来として「日本で最初にラーメンを食べた水戸黄門」という話をご紹介しました。この物語は、ラーメンの歴史を語る上で欠かせないエピソードです。しかし、近年の研究で、この説を覆すかもしれない新たな事実が発見されました。ここでは、ロマンあふれるラーメンの起源を巡る物語を探っていきます。
定説:日本で最初にラーメンを食べたのは水戸黄門
まずは、広く知られている「水戸黄門」の伝説からおさらいしましょう。この物語の主人公は、水戸藩主の徳川光圀。彼は大変な知識人で、1665年に中国(明)から亡命してきた儒学者の朱舜水(しゅしゅんすい)を自分の藩に招きました。
そのおもてなしのお返しとして、朱舜水が光圀に振る舞ったのが、中華風の麺料理だったとされています。現代のラーメンと違い、麺のコシを出す「かん水」がなかったため、代わりにレンコンの粉を練り込んでいたそうです。スープは中国式ハムで出汁をとり、薬味にはニラやニンニクなどが使われていました。この料理を光圀は大変気に入り、のちに家臣にも振る舞ったという記録が残っています。
この話が全国的に有名になったのは1990年代。新横浜ラーメン博物館がこの料理を再現・展示したことや、国民的ドラマ『水戸黄門』の人気が後押ししました。国民的ヒーローと国民食の結びつきは非常に強力で、今でも茨城県水戸市では「水戸藩らーめん」が郷土の味として愛されています。
新事実:室町時代にもっと古いラーメンがあった!
水戸黄門の物語は、長らく「日本初ラーメン伝説」として信じられてきました。しかし、2017年にこの歴史が大きく動きます。なんと、水戸黄門の時代より約200年も遡る室町時代に、すでにラーメンの原型となる麺料理が食べられていたことがわかったのです。
その証拠が見つかったのは、京都・相国寺の僧侶が記した『蔭涼軒日録(いんりょうけんにちろく)』という日記。1488年の記録に、「経帯麺(けいたいめん)」という中国の麺料理を客人に振る舞ったと記されていました。決定的だったのは、その作り方です。中国の書物に残されたレシピには、小麦粉と塩に加え、「鹸(けん)」、つまり現代の「かん水」と同じアルカリ塩類を使うと明記されていました。かん水を使っているという点で、この経帯麺は、光圀が食べたレンコン粉の麺よりも、現代のラーメンのより直接的なご先祖様と言えるのです。
ラーメンの日はイベント満載!でも業界はピンチ?

7月11日のラーメンの日や、その他にもたくさんある麺類の記念日は、私たち消費者にとっては楽しいイベントです。しかしその一方で、ラーメン業界は今、いくつかの大きな課題に直面しています。ここでは、華やかな記念日の裏側にある、ラーメン業界の現状と、未来に向けた挑戦について見ていきましょう。
ラーメン関連の記念日はこんなにある!
実は、「ラーメンの日」以外にも、ラーメンや麺類に関する記念日はたくさんあります。これは、カレンダーをマーケティングツールとして活用する「記念日経済」とも呼べる日本独特の文化です。
-
インスタントラーメンの日(8月25日): 1958年に世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が発売された日。
-
とんこつラーメンの日(10月2日): 「とん(10)こつ(2)」の語呂合わせ。
-
辛ラーメンの日(4月10日): 辛いを意味する英語「ホット」を「フォー(4)トー(10)」と読む語呂合わせ。
-
めんの日(毎月11日): 数字の「11」が麺のように見えることから。特に11月11日は有名です。
これらの記念日は、企業や業界団体が販売促進のために制定し、メディアがそれを取り上げることで、消費が喚起されるというサイクルを生み出しています。私たちも「今日は〇〇の日だから」と、ついその商品を手に取ってしまうことがありますよね。
活況の裏で…ラーメン店が直面する3つの危機
ラーメン市場は、2024年度には約7900億円に達すると見込まれるなど、非常に大きな産業です。しかし、その裏では多くの個人経営店などが深刻な危機に瀕しています。
-
コストの高騰: 小麦や豚肉といった食材はもちろん、ガス代や電気代、人件費など、ラーメンを作るためのあらゆるコストが上がり続けています。この5年間で原材料費は約3割も上昇したというデータもあり、店の利益を圧迫しています。
-
「1000円の壁」: コストは上がっているのに、ラーメン1杯の値段を1000円以上に上げることに抵抗を感じる店主は少なくありません。「高すぎる」とお客さんが離れてしまうことを恐れているのです。この結果、利益が出ずに倒産してしまうラーメン店は過去最多となっています。
-
人手不足と後継者問題: ラーメン店の仕事は、長時間労働で体力的にも厳しいことで知られています。そのため、新しい働き手が見つかりにくく、また高齢の店主が引退する際に後を継ぐ人がおらず、名店が惜しまれつつ閉店するケースも増えています。
私の行きつけの小さなラーメン店も、昨年ついに50円の値上げに踏み切りました。店主は申し訳なさそうに「続けていくために、ごめんね」と壁に貼り紙をしていました。消費者としては安い方が嬉しいですが、この美味しい一杯を守るためには、適正な価格を支払うことも大切だと感じた瞬間でした。私たち客側の意識も、お店を支える上で重要なのかもしれません。
危機が促す「革新」の動き
しかし、こうした危機は、ただ業界を暗くするだけではありません。むしろ、生き残りをかけた様々な「革新」を生み出すきっかけにもなっています。
-
テクノロジーの導入: 人手不足を解消するため、調理を自動で行うロボット(CHEFFYなど)や、料理を運ぶ配膳ロボットを導入する動きが広がっています。
-
高付加価値商品の開発: 「1000円の壁」を乗り越えるため、健康志向や新しい価値観に応える商品が生まれています。代表的なのが、肉や魚を使わない「プラントベースラーメン」。一風堂などが開発を進め、新しい客層を開拓しています。
-
冷凍技術の進化: 外食が難しい人々のために、お店の味を家庭で再現できる高品質な冷凍ラーメンが開発されています。最新技術により、麺が伸びにくく、スープの風味も損なわれない一杯が楽しめます。
-
サステナビリティへの配慮: 食品ロスを減らすため、ハーフサイズメニューを用意したり、出汁を取った後の魚介節をペットフードとして再利用したりする取り組みも進んでいます。
このように、ラーメン業界は、直面する課題をバネにして、伝統を守りながらも新しい時代に適応しようと変化し続けているのです。
世界に羽ばたく日本のラーメン
今やRAMENは、SUSHIやTEMPURAと並ぶ世界共通語。日本の国民食は、国境を越えて、世界中の人々を虜にしています。なぜラーメンは、これほどまでに世界で人気を博しているのでしょうか。その成功の秘密は、「味の力」「文化の力」、そして驚くべき「適応力」にありました。
ポップカルチャーが火をつけた世界的人気
ラーメンが世界に広まった大きなきっかけの一つが、日本のアニメや漫画といったポップカルチャーです。作中のキャラクターが、実に美味しそうにラーメンをすするシーンを見て、「自分もあの本物を体験してみたい!」と憧れを抱いた海外のファンは少なくありません。ラーメンは、物語を通じて日本の文化の象
徴となり、世界中の人々の心に強い印象を刻み付けたのです。
また、日本のラーメン店そのものの雰囲気も、外国人観光客にとっては魅力的な体験です。カウンターだけの小さな店構え、湯気の立つオープンキッチン、食券機で注文するシステム。これらすべてが、食事以上のエンターテイメントとして楽しまれています。
成功の鍵は「うま味」と驚異の「適応力」
もちろん、人気の根幹には圧倒的な「美味しさ」があります。昆布や味噌の「グルタミン酸」と、豚骨や鰹節の「イノシン酸」。この2つのうま味成分が合わさることで生まれる「うま味の相乗効果」が、複雑で奥行きのある味わいを生み出し、人々を魅了します。
しかし、ラーメンの真の強さは、その驚くべき「適応力」にあります。ラーメンは、現地の文化や好みに合わせて、柔軟に姿を変えることができるのです。
-
味覚への適応: 各国の好みに合わせて、スープの濃さや味を調整する。
-
宗教への対応: イスラム教徒向けのハラル認証を受けた、豚やアルコールを使わないチキンラーメンを開発する。
-
食の多様性への対応: ベジタリアンやヴィーガン向けに、肉・魚介類を一切使わないプラントベースのラーメンを提供する。
-
文化の融合: ヨーロッパでは、ラーメンとワインのペアリングを提案するなど、現地の食文化と融合する。
ラーメンは、ただ日本の味を押し付けるのではなく、麺、スープ、タレ、トッピングという基本構造(プラットフォーム)は守りつつ、中身(アプリ)を現地のニーズに合わせて自由に入れ替えることができます。この「モジュール性」こそが、他の多くの料理にはない強みであり、世界中で愛される理由なのです。
よくある質問(FAQ)
ここでは、「ラーメンの日」やラーメン全般に関して、多くの人が疑問に思うことをQ&A形式でまとめました。
Q1. ラーメンの日はいつですか?
A1. 毎年7月11日です。
Q2. ラーメンの日はなぜ7月11日なのですか?
A2. 「7」をレンゲ、「11」を箸に見立てたことと、「日本で最初にラーメンを食べた」とされる徳川光圀(水戸黄門)の誕生日にちなんでいる、という2つの理由があります。
Q3. ラーメンの日のイベントはありますか?
A3. はい、日本ラーメン協会に加盟している店舗を中心に、トッピング無料や割引などのキャンペーンが実施されることがあります。お近くのお店の情報をチェックしてみてください。
Q4. 日本で最初にラーメンを食べたのは本当に水戸黄門ですか?
A4. 長らくそう信じられてきましたが、近年の研究で、それより約200年早い室町時代に「かん水」を使った麺料理が食べられていた記録が見つかっています。ただし、物語としての魅力から、今でも水戸黄門の逸話は広く親しまれています。
Q5. なぜ山形県はラーメンの消費量が多いのですか?
A5. 昔から蕎麦文化が根付いていたこと、夏でも食べられる「冷やしラーメン」が生まれたこと、家族での外食文化として定着していることなど、複数の要因が重なっているためと考えられています。
Q6. ラーメン店が「1000円の壁」で苦しんでいるというのはなぜですか?
A6. 材料費や光熱費などのコストは上昇し続けていますが、ラーメン1杯の価格を1000円以上にすると客離れが起きることを恐れ、多くの店が値上げをためらっているためです。これにより、利益が圧迫され経営が厳しくなっています。
まとめ:進化し続ける一杯を、これからも楽しもう!
この記事では、7月11日の「ラーメンの日」を切り口に、その面白い由来から、歴史の裏側、そしてラーメン業界が直面する課題と未来への挑戦まで、幅広く掘り下げてきました。
「ラーメンの日」が、夏の売上を伸ばすためのマーケティング戦略から生まれたという事実は、少し現実的に聞こえるかもしれません。しかし、その背景には、日本の国民食であるラーメンの文化を守り、発展させたいという業界全体の熱い思いがあります。
水戸黄門の伝説から、さらに古い室町時代の記録へ。伝統的な職人技から、AI調理ロボットやプラントベースラーメンという最新技術へ。ラーメンの世界は、決して立ち止まることなく、常に時代に合わせて進化し続けています。この驚くべき「適応力」と「進化する力」こそが、ラーメンがこれからも日本で、そして世界で愛され続ける理由なのでしょう。
さあ、この記事を読んでラーメンが食べたくなってきたのではありませんか?次の7月11日、あるいは今度の週末にでも、ぜひお気に入りの一杯を味わいに行ってみてください。その一杯に込められた歴史や物語に思いを馳せれば、いつもよりさらに美味しく感じられるはずです。