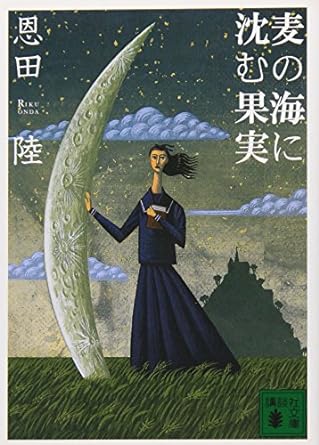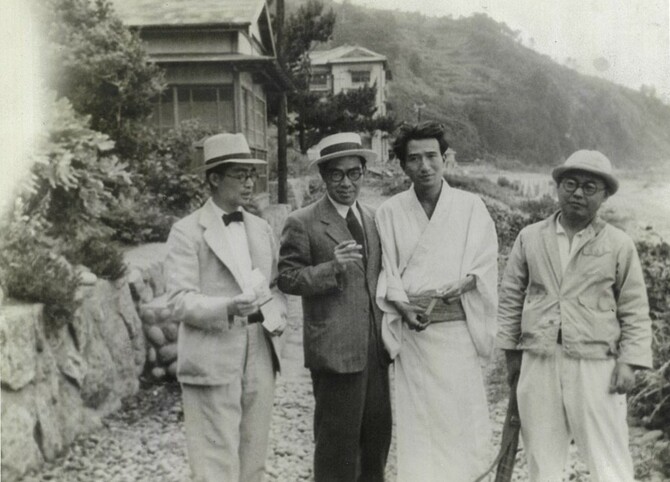梅雨の季節が近づくと、手紙や俳句を書く際にぴったりの季語が気になる方も多いでしょう。
この記事では、梅雨に関する美しい季語を一覧にしてご紹介します。季語とは、俳句や手紙で季節感を表現するための言葉で、日本の四季折々の風情を伝える大切な役割を果たします。
時候、天文、植物・動物、そして暮らしに分類された季語を詳しく解説し、梅雨の魅力を再発見していただける内容となっています。
梅雨の季節ならではの表現を楽しんでください。
梅雨の季語一覧

梅雨の季語一覧:時候
- 入梅(にゅうばい):梅雨が始まる日を指す季語です。古くは、芒種(ぼうしゅ、6月6日頃)の後の最初の壬(みずのえ)の日が「入梅」とされていましたが、現代では具体的な日にちは決まっていません。これから本格的に梅雨が始まる時期に使います。
- 梅雨に入る(つゆにいる):梅雨が始まることを表す季語です。梅雨入りとも言い、梅雨が本格的に始まる時期を指します。
- 梅雨の気配(つゆのけはい):梅雨が近づいていることを感じさせる季語です。湿度が上がり、空気が重く感じられるようになる時期に使います。
- 走り梅雨(はしりづゆ):本格的な梅雨入り前に降る雨を指す季語です。梅雨の走りとも言い、梅雨の前兆として使われます。
- 夏至(げし):一年で最も昼が長い時期を指す季語です。6月21日か22日頃で、梅雨の時期にあたります。「夏に至る」という意味があり、これから本格的な夏が訪れる兆しを表します。
- 梅雨(つゆ):6月頃に降り続く長い雨の時期を指す季語です。中国で生まれた言葉で、紅梅の実が熟す頃に降る雨を意味します。日本では「つゆ」と読まれるようになり、露(つゆ)や潰ゆ(ついゆ)に関連すると言われています。
- 黴雨(ばいう):梅雨の別称で、湿気が多く黴(かび)が生えやすいことからこう呼ばれます。雨が続く梅雨の特徴を捉えた季語です。
- 梅雨時(つゆどき):梅雨の時期全体を指す季語です。曇りや雨が続く季節で、湿度が高く蒸し暑い日々が続きます。
- 梅雨冷(つゆびえ):梅雨の時期に一時的に訪れる寒さを表す季語です。梅雨の時期は気温差があり、雨の日は寒く感じることがあります。体調を崩しやすい時期でもあります。
- 梅雨寒(つゆさむ):梅雨の時期に気温が下がり、寒さを感じることを表す季語です。梅雨寒が続くと、冷害を引き起こすこともあります。
- 梅雨明け(つゆあけ):梅雨が終わり、夏が本格的に始まる時期を表す季語です。地域によって梅雨明けの時期は異なりますが、梅雨入りから約30日後とされることもあります。
梅雨の季語一覧:天文
- 五月晴れ(さつきばれ):梅雨の時期に見られる晴れ間を指す季語です。旧暦の五月は現在の6月を指すため、梅雨の時期の晴れ間に使われます。
- 五月雨(さみだれ):6月に降り続く長雨のことを指す季語です。梅雨と同じ意味で使われますが、五月雨は特に雨そのものを強調します。
- 五月雨雲(さみだれぐも):梅雨の時期に見られる厚い雲を指す季語です。空全体が灰色の雲に覆われる様子を表します。
- 薬降る(くすりふる):旧暦5月5日の午の刻に降る雨を指す季語です。この日の雨は薬効があると伝えられており、神水とも呼ばれます。
- 青梅雨(あおつゆ):梅雨の時期にもかかわらず、雨が少なく晴れの日が続くことを指す季語です。農作物に影響を与えることもあります。
- 梅雨曇(つゆぐもり):梅雨時の曇り空を表す季語です。空全体が厚い雲に覆われ、今にも雨が降りそうな状態を指します。
- 梅雨雲(つゆぐも):梅雨の時期に空を覆う厚い雲を指す季語です。空全体が灰色の雲に覆われる様子を表現しています。
- 梅雨霖(ばいりん):梅雨の長雨を指す季語です。雨がしとしとと長く降り続く様子を表します。
- 梅雨の雷(つゆのらい):梅雨の時期に鳴る雷を指す季語です。梅雨の終わりに多く見られる現象です。
- 梅雨晴(つゆばれ):梅雨の時期に一時的に訪れる晴れ間を表す季語です。雨が続く中での晴れ間を喜ぶ気持ちが込められています。
- 梅雨夕焼(つゆゆうやけ):梅雨の時期に見られる夕焼けを指す季語です。雲間から見える夕焼けが、特に美しいことがあります。
- 黒南風(くろはえ):梅雨の時期に吹く湿った南風を指す季語です。憂鬱な気持ちを反映した言葉で、梅雨の空模様を表します。
- 五月闇(さつきやみ):梅雨の時期の夜の暗さを表す季語です。雨雲に覆われた夜空が特に暗く感じられる様子を指します。
- 梅雨の月(つゆのつき:梅雨の夜に見える月を指す季語です。雲間にぼんやりと見える月や、雨が止んで見える月など、様々な表情を楽しめます。
- 梅雨の星(つゆのほし):梅雨の夜空に見える星を指す季語です。雨雲に覆われがちな夜空に星が見えると、心が明るくなります。
- 送り梅雨(おくりづゆ):梅雨の終わりに降る強い雨を指す季語です。梅雨を見送るような雨という意味があります。
梅雨の季語一覧:植物・動物

- 雨蛙(あまがえる):梅雨の時期によく見かける小さな蛙を指す季語です。雨が近づくと「雨鳴き」と呼ばれる鳴き方をすることで知られています。
- 青蛙(あおがえる):梅雨の時期に見られる青い色の蛙を指す季語です。雨の日に特によく見かけます。
- 五月雨蛙(さみだれがえる):梅雨の時期に活動する蛙を指す季語です。梅雨の長雨と共に蛙の鳴き声が響く様子を表現します。
- 蝸牛(かたつむり・でんでんむし):梅雨の時期に活発に活動するかたつむりを指す季語です。湿気を好むため、雨の日によく見かけます。
- 雨蛍(あまほたる):梅雨の時期に見られる蛍を指す季語です。湿気の多い環境を好む蛍が飛び交う様子を表現します。
- 梅雨の鳥(つゆのとり):梅雨の時期に見られる鳥を指す季語です。雨の日でも元気に活動する鳥たちの様子を表現します。
- 梅雨の蝶(つゆのちょう):梅雨の時期に飛び回る蝶を指す季語です。雨の日の間隙を縫って活動する蝶の姿を描きます。
- 紫陽花(あじさい):梅雨の時期に咲く花で、水色や赤、紫など様々な色があります。多くの俳人が詠んだ花でもあります。
- 手毬花(てまりばな):紫陽花の別称です。花が手毬のように丸く咲くことからこの名前がついています。
- 蓮の花(はすのはな):梅雨の時期に見頃を迎える花で、湿地や池に咲きます。美しい花が梅雨の季節を彩ります。菖蒲(しょうぶ):梅雨の時期に咲く花で、長く伸びた茎に紫や白の美しい花を咲かせます。湿地を好むため、梅雨の季語とされています。
- 菖蒲酢(しょうぶす):菖蒲の花が咲く頃に梅雨の湿気を払うために酢を使う風習を表す季語です。
- 筍梅雨(たけのこづゆ):筍が生える頃に降る梅雨を指す季語です。湿気を好む筍が盛んに生える時期を表現しています。
- 梅雨茸(つゆたけ):梅雨の時期に生える茸(きのこ)を指す季語です。湿気の多い環境でよく見かける茸を表現しています。
- 梅雨菌(つゆきのこ):梅雨の時期に見られる菌類を指す季語です。湿気が多い環境でよく発生することから梅雨の季語として使われます。
- 濁り鮒(にごりぶな):梅雨の時期に産卵する鮒を指す季語です。雨で川の水が濁っている様子を表しています。
- 青梅(あおうめ):梅雨の時期に収穫される未熟な梅の実を指す季語です。梅酒や梅干しに利用されることが多いです。
- 苔(こけ):梅雨の湿気で苔が生き生きとする様子を指す季語です。梅雨の時期に苔の緑が鮮やかに見えます。
- 菜種梅雨(なたねづゆ):菜の花が咲く頃に降る長雨を指す季語です。春の終わりから初夏にかけての雨で、梅雨の前兆として使われます。
梅雨の季語一覧:暮らし
- 梅雨支度(つゆじたく):梅雨に備えての準備を指す季語です。雨具の用意や、家の中の湿気対策を行うことを表現します。
- 田植え(たうえ):5~6月に行われる田植えを指す季語です。この時期が梅雨と重なるため、梅雨の季語とされています。
- 雨休み(あめやすみ):雨で農作業を休みにすることを指す季語です。雨の日に休みを取ってお祝いをする習慣があったことを表しています。
- 夏合羽(なつがっぱ):夏の雨の日に着用する薄い合羽を指す季語です。昔は裕福な人々が使っていた雨具です。
- 五月羽織(さつきばおり):梅雨の時期に羽織る軽い衣服を指す季語です。湿気が多い時期に着る衣服を表現しています。
- 蒼朮を焼く(そうじゅつをやく):梅雨の時期に部屋の湿気を払うために薬用植物を焼くことを表す季語です。蒼朮(そうじゅつ)という植物を焚いて湿気を防ぎます。
- 蒼朮を焚く(そうじゅつをたく):蒼朮を焼くの別表現です。梅雨の時期に部屋の湿気を払うために薬用植物を焚くことを指します。
- 神水(しんすい):旧暦5月5日の午の刻に降った雨水が竹の節に溜まったものを指す季語です。薬効があると伝えられています。
- 水見舞(みずみまい):洪水や浸水などの水害に遭った人を見舞うことを指す季語です。被害があるなしに関わらず、安否を問い合わせることも含まれます。
- 川止め(かわどめ):川が氾濫して危険なため、川を渡ることが禁じられることを指す季語です。梅雨時に最も多く見られます。
- 川づかえ(かわづかえ):川が増水して渡れなくなることを指す季語です。梅雨時の川の増水を表現しています。
- 恵みの雨(めぐみのあめ):農作物にとって必要な雨を指す季語です。梅雨の時期の雨が作物に恵みをもたらすことを表します。
- 恵雨(けいう):恵みの雨を指す季語です。農作物にとって重要な雨で、梅雨の時期に多く使われます。
- 雨宿り(あまやどり):梅雨の雨を避けて一時的に屋内や軒下で雨をしのぐことを指す季語です。雨が止むのを待つ様子を表現します。
- 五月川(さつきがわ):梅雨の雨で水量が増した川を指す季語です。川の流れが速くなり、水かさが増す様子を表します。
- 五月雨傘(さみだれがさ):梅雨の時期に使う傘を指す季語です。長雨の時期に欠かせないアイテムです。
- 濁り井(にごりい):梅雨時に井戸の水が濁る様子を表す季語です。長雨によって地中の水が増えることを示しています。
- 皐月波(さつきなみ):梅雨の時期に海に立つ大波を指す季語です。荒南風(あらはえ)によって海が荒れることを表現しています。
- 梅雨海(つゆうみ):梅雨の時期の海を指す季語です。雨に煙る海や、静かな海の様子を表現します。
- 梅雨籠(つゆごもり):梅雨の時期に家に閉じこもることを指す季語です。長雨で外出できない様子を表しています。
- 梅雨の旅(つゆのたび):梅雨の時期に行う旅行を指す季語です。雨の中を旅する風情や、雨に濡れた景色を楽しむ様子を表現します。
まとめ:梅雨の季語一覧
上記をまとめます。
- 季語「入梅」「梅雨の気配」「走り梅雨」などの時候の説明
- 季語「五月晴れ」「梅雨雲」「梅雨夕焼」などの天文の説明
- 季語「雨蛙」「紫陽花」「蝸牛」などの植物・動物の説明
- 季語「梅雨支度」「田植え」「蒼朮を焼く」などの暮らしの説明