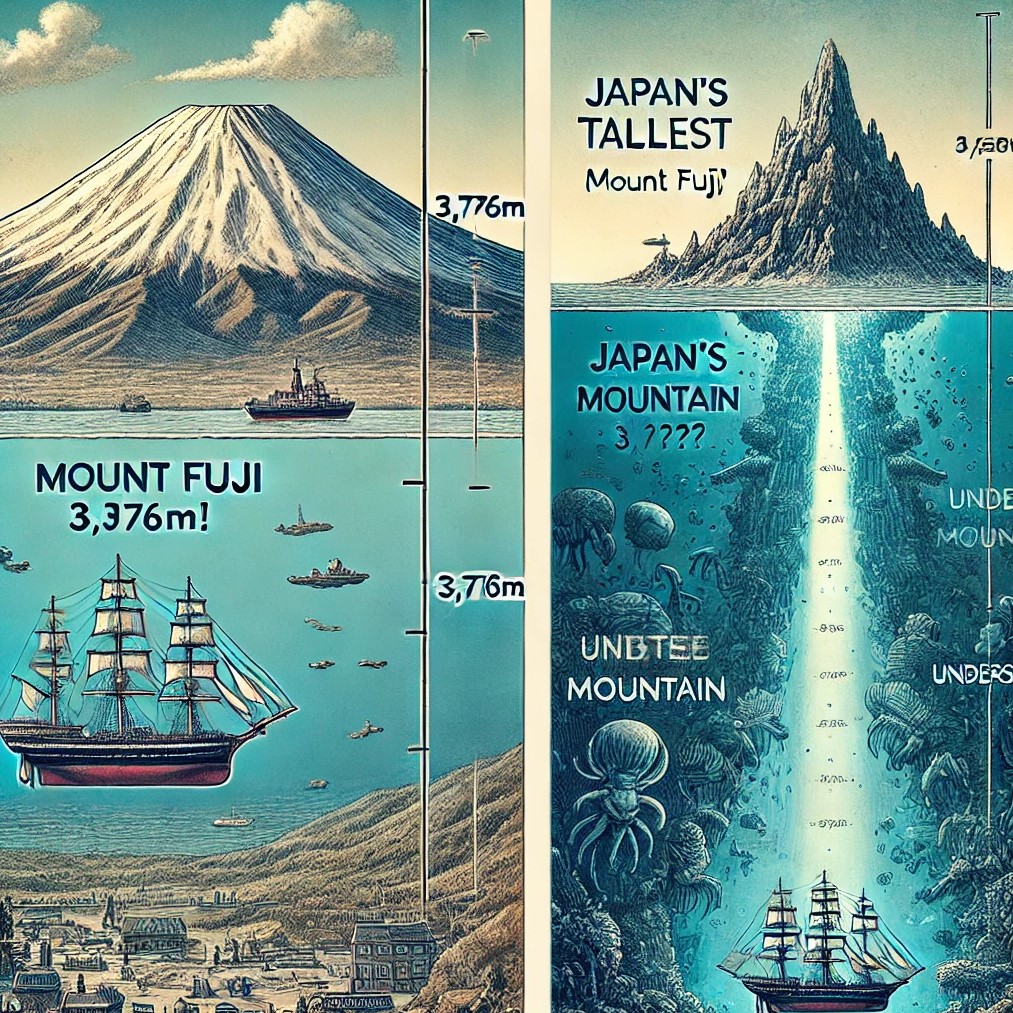「できるだけ地震が少ない県に住みたい」
日本に住む私たちにとって、これは切実な願いではないでしょうか。大きな地震のニュースを聞くたびに、自分や家族の安全を考え、より災害の少ない場所を求めてしまうのは自然なことです。しかし、安易に「地震の少ない県ランキング」を信じてしまうことには、実は大きな落とし穴が潜んでいます。
この記事では、単なる回数ランキングでは見えてこない、日本における地震リスクの真実を徹底的に解き明かします。読み終える頃には、「どこが安全か」という視点から、「どこに住んでいても、どう備えるべきか」という、あなたと家族の未来を守るための本質的な視点が身についているはずです。
- 「地震の少ない県」ランキングは、何を基準にするかで順位が大きく変わるため、絶対的な指標ではない。
- 過去に地震が少なかった県も、将来発生が予測される「南海トラフ巨大地震」では甚大な被害を受ける可能性がある。
- 地震の発生確率が低いとされてきた活断層も、熊本地震のように突然活動することがあり、「確率が低い=安全」ではない。
- 地震のリスクは揺れだけでなく、津波や、揺れを増幅させる「軟弱な地盤」など、複合的に考える必要がある。
- 本当の安全は「場所選び」だけで決まるのではなく、正しい知識に基づく「日頃の備え」が最も重要である。
「地震の少ない県」ランキングの真実とウソ
「地震の少ない県」と聞いて、あなたはどの都道府県を思い浮かべますか?メディアで時折見かけるランキングは、私たちの安全な場所選びの判断基準になりがちです。しかし、その数字の裏側を少し覗いてみると、意外な事実が見えてきます。
統計データで見る「揺れない県」はどこ?
結論から言うと、どの統計を見るかによって「地震の少ない県」は変わります。
例えば、気象庁のデータを基に「震度1以上の地震の観測回数」で見てみましょう。ある10年間のデータでは、佐賀県、奈良県、福井県、富山県などが全国で最も少ないグループに入ります。これは、多くの人が持つ「西日本や日本海側は地震が少ない」というイメージと一致するかもしれません。
一方で、「震度5弱以上の強い揺れの回数」に焦点を当てると、また違った顔ぶれになります。過去のデータを見ると、愛知県や岐阜県、香川県、岡山県などは、この破壊的な揺れを経験した回数が極めて少ない県として挙げられます。人々が「安全な県」に求めるのは、こうした大きな被害に繋がる揺れが少ないことでしょう。
このように、指標を変えるだけでランキングは変動します。単に「地震が少ない」という言葉を鵜呑みにするのは危険なのです。
なぜランキングはアテにならない?統計のワナを解明
ランキングがアテにならない最大の理由は、「統計のワナ」があるからです。
第一に、「集計期間」の問題があります。例えば、直近10年間のデータは、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震の余震活動に大きく影響されます。そのため、福島県や熊本県が突出して多くなりますが、これがその土地の長期的な危険性をすべて表しているわけではありません。
第二に、「地震の定義」が曖昧なことです。「回数」を重視するのか、命や財産に直接関わる「揺れの強さ」を重視するのかで、安全な県の答えは全く変わってきます。香川県は揺れの総回数では全国トップクラスに少ないですが、将来の巨大地震のリスクを抱えています。
つまり、私たちが目にする「安全な県ランキング」は、作り手が選んだ特定の基準で切り取られた、一面的な情報に過ぎないのです。
[独自見解] ランキングを鵜呑みにしていた私の気づき
以前の私は、こうしたランキングを見て「岡山や香川は災害が少なくて安心だ」と漠然と考えていました。特に「晴れの国おかやま」というキャッチフレーズは、安全なイメージをさらに強固にしていました。しかし、防災について深く学ぶうち、その考えがいかに危ういものだったかに気づかされました。過去のデータが少ないことは、あくまで「過去の事実」でしかなく、「未来の安全」を保証するものでは全くないのです。この気づきが、表面的な情報に惑わされず、リスクの本質を見ることの重要性を教えてくれました。
なぜ?地震の少ない県と多い県が存在する地質学的な理由
そもそも、なぜ日本国内でこれほど地震の発生頻度に差があるのでしょうか。その答えは、私たちの足元、日本列島が置かれた地球科学的な環境にあります。
日本列島の宿命!プレートと地震の基本メカニズム
日本の地震の多さは、複数の巨大な岩盤「プレート」がひしめき合う場所に位置しているという宿命によるものです。
私たちの足元にある大地は、巨大なジグソーパズルのような十数枚のプレートで覆われています。日本周辺では、「太平洋プレート」「フィリピン海プレート」「北米プレート」「ユーラシアプレート」という4つものプレートがぶつかり合っています。このプレート同士が押し合い、片方がもう一方の下に沈み込む際に、膨大なエネルギーが蓄積されます。このエネルギーが限界に達して一気に解放される現象、それが地震です。
地震には大きく分けて、プレートの境界で起こる「海溝型地震」と、内陸のプレート内部にある活断層がずれる「内陸型(活断層型)地震」の2種類があります。
海溝型地震と内陸型地震
- 海溝型地震: プレートの沈み込み帯(海溝やトラフ)で発生。M8~9クラスの超巨大地震になることがあり、広範囲に強い揺れと津波をもたらす。南海トラフ巨大地震がこのタイプ。
- 内陸型地震: 陸地の下にある活断層がずれて発生。規模は海溝型より小さいが、震源が浅いため、直上の地域に局所的で破壊的な揺れを引き起こすことがある。阪神・淡路大震災や熊本地震がこのタイプ。
プレートからの距離と活断層が地震の頻度を決める
統計的に地震の多い東北の太平洋側は、まさに太平洋プレートが沈み込む「日本海溝」の真上に位置しています。そのため、海溝型地震も内陸型地震も頻繁に発生します。
一方、中国・四国地方などが比較的地震が少ないのは、この日本海溝から地理的に離れていることが大きな理由です。これらの地域の揺れは、主にフィリピン海プレートの沈み込みや、地域内に点在する活断層の活動によって引き起こされます。
そして、岡山県のように県内の主要な活断層が少ないとされる地域は、結果的に地震の発生回数が少なくなる傾向にあります。逆に、長野県のように内陸でも糸魚川-静岡構造線のような巨大な活断層が貫いている場所では、歴史的に大きな地震が繰り返されてきました。
[コラム] 沖縄の地震が少ないのは「蛇紋岩」のおかげ?
沖縄県は、巨大地震を起こす琉球海溝の近くにありながら、M8クラスの巨大な海溝型地震の記録が少ない、少し不思議な場所です。
近年の研究で、その謎を解く鍵として「蛇紋岩(じゃもんがん)」という石の存在が注目されています。これは水分を多く含んだ、非常にもろくて滑りやすい性質を持つ石です。沖縄の沖合で沈み込むフィリピン海プレートの表面にこの蛇紋岩が大量に存在し、プレート間の潤滑油のような役割を果たしているのではないか、と考えられています。そのおかげで、巨大なエネルギーが溜まりにくく、大きな地震が起きにくいのかもしれません。これは、地震リスクが単純なプレートの配置だけでなく、その場所固有の地質によって大きく変わることを示す面白い例です。
「地震の少ない県」に潜む最大の災害リスク|南海トラフと活断層
過去の地震回数が少ないという事実は、時に私たちを油断させます。しかし、日本の未来に目を向けたとき、この「安全神話」は非常にもろく、危険なものであることがわかります。特に、西日本に住むすべての人に関わる巨大なリスクが存在します。
確率70-80%!南海トラフ巨大地震が日本の安全神話を覆す
日本が直面する最大の災害リスク、それが「南海トラフ巨大地震」です。
南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州の東沖まで続く、水深4,000m級の深い溝のこと。ここではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでおり、およそ100年から150年の間隔でM8クラスの巨大地震を繰り返し発生させてきました。政府の地震調査研究推進本部は、この南海トラフでM8~9クラスの巨大地震が今後30年以内に発生する確率を「70%~80%」と発表しています。これは、いつ起きてもおかしくない、極めて切迫した脅威です。
皮肉なことに、これまで「地震が少ない安全な県」とされてきた地域の多くが、この巨大地震の震源域にすっぽりと含まれているのです。
岡山・香川も安心できない?想定される被害とは
例えば、災害が少ないイメージの強い岡山県。しかし、南海トラフ巨大地震が発生すれば、最大で震度6弱の揺れに見舞われ、1,300人もの死者が出ると想定されています。
また、地震回数の少なさで知られる香川県では、最大震度7という破壊的な揺れが予測され、場所によっては最大5mの津波が押し寄せるとされています。過去の記録を遡れば、1707年の宝永地震(南海トラフ巨大地震)で、高松は震度6相当の揺れと津波で大きな被害を受けています。歴史は、香川県が決して安全地帯ではないことを教えているのです。
内陸の奈良県も例外ではありません。津波の心配はありませんが、強い揺れによって約1,600人の死者と、約4万4,000棟の家屋が全壊・焼失すると想定されています。過去のデータだけを見て「安全だ」と思い込むことが、いかに危険かがわかります。
熊本地震の教訓。「確率が低い」は「安全」ではない活断層の恐怖
南海トラフと並んで見過ごせないのが、内陸の「活断層」のリスクです。
2016年の熊本地震は、私たちに重要な教訓を与えました。この地震を引き起こした布田川断層帯は、地震発生直前の時点で、30年以内の発生確率が「ほぼ0%から0.9%」と、極めて低い評価だったのです。この事実は、「確率が低い」という評価が「安全」を意味しないことを、何よりも雄弁に物語っています。
この教訓を踏まえて全国を見てみると、「安全」とされてきた県にも、静かにその時を待つ「時限爆弾」のような活断層が存在します。
- 岡山県: 県内には長者ヶ原-芳井断層などがあり、活動すればM7クラスの地震が想定される。
- 香川県: 県の南側を巨大な中央構造線断層帯が走り、県内にも長尾断層帯が存在する。
- 佐賀県: 佐賀平野の北側には、M7.5程度の地震を起こす可能性がある佐賀平野北縁断層帯がある。
- 富山県: 過去100年間の大地震は少ないですが、県内には跡津川断層帯など複数の主要活断層が走っている。2024年の能登半島地震は、決して他人事ではないことを示しました。
これらの活断層は、明日活動するかもしれないし、数千年後かもしれません。しかし、ひとたび動けば、地域に壊滅的な被害をもたらす力を持っていることを、私たちは決して忘れてはならないのです。
地震に本当に強い県とは?企業と個人のための安全な場所選び

では、私たちは一体何を基準に、どこを選べば良いのでしょうか。リスクがゼロの場所は日本に存在しない以上、企業も個人も、より賢いリスクとの付き合い方が求められます。
企業のBCP対策に選ばれる県とその理由
企業にとって、地震対策はビジネスを続けるための重要な経営戦略「BCP(事業継続計画)」の柱です。その目的は、完璧に安全な場所を探すことではなく、東京や大阪などの本社機能が被災しても事業を止めないための「バックアップ拠点」を確保することにあります。
この観点から、歴史的に地震が少なく、首都圏などと同時に被災するリスクが低い地域が注目されています。
BCP拠点として注目される地域例
- 岡山県: 災害リスクの低さに加え、交通の便の良さから、大手銀行が本社機能の一部を移転したり、データセンターが建設されたりしています。
- 佐賀県: 「南海トラフ巨大地震で津波の想定がない九州唯一の県」という点を強みに、企業の誘致を進めています。
- 北海道: 首都圏からの地理的な距離と、安定したエネルギー供給を背景に、IT企業の巨大データセンターなどが立地しています。2018年の北海道胆振東部地震による大規模停電の際も、非常用電源で稼働し続けた実績は、その強靭性を証明しました。
これらの企業は、単純な地震回数だけでなく、複合的なリスクと事業継続の可能性を天秤にかけ、戦略的に場所を選んでいるのです。
移住で失敗しないために。個人ができるリスクチェック術
個人がより安全な場所へ移住を考える際にも、企業と同じように多角的な視点が不可欠です。ランキングに頼るのではなく、自分自身でリスクを調べる行動が未来を守ります。
具体的には、以下の3つのステップでチェックすることが重要です。
-
ハザードマップを必ず確認する:
まず、住みたい自治体が公表している「ハザードマップ」を必ず確認しましょう。これを見れば、地震による揺れの強さだけでなく、津波、洪水、土砂災害、液状化といった、その土地が抱える様々な災害リスクが一目でわかります。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで簡単に調べることができます。
-
将来の予測を重視する:
過去の発生回数よりも、南海トラフ巨大地震のような「将来の確率論的な予測」を重視しましょう。例えば、津波のリスクを最も避けたいのであれば、沿岸部ではなく内陸部を選ぶ、といった判断が有効になります。自分がどのリスクを最も避けたいのかを明確にすることが大切です。
-
地域のインフラとコミュニティを知る:
見落としがちですが、災害時にライフラインがどれだけ早く復旧するか、地域の助け合い(共助)が機能するかは非常に重要です。道路が寸断されやすい山間部や、地域との交流が少ない新興住宅地などは、災害時に孤立するリスクも考えておく必要があります。
移住のメリット・デメリット
| メリット (Pros) | デメリット (Cons) |
| 特定の災害リスク(津波など)を軽減できる | 移住先に別の種類のリスク(活断層など)が存在する可能性がある |
| 首都圏などとの同時被災を避けられる | 新しい土地での生活基盤(仕事、学校など)の再構築が必要 |
| より安心できる環境で生活できる可能性がある | 地域の防災意識が低く、いざという時の助け合いが期待できない場合がある |
移住は大きな決断です。メリットとデメリットを冷静に比較し、家族全員で話し合って決めることが後悔しないための鍵となります。
究極の災害対策は「防災意識」|地震の少ない県ほど危ない理由
ここまで、場所選びのリスクについて考えてきました。しかし、最も重要なことは、実は「場所」そのものではなく、そこに住む人々の「心構え」です。そして、ここには大きな逆説が潜んでいます。
「自分だけは大丈夫」が命取りに。正常性バイアスの罠
歴史的に災害が少ないという「安全」な評判は、人々の心に油断を生ませ、かえって地域の防災力を弱めてしまうことがあります。
私たち人間には、予期せぬ事態に直面したとき、「たいしたことはない」「自分だけは大丈夫」と、危険を無意識に過小評価してしまう「正常性バイアス」という心の働きがあります。過去に大きな被害を経験していない地域ほど、このバイアスが強く働き、「避難勧告が出ても逃げない」といった危険な行動に繋がりやすいのです。
実際に、南海トラフ巨大地震という大きなリスクを抱える香川県では、災害時の安否確認方法を決めている県民の割合が全国でワースト2位というデータがあります。また、岡山県でも、災害に対して「特に対策をしていない」と答える住民が少なくありません。この「油断」こそが、いざという時に被害を拡大させる最大の要因になりうるのです。
地震保険加入率にも表れる地域の防災意識の差
この防災意識の差は、「地震保険の加入率」という客観的なデータにもはっきりと表れています。
大地震のリスクが高いと認識されている宮城県の加入率が全国トップクラスに高いのに対し、「安全」と思われがちな長崎県や沖縄県は全国で最も低い水準にあります。もちろん、保険がすべてではありません。しかし、この数字は、リスクを自分事として捉え、具体的な備えをしている人の割合を反映していると言えるでしょう。
今日からできる!家族と自分の命を守るアクションリスト
本当の安全は、日々の小さな備えの積み重ねから生まれます。以下のリストを参考に、今日からできることを始めてみましょう。
- ハザードマップの確認: 自宅、職場、学校の周りのリスクを確認する。
- 家具の固定: 寝室や子供部屋など、命を守るべき場所から優先的に行う。
- 備蓄品の準備: 最低3日分、できれば1週間分の水と食料、簡易トイレを準備する。
- 家族との連絡方法の確認: 災害用伝言ダイヤル(171)の使い方などを話し合っておく。
- 避難場所と経路の確認: 実際に家族と歩いてみて、危険な場所がないかチェックする。
FAQ(よくある質問)
Q1. 結局、日本で一番安全な県はどこですか?
A1. 残念ながら、「ここなら100%安全」という県は日本に存在しません。地震の回数が少ない県でも、将来の巨大地震や活断層のリスクを抱えています。大切なのは、ランキングに惑わされず、今住んでいる場所のリスクを正しく理解し、備えることです。
Q2. 南海トラフ巨大地震で被害が少ないと予想される県はどこですか?
A2. 震源域から遠い北海道や東北、日本海側の県は、南海トラフ巨大地震による直接的な揺れや津波の影響は比較的小さいとされています。ただし、物流の寸断など、経済的な影響は日本全国に及びます。
Q3. 活断層が少ない県はどこですか?
A3. 岡山県や香川県などは、主要な活断層が比較的少ないとされています。しかし、まだ知られていない活断層が存在する可能性や、隣県の活断層地震の影響を受ける可能性は常にあります。「活断層が少ない=安全」と断定はできません。
Q4. 移住するなら、まず何を確認すべきですか?
A4. まずは、移住候補の自治体が公開している「ハザードマップ」を必ず確認してください。地震だけでなく、津波、洪水、土砂災害など、あらゆる災害リスクを把握することが第一歩です。その上で、地域のインフラや防災への取り組みなども調べると良いでしょう。
Q5. ハザードマップはどこで見られますか?
A5. 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や、各市町村のウェブサイトで確認することができます。「(市町村名) ハザードマップ」で検索してみてください。
Q6. 地震保険には入るべきですか?
A6. 地震による損失は火災保険では補償されません。地震で家や家財が損害を受けた後の生活を再建するためには、地震保険が非常に重要になります。公的な支援だけでは不十分な場合が多いため、ご自身の状況に合わせて加入を検討することをおすすめします。
結論:幻想の「安全な場所」探しから、現実的な「備え」へ
「地震の少ない県はどこか?」という問いから始まったこの記事ですが、その探求の旅は、「日本にリスクゼロの場所はない」という現実にたどり着きました。統計ランキングは指標によって変わるあやふやなものであり、過去の静けさが未来の安全を約束してくれるわけではありません。
私たちが本当にすべきことは、幻想の「安全な場所」を探し求めることではなく、日本全国どこにいても、その土地固有のリスクを正しく理解し、それに備える「文化」を根付かせることです。それは、「どこが安全か?」と問うのではなく、「ここのリスクは何か? どう備えるか?」と自問自答することへの、考え方の大きな転換を意味します。
この記事を読んでくださったあなたが、今日から起こすべき行動は明確です。
さあ、今すぐあなたと家族の未来を守るための第一歩を踏み出しましょう。まずは、お住まいの地域の「ハザードマップ」を確認し、家族で防災について話し合うことから始めてください。
究極の安全は、地理的な条件ではなく、科学的な知識と、具体的な準備、そして私たちの強靭な心構えによってのみ、もたらされるのです。