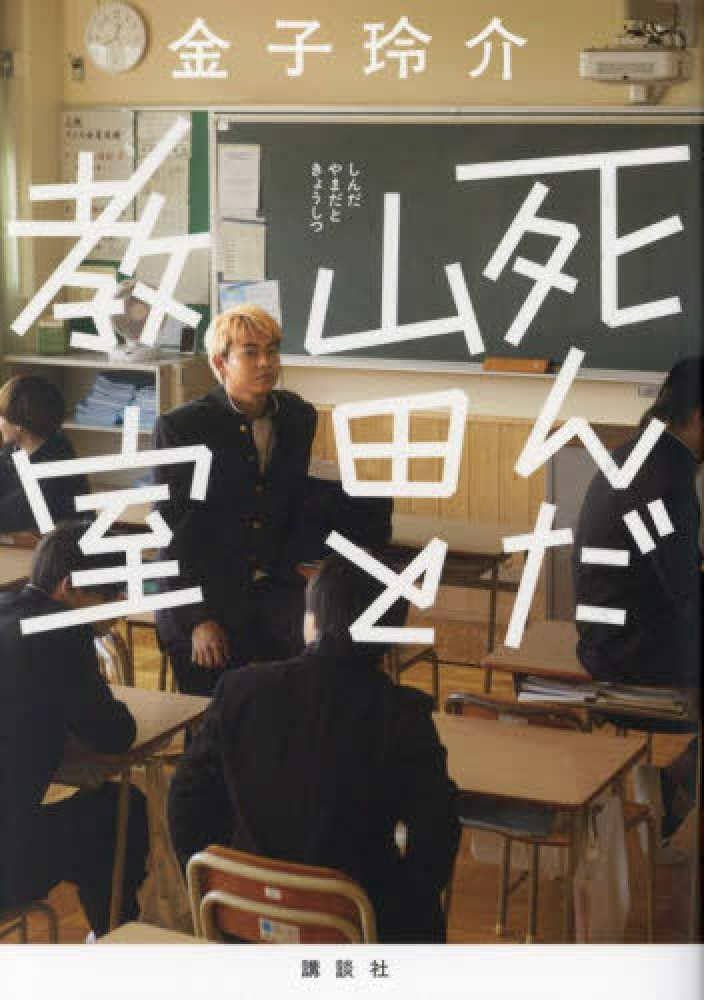「いかれころ」 のあらすじ(ネタバレあり)です。 「いかれころ」 未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。
三国美千子さんの芥川賞受賞作である 「いかれころ」 は、古き良き日本の田舎に息づく、どこか陰鬱で、それでいて強烈な人間模様を描いた作品です。主人公の奈々子の視点を通して、一族の栄枯盛衰と、それに翻弄される人々の姿が丹念に描かれています。
物語の中心となるのは、奈々子の叔母である志保子の縁談です。精神に障害を持つ志保子が、ようやく巡り合った良縁。しかし、この縁談は、杉崎家の本家と分家の複雑な人間関係、そして村に根強く残るしきたりや身分制度によって、様々な波乱を巻き起こしていきます。
村の女たちの陰口、本家の権威、そして家族それぞれの思惑が交錯する中で、志保子の縁談は進んでいくのですが、その過程で露呈する家族間の溝や、個人の尊厳が踏みにじられる描写は、読者の心に深く突き刺さります。
奈々子の幼い視点から語られることで、大人の世界の理不尽さや不条理さが、より一層鮮やかに浮き彫りになります。無垢な瞳を通して描かれる、どこか滑稽で、しかし悲しい田舎の日常は、読者に多くの問いを投げかけます。
この作品は、単なる田舎の物語ではありません。普遍的な家族のあり方、人間の業、そして時の流れとともに失われていくものへの哀愁が、丁寧に織り込まれています。読み進めるほどに、登場人物たちの感情が胸に迫り、読後には深い余韻が残ることでしょう。
「いかれころ」のあらすじ(ネタバレあり)
物語は昭和五十八年、大阪の田舎にある杉崎の分家で暮らす四歳の奈々子の視点から始まります。妊娠中の母・久美子は毎週土曜日、奈々子を連れて三本松村の本家を訪れます。本家はかつて大地主だった農家で、そこには曾祖母、祖父母、叔父、そして精神を病んだ叔母の志保子が暮らしています。
奈々子の父・隆志は婿養子で、本家の祖父・末松は彼のことを馬鹿にしています。停学中の叔父・幸明や、精神を病んだ志保子の存在は、杉崎家の複雑な内情を示唆しています。そんな中、親戚を通じて志保子に縁談が持ち上がり、結婚が予定されます。
しかし、身分制度の残るこの村では、杉崎ほどの家の娘に支払われる結納金が百万円ということに、本家の人々は不満を抱きます。志保子は常に覆いをかぶせた籠を持ち歩き、奈々子にもその中身を見せようとせず、家族は彼女を恐れています。
奈々子たちが自宅に戻ると、中学教師の父・隆志が帰宅します。土曜日の半ドンにもかかわらずすぐに帰らない父に、母・久美子は不満を抱いています。母の中にも、隆志を婿養子として見下す感情があることがわかります。隆志は福井出身で、学生運動に身を投じたため、地元での就職が叶わず大阪で教師になったという過去があります。
ある日、志保子は奈々子を幼稚園に迎えに来て、本家へ連れて行きます。そこで、墓参りに行った二人は親戚のおばさんと出会います。曾祖母が後妻に入った際、先妻の子供たちを追い出したという過去があり、その恨みからおばさんは志保子に嫌味を言いますが、志保子は丁寧に頭を下げるばかりです。
やがて志保子の結納の日が訪れます。分家である奈々子の一家も本家に集まりますが、志保子が着ている安物の着物に、女たちは眉をひそめます。実は、母・久美子が最後まで自慢の振袖を貸したがらず、結局貸したものの、直前に致命的なシミが見つかり、急遽安物を購入することになったのです。
縁談を仲介した分家筋の永通と、縁談相手の氏家の父親は堂々たる貫禄を見せます。志保子の婚約者となる和良は、歳は少し行っているものの、背の高い上品な男性でした。志保子が謎の籠を持ち歩いていることにも和良は気にしない様子で、結納は無事に終わります。
しかし、物語は次第に暗雲が立ち込めます。田植えの日、身重の母・久美子がいなく、温泉旅行に行ったことで女たちが陰口をたたきます。奈々子の子守は志保子に任され、志保子は分家に来て、まだ飾ってあるひな人形を見て、奈々子が行き遅れるからと片付けてしまいます。翌日、母は人形を片付けられたことに激怒します。
奈々子は幼稚園、そして小学校へ進学しますが、杉崎の分家の娘という地位は子供の世界では通用せず、いじめに遭います。しかし、奈々子は杉崎の者として毅然としてそれに耐え、母にはいっさい伝えませんでした。
父と母の仲は冷え切っていきます。母は本当は別の男性と一緒になりたかったのですが、立派な分家の建物を建てられ、無理やり婿をとらされたのです。父はいつしかバットの素振りをやめ、エッチなビデオの収集にハマり、いつか奈々子が婿をとって住む予定の二階部分はビデオで埋め尽くされていくのでした。
十月二週目の吉日に志保子と和良の結婚式が決まりますが、夏の盛りの曾祖父の二十三回忌に和良が来た際、奈々子の母は「結婚もしていないのに夫婦づらして」と毒づきます。志保子は部屋にこもり、和良と二人きりで話をします。そして八月、奈々子が楽しみにしていた花火大会の時には、全てが終わっていました。
志保子と和良の縁談は破談となったのです。婚約指輪を返すこともできず、結納金は倍返しだと、本家では文句が噴出します。犬のマーヤも死んでしまい、奈々子の両親の仲も破局寸前です。父は福井の実家へ帰ることが増え、母は離婚をちらつかせ本家に戻りますが、祖母に「あんた、いまから働いて子供を養う気があるのか」と叱られます。父も母に「お前にあるのは、この分家の家だけだ」とけなします。
両親は不仲ながらも、なんとか結婚生活を続けます。本家の祖父が毎日のように分家の家の庭を手入れしますが、父は後片付けもしません。時は流れ、奈々子の家族には、みじめな将来しか待っていないのでした。
「いかれころ」の感想・レビュー
三国美千子さんの 「いかれころ」 を読み終えて、まず感じたのは、地方の閉鎖的なコミュニティ、特に「家」という概念に縛られた人々の生々しい息遣いです。新潮新人賞と三島由紀夫賞をW受賞したというこの作品は、その肩書きにふさわしい、濃密で示唆に富んだ読書体験を提供してくれました。
物語の軸となるのは、たった一つの縁談が始まり、そして破局を迎えるというシンプルな出来事。しかし、そのシンプルな出来事の周囲に、まるで巨大な古木に群がる寄生植物のように、様々な人間たちがうごめいています。彼らの言動の一つ一つが、村社会の暗黙のルールや、家族間の複雑な力関係を浮き彫りにしていきます。
特に印象的だったのは、やたらいばりくさっている本家の祖父です。彼の言動は、家父長制が色濃く残る田舎の姿を象徴しているかのようです。その一方で、妖怪のような曾祖母の存在は、古くから続く因習や、もはや合理性では説明できない慣習の重みを表現しているように思えました。
そして、奈々子の母親。彼女の「婿にしてやったんだ」という高慢な態度は、分家の人間であるという自負と、本家に対するある種の優越感が入り混じった複雑な感情から生まれているのでしょう。このように、登場人物たちの誰もが、ある種の「いかれ」た状態にあるのかもしれない、そんなことを思わされました。
古い人間にとっては「そうそう、田舎って、こうだったよねえ」と、既視感を覚えるような人間模様がそこにはありました。私が実際に体験したことのあるような、近所の視線や陰口、身内の中での序列争いなど、決して美化されることのない、リアルな田舎の姿が描かれているのです。
そして、この作品の巧みな点は、ところどころにはさまれる「その後」のエピソードです。まるで、時代が流れ、古めかしい巨木だった田舎の権威が、徐々に崩れ落ちていくかのようなもの悲しさを感じさせてくれます。栄華を誇った杉崎家が、奈々子の両親の不仲や父の堕落を通して、ゆるやかに衰退していく様子は、日本の地方が抱える現実の縮図のようにも見えました。
読み終わって、残ったのは、どこかなつかしく、しかし同時に哀れさを感じさせる、不思議な感情でした。それは、失われゆくものへの郷愁と、抗うことのできない時代の流れに対する諦めにも似た感覚でしょうか。
奈々子の幼い視点から描かれることで、大人たちの世界がより一層生々しく、そしてどこか滑稽に映し出されます。純粋な奈々子の目を通して、家族間の軋轢や、大人の建前、そして秘められた欲望が、余計な装飾なくストレートに伝わってきます。彼女の冷静な観察眼が、物語に深みを与えていると言えるでしょう。
特に、志保子叔母さんの存在は、この作品の核をなしています。彼女が常に持ち歩く「籠」の謎は、彼女自身の内面や、家族が抱える秘密を象徴しているかのようです。彼女の縁談が進むにつれて、杉崎家の隠された部分が少しずつ露呈していく様は、まるで封印されていたものが解き放たれるような緊張感がありました。
結納の日の描写も印象的です。母が振袖を貸したがらなかった件や、最終的にシミが見つかり安物の着物になったというエピソードは、表面的な体裁を重んじる田舎特有の価値観と、それによって傷つけられる個人の尊厳を鮮やかに描いています。形式と本音の乖離が、登場人物たちの間で生じる葛藤を浮き彫りにしているのです。
奈々子が学校でいじめに遭う場面も、見過ごせません。杉崎の分家の娘という「地位」が、子供の世界では全く通用しないという事実が、この作品のテーマである「家」というものの相対的な価値を問いかけているように感じました。いじめに耐え抜く奈々子の姿は、家族や環境に翻弄されながらも、強く生きようとする人間の姿を象徴しているかのようです。
そして、奈々子の両親の不仲。母の本当の願望と、婿養子として家に入った父の屈折した感情が、互いを傷つけ合い、家族全体に暗い影を落とします。父がエッチなビデオに耽溺していく様子は、彼の内面の空虚さや、満たされない欲望の表れなのでしょう。将来、奈々子が住むはずだった二階がビデオで埋め尽くされていくという描写は、未来への希望が失われていくような、やるせない気持ちにさせられました。
縁談の破談は、杉崎家の権威が揺らぎ始めていることを象徴する出来事です。婚約指輪の返還や結納金の倍返しといった現実的な問題が、理想や体面をはるかに凌駕する重さで迫ってきます。犬のマーヤの死も、この一族の衰退を暗示しているかのようです。
母が離婚をちらつかせ、本家に戻ろうとするものの、祖母に現実を突きつけられる場面は、田舎の女性が背負う運命の重さを感じさせます。経済的な自立が困難な中で、家という檻から逃れられない現実が、そこにはあります。父の「お前にあるのは、この分家の家だけだ」という言葉も、母を縛る足かせのようでした。
不仲ながらも結婚生活を続ける両親、そして本家の祖父が庭を手入れするが父は後片付けをしないという描写は、かつての権威と、今の堕落した現状を対比させているかのようです。そして、奈々子の家族に待っている「みじめな将来」という予感は、この物語に深いペシミズムをもたらしています。
「いかれころ」 は、特定の地域や時代に限定されることなく、普遍的な人間の感情や社会の構造を問いかける力を持った作品です。家族の絆、個人の自由、そして社会の圧力といったテーマが、読者の心に深く問いかけます。読み終えた後、登場人物たちの行く末を想像せずにはいられない、そんな強い魅力を秘めた一作でした。
まとめ
「いかれころ」 のあらすじ(ネタバレあり)を箇条書きでまとめます。
- 奈々子の視点から、古き良き日本の田舎に息づく杉崎家の人間模様が描かれる。
- 物語の中心は、精神に障害を持つ叔母・志保子の縁談。
- 杉崎本家と分家の複雑な関係、そして村のしきたりが縁談に影響を与える。
- 志保子の婚約者は和良で、結納は無事に済まされる。
- 奈々子の両親の仲は冷え込み、父はエッチなビデオ収集にハマる。
- 母は結婚前、別の男性と一緒になりたかったという過去がある。
- 志保子の縁談は最終的に破談となり、本家では結納金の倍返しを巡って揉める。
- 奈々子は学校でいじめに遭うが、家族には伝えない。
- 奈々子の両親は不仲ながらも結婚生活を続ける。
- 杉崎家には、時の流れとともにみじめな将来しか待っていないという予感で物語は終わる。