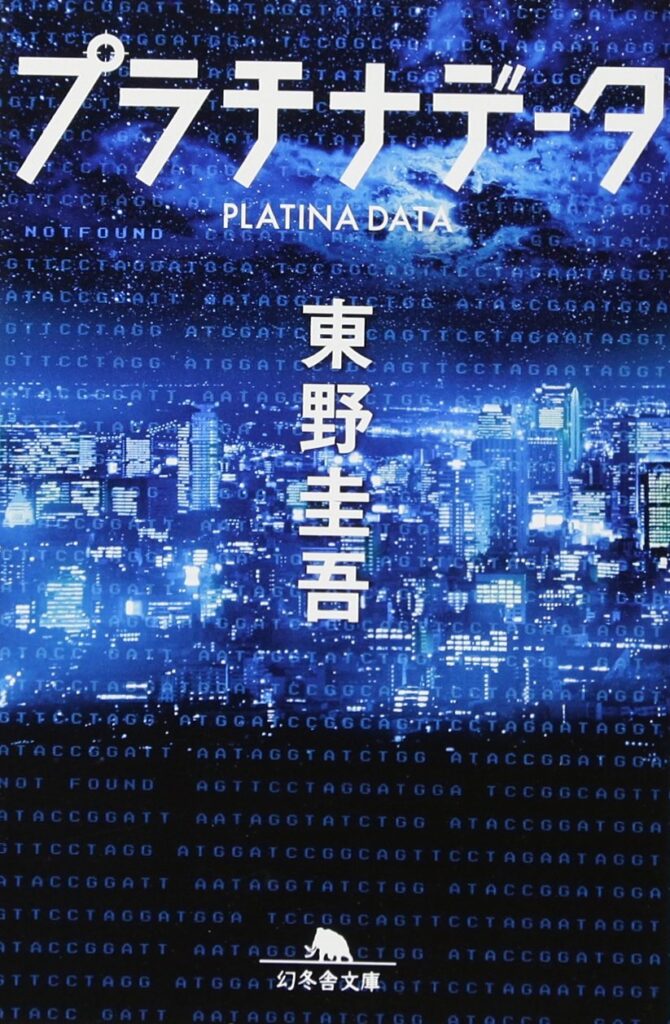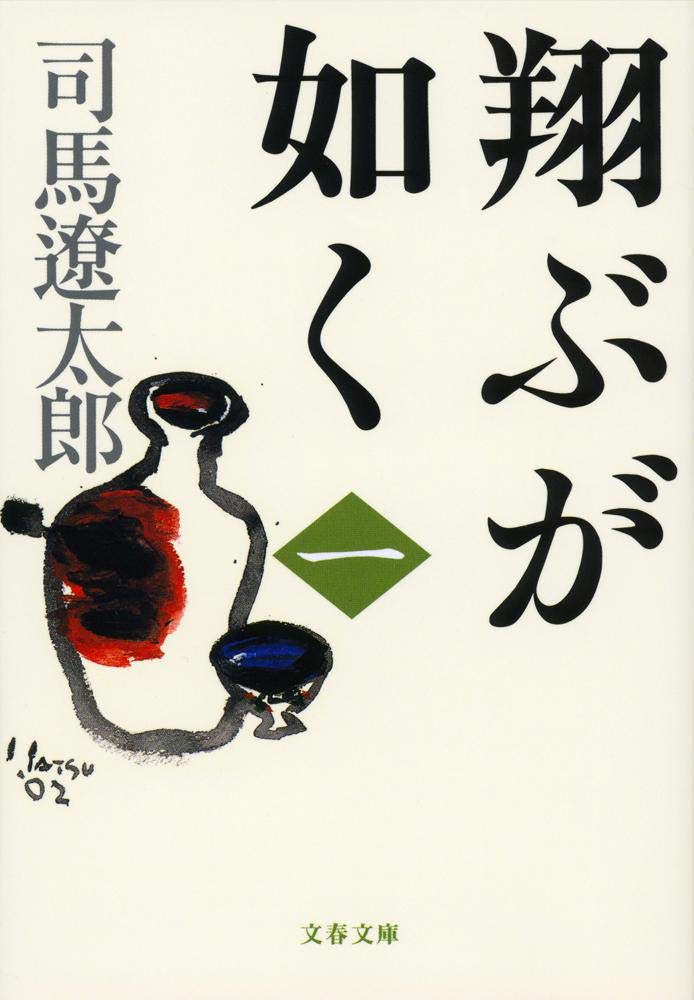
「翔ぶが如く」のあらすじ(ネタバレあり)です。「翔ぶが如く」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。司馬遼太郎先生が描く明治維新後の激動の時代、その中心にいた二人の薩摩人、西郷隆盛と大久保利通の物語、それが『翔ぶが如く』です。維新を成し遂げた英雄たちが、なぜ袂を分かち、西南戦争という悲劇へと突き進んでしまったのか。この壮大な歴史のうねりを、司馬先生ならではの視点で克明に描き出しています。
物語は明治初期、新政府内でくすぶる対立から始まります。特に、朝鮮への使節派遣を巡る「征韓論」が大きな火種となります。この論争をきっかけに、西郷隆盛は政府を去り、故郷鹿児島へと戻ります。一方、大久保利通は政府に残り、近代国家建設へと邁進。かつての盟友は、それぞれの道を歩み始めます。
鹿児島では、西郷を慕う士族たちが「私学校」を中心に勢力を拡大し、中央政府への不満を募らせていきます。そして、些細なきっかけから、ついに西南戦争が勃発。西郷は、本意ではなかったかもしれませんが、不平士族たちに担がれる形で、西南戦争の指導者となります。この戦いは、単なる内戦ではなく、古い武士の時代の終わりと、新しい時代の始まりを告げるものでした。
この物語は、西郷隆盛や大久保利通だけでなく、桐野利秋、篠原国幹、そして警察制度の父・川路利良など、魅力的な人物たちが数多く登場します。彼らの生き様を通して、明治という時代の熱気、葛藤、そして悲哀が伝わってきます。文庫版で全10巻という長編ですが、読み始めるとその世界に引き込まれ、最後まで一気に読み進めてしまうことでしょう。この記事では、物語の結末に触れながら、その詳細なあらすじと、私の個人的な思いを綴っていきます。
「翔ぶが如く」のあらすじ(ネタバレあり)
明治維新という大事業を成し遂げた日本。しかし、その後の国家建設の道を巡り、新政府内では深刻な対立が生まれていました。特に大きな亀裂を生んだのが「征韓論」です。西郷隆盛は朝鮮への使節派遣を強く主張しますが、岩倉具視や大久保利通らの反対に遭い、閣議決定は覆されます。これに憤慨した西郷は、参議をはじめとする全ての官職を辞し、鹿児島へと下野します。彼を慕う桐野利秋や篠原国幹といった薩摩出身の軍人・官僚たちも、後を追うように辞職し、鹿児島へ帰郷しました。
鹿児島に戻った西郷は、表舞台から距離を置き、狩りなどをして静かに暮らそうとします。しかし、彼の人望は絶大であり、帰郷した士族たちは西郷を中心に「私学校」を設立。これは実質的に薩摩士族の軍事・政治教育機関となり、中央政府への不満を持つ者たちの拠点となっていきます。当時の鹿児島は、中央政府の統治が完全には及んでおらず、半ば独立国のような様相を呈していました。旧藩主の父・島津久光の影響力も依然として強く、中央への税金も満足に納めていない状況でした。
そんな中、政府内で警察権力の強化を目指す大警視・川路利良(薩摩出身)は、私学校の動向を探るため、密偵を鹿児島へ送り込みます。しかし、この動きはすぐに私学校側に察知され、「西郷暗殺の刺客が送り込まれた」という誤解を生み、士族たちの怒りは頂点に達します。明治10年、抑えきれなくなった士族たちは「政府に問罪する」という名目で挙兵。西郷は、もはや自制の効かなくなった彼らに「おいの身体を預ける」と告げ、その神輿に担がれる形で西南戦争の総大将となります。
しかし、この挙兵には明確な政治的目標も、勝算のある軍事戦略もありませんでした。熊本城での籠城戦に手間取り、最大の激戦地となった田原坂で甚大な損害を被ります。その後、九州各地を転戦するも敗退を重ね、最後は故郷・鹿児島の城山に追い詰められます。明治10年9月24日、西郷隆盛は城山で自刃。多くの薩摩隼人たちも運命を共にしました。西南戦争の終結からわずか8か月後、政府の中心人物となっていた大久保利通も、東京の紀尾井坂で不平士族によって暗殺され、維新の二人の巨星は、相次いでこの世を去りました。
「翔ぶが如く」の感想・レビュー
『翔ぶが如く』、文庫版で全10巻。読み終えたときの感慨は、言葉では言い尽くせないものがありました。これは単なる歴史小説ではありません。明治という、日本が最も激しく揺れ動いた時代の空気、そこに生きた人々の息遣い、理想と現実の狭間での葛藤、そして避けられなかった悲劇を、司馬遼太郎先生は見事に描き切っています。特に、西郷隆盛と大久保利通という二人の巨星が、なぜ袂を分かち、西南戦争という形で激突しなければならなかったのか。その問いに対する深い洞察が、物語全体を貫いています。
私がこの物語で最も強く感じたのは、西郷隆盛という人物の「空虚さ」と、その底知れない「魅力」の同居です。幕末、あれほどまでにエネルギッシュに、時に権謀術数を駆使して維新回天を成し遂げた人物が、明治の世に入ると、まるで魂が抜けたようになってしまう。作中で描かれる西郷は、新しい国家の方向性に失望し、特に武士、とりわけ薩摩士族の精神性が失われていくことを深く憂えています。彼が征韓論で望んだのは、朝鮮との戦争ではなく、むしろ自らがかの地で死ぬことによって、現状への抗議を示し、あるいは武士としての「死に場所」を得ることだったのかもしれません。そう考えると、彼の行動には一貫した悲壮感が漂います。
鹿児島に帰郷してからの西郷は、政治の表舞台から距離を置き、狩りに明け暮れる日々を送ります。しかし、彼を慕う人々が彼を放ってはおかない。私学校が作られ、不平士族たちのエネルギーが渦巻く中、彼はその中心に祭り上げられていく。西南戦争が勃発する直接のきっかけは、川路利良が放った密偵に対する過剰反応でしたが、その根底には、新政府への根深い不満と、西郷への絶対的な期待がありました。そして西郷は、まるで運命を受け入れるかのように、「おいの身体を預ける」と言って、その神輿に乗るのです。西南戦争中、彼が具体的な作戦指導をほとんど行わなかったという事実は、彼の「空虚さ」を象徴しているように思えてなりません。彼はもはや、自らの意志で歴史を動かすのではなく、時代の大きな流れに身を任せていただけなのかもしれません。
しかし、そんな「空っぽ」に見える西郷が、なぜあれほどまでに人々を惹きつけたのか。これが『翔ぶが如く』のもう一つの大きなテーマであり、司馬先生自身も「後世の者が小説をもってしても把えがたい」と認めるほどの謎です。作中、中津隊の増田宋太郎のエピソードは、その魅力を間接的ながら鮮やかに伝えています。敗色濃厚な中で、増田は故郷へ帰るよう部下に命じながら、自分は西郷と共に死ぬことを選びます。「一日先生に接すれば一日の愛生ず。三日先生に接すれば三日の愛生ず。親愛日に加はり、去るべくもあらず。今は、善も悪も死生を共にせんのみ。」この言葉に、理屈を超えた西郷の人間的魅力、カリスマ性が凝縮されています。会った者を虜にしてしまう、その「何か」。文章や記録だけでは決して伝わらない、人間そのものが発するオーラのようなものがあったのでしょう。司馬先生は、その掴みどころのない魅力を、様々な人物の視点や証言を通して、立体的に描き出そうと試みています。そして読者は、その「何か」の正体を知りたいと、強く願わずにはいられなくなるのです。
一方、西郷と対照的に描かれるのが、大久保利通です。かつては「吉之助さぁ」「一蔵どん」と呼び合った無二の親友であり、維新の同志でありながら、国家観の違いから袂を分かちます。大久保は、情よりも理を重んじ、強力な官僚機構による中央集権国家の建設を目指します。そのモデルは、ビスマルク率いるプロイセン。彼は、感傷や旧来の身分制度に囚われることなく、冷徹なまでに現実的な政策を推し進めます。征韓論に反対したのも、内政の安定と富国強兵を優先すべきだという合理的な判断からでした。西郷が「情」の人であるならば、大久保は「理」の人。その対比が鮮やかです。
しかし、その大久保もまた、薩摩出身であるという事実に縛られていたのかもしれません。西南戦争は、客観的に見れば新政府と旧士族の戦いですが、村田新八が看破したように、本質的には「大久保利通と西郷隆盛の私闘」という側面が色濃くありました。同じ薩摩という土壌から生まれ育ちながら、全く異なる道を歩むことになった二人の個人的な確執が、多くの血を流す内戦へと発展してしまった。その悲劇性を、司馬先生は淡々とした筆致で描いています。そして、西郷の死からわずか8か月後、権力の頂点にあった大久保が暗殺される結末は、あまりにも劇的であり、日本の政治風土における「権力の集中」に対する警鐘のようにも読めます。司馬先生が指摘するように、日本では絶対的な権力者が現れると、それを良しとしない空気が生まれ、最終的には暗殺という形でその権力が停止させられる歴史が繰り返されてきたのかもしれません。信長、井伊直弼、そして大久保利通…。この指摘は、現代に生きる私たちにとっても、深く考えさせられるものがあります。
この物語のタイトル『翔ぶが如く』は、単に西郷や大久保個人を指すのではなく、薩摩隼人の気質そのものを表していると、司馬先生は解説しています。「進むを知って退くを知らず、唯、猪突を事として、縦横の機変に応ずるを知らず」。まさに、西南戦争における薩摩軍の戦いぶりそのものです。個々の兵は勇猛果敢で強い。しかし、戦略や兵站といった近代的な戦争の概念が欠落している。熊本城に固執し、田原坂で無謀な突撃を繰り返す。その姿は、古えの隼人のように「翔ぶがごとく」勇猛ではあるけれど、時代の変化に対応できない悲哀を漂わせています。西南戦争の敗北は、単に薩摩軍が敗れたというだけでなく、鎌倉時代から続いてきた武士という存在、その生き方そのものが終焉を迎えた瞬間だったのかもしれません。その意味で、『翔ぶが如く』は、日本の歴史における一つの時代の終わりを告げる壮大な鎮魂歌とも言えるでしょう。
そして、この物語を語る上で欠かせないのが、川路利良の存在です。彼もまた薩摩出身でありながら、郷土の情よりも、近代的な警察制度を日本に確立するという理想に生きた人物です。フランスで学んだ警察制度を日本に根付かせようとする彼の情熱は本物でした。しかし、その情熱ゆえに放った密偵が、結果的に西南戦争の引き金を引いてしまう。そして、敬愛する大久保利通の死後、急速に衰弱し、後を追うように病没する。彼の存在は、理想と現実、郷土愛と国家への忠誠といった、明治という時代が抱えた複雑な葛藤を象徴しているように思えます。
司馬先生は、この物語を執筆するにあたり、膨大な資料を読み込み、登場人物一人ひとりの評伝を織り交ぜながら、歴史の大きな流れを描き出しています。神田の古本屋街からトラックで資料が運ばれたという有名な逸話がありますが、この『翔ぶが如く』を読むと、その徹底した取材ぶりがひしひしと伝わってきます。単なる史実の羅列ではなく、そこに生きた人々の感情や思惑、時代の空気を、まるで見てきたかのように生き生きと描写する筆力は、まさに圧巻です。難しい漢字や馴染みのない人名が多く登場しますが、それでも読者を飽きさせず、最後まで引き込む力は、司馬文学ならではの魅力と言えるでしょう。
『翔ぶが如く』は、決して明るい物語ではありません。むしろ、通読すると重苦しい気持ちになるかもしれません。維新の理想が潰え、かつての仲間たちが殺し合い、多くの命が失われていく。しかし、そこには確かに、新しい日本を創ろうとした人々の凄まじいエネルギーと、時代の大きな転換点に立ち会った者たちの苦悩がありました。西郷隆盛の掴みどころのない魅力、大久保利通の冷徹なまでの合理性、そして彼らを取り巻く薩摩隼人たちの激しい生き様。読み終えた後も、その余韻は深く心に残ります。明治という時代、そして西郷と大久保という二人の巨人について、改めて考えさせてくれる、まさに「大河小説」と呼ぶにふさわしい傑作だと、私は思います。
まとめ
司馬遼太郎先生の『翔ぶが如く』は、明治維新後の激動期、西南戦争へと至る西郷隆盛と大久保利通という二人の薩摩人の対立を中心に描いた壮大な歴史物語です。なぜ維新の英雄たちが袂を分かち、悲劇的な内戦へと突き進んだのか。その背景にある時代の空気、人々の葛藤、そして薩摩という土地の特異な気風が、克明に描き出されています。
西郷隆盛の不可解なまでの魅力と「空虚さ」、大久保利通の近代国家建設への冷徹な意志、そして彼らを取り巻く人々の生き様を通して、武士の時代の終焉と新しい時代の胎動を感じ取ることができます。全10巻という長編ですが、読み応えは十分。日本の近代史、そしてそこに生きた人々のドラマに深く触れることができる、必読の作品と言えるでしょう。