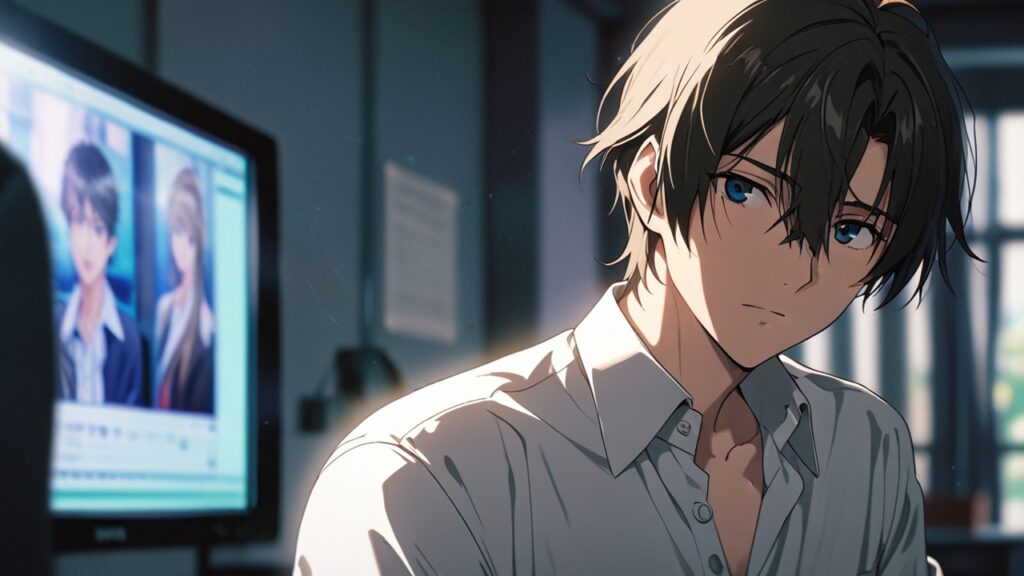また今年も、台風のニュースが聞こえてくる季節になりました。「この暴風雨の中、本当に出勤しなきゃいけないの…?」と、毎年もやもやした気持ちを抱えている人も多いのではないでしょうか。周りの同僚が出勤していると、「自分だけ休むのは『甘え』なのかな」と不安になったり、会社からの「自己判断で」という曖昧な指示にどう対応すべきか悩んだりしますよね。
結論から言えば、危険を冒してまで出勤する必要は全くありません。あなたのその「台風出勤はおかしい」という感覚は、至極まっとうです。法律は、労働者の命と安全を守ることを会社に義務付けています。この記事では、なぜ台風出勤がおかしいのか、その法的根拠から、あなたの身を守るための具体的な行動、そして「休むのは甘え」という社会的な圧力の正体まで、分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたはもう台風のたびに悩むことはなくなります。
-
危険な台風出勤は法的に拒否できること
-
会社には社員の安全を守る「安全配慮義務」があること
-
「休むのは甘え」ではなく、自分の命を守る正当な権利であること
-
台風で休む際に有給休暇を強制されたら違法になる可能性があること
-
万が一、通勤中に車が破損したり、事故に遭ったりした場合の補償について
【法的根拠】台風出勤はおかしいと感じるあなたへ!知っておくべき法律と権利
「台風出勤はおかしい」と感じる気持ちは、感情論ではありません。法律があなたの安全をしっかりとバックアップしています。いざという時に自分の身を守れるよう、まずは基本的なルールを知っておきましょう。
会社の「安全配慮義務」とは?すべての働く人を守る基本ルール
会社(使用者)には、そこで働くすべての人が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」というものが法律で定められています(労働契約法第5条)。これは正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、すべての従業員に適用される大切なルールです。
この義務は、単に「職場の機械が安全か」という話にとどまりません。台風のように明らかに危険が予測される状況で、従業員の通勤時の安全に配慮することも含まれます。具体的には、会社が責任を問われるポイントは3つあります。
-
危険を予測できたか(予見可能性):天気予報で「大型で非常に強い台風」が来ると分かっていれば、出勤が危険であることは誰でも予測できます。
-
危険を避ける手段があったか(結果回避可能性):会社には、在宅勤務への切り替えや臨時休業など、危険を避けるための選択肢があります。それなのに出勤を強いるのは、この義務を果たしていないことになります。
-
出勤と被害に因果関係があるか(因果関係):会社の指示で無理に出勤した結果、ケガをしたり、車が破損したりすれば、そこには直接的な関係が認められる可能性が非常に高いです。
この「安全配慮義務」に違反したからといって、すぐに会社が罰せられるわけではありません。しかし、もし事故が起きて裁判になれば、会社は多額の損害賠償を命じられる可能性があります。法律は、あなたの安全を最優先に考えるよう、会社に強く求めているのです。
危険な出勤は断れる!あなたの「ノー」という権利
働く人には、会社と結んだ契約どおりに働く義務(労務提供義務)があります。しかし、それは命の危険を冒してまで果たさなければならないものではありません。
自分の命や身体に、客観的に見て明らかな危険が迫っている場合、あなたにはその業務(この場合は危険な通勤)を拒否する権利があります。「公共交通機関がすべてストップしている」「自治体から避難指示が出ている」といった状況で、それでも「何とかして会社に来い」という命令は、そもそも会社の安全配る義務に違反した違法な命令である可能性が高いのです。
ただし、この権利を使う際には少し注意が必要です。もし後から「思ったほど危険な状況ではなかった」と判断された場合、無断欠勤として扱われてしまうリスクもゼロではありません。
私がまだ若手社員だった頃、大型台風が直撃した日がありました。電車はほとんど動いておらず、外は暴風雨。上司からは「来れる人だけでいい」という曖昧な連絡のみ。不安に思いながらも「行かないと評価が下がるかも…」という同調圧力に負け、びしょ濡れで出社しました。幸い無事でしたが、オフィスには必死の形相でたどり着いた数人の同僚がいるだけ。その日の業務効率は最悪でした。今思えば、あの時の「出勤」は誰のためにもならない、ただ危険なだけの行為でした。この経験から、曖昧な指示こそが一番の問題であり、自分の身は自分で守る知識が必要だと痛感しました。
台風で休んだら有給休暇を強制される?それは違法かも
「台風で休むなら、有給休暇(年次有給休暇)を使いなさい」と会社から言われた経験はありませんか?実はこれ、違法になる可能性が非常に高いです。
有給休暇は、もともと働く義務がある日に、労働者が「自分の意思で」休むために使う権利です。しかし、台風を理由に会社側が「今日は休みでいい」と休業を決定した場合、その日はそもそも働く義務自体がなくなっています。働く義務のない日に、有給休暇をあてることはできません。
もし、会社ではなくあなた自身の判断で「安全のために休みます」と伝えた場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、その日の給料は支払われないのが基本です。しかし、会社が一方的に有給休暇扱いにすることは、あなたの貴重な権利を奪う行為であり、認められません。
なぜ「台風出勤」はなくならない?企業のホンネと「自己判断」のワナ
法律では労働者の安全が守られているはずなのに、なぜ「台風出勤はおかしい」と感じる状況がなくならないのでしょうか。そこには、企業の財務的な事情と、責任を回避するための巧妙な言葉のトリックが隠されています。
「自己判断で」は責任逃れの言葉
「出勤については、各自の安全を最優先に、自己判断でお願いします」――。一見、従業員を気遣っているように聞こえるこの言葉。しかし、これが一番やっかいな指示です。
会社が「臨時休業にします!」と明確に宣言した場合、それは「会社の都合による休み」と見なされる可能性があります。その場合、会社は従業員に平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなくてはなりません(労働基準法第26条)。
一方で、「自己判断で」と指示を出すとどうなるでしょうか。
-
出勤した従業員からは、通常通り労働力を得られます。
-
休んだ従業員に対しては、「本人が自分の判断で休んだ」ことになり、「ノーワーク・ノーペイの原則」を適用して給料を支払わなくて済む場合があります。
つまり、会社にとっては、休業手当というコストをかけずに済む「自己判断」という曖昧な指示が、短期的に見ると金銭的に最も都合が良いのです。この構造が、従業員に危険な判断を迫り、「台風出勤」をなくすことを難しくしている根本的な原因です。
会社の災害対策(BCP)は万全?大企業と中小企業の格差
災害時に事業をどう継続するか、前もって計画を立てておくことを「BCP(事業継続計画)」と呼びます。災害大国である日本において、これは企業にとって非常に重要な取り組みです。
しかし、このBCPの策定状況には、企業規模によって大きな差があるのが現実です。
-
大企業:多くの大企業ではBCPが策定されており、台風などの際にはテレワークへの移行や計画休業の基準が明確に決められています。例えば、リコーやNECのような企業は、以前からテレワーク環境を整備していたため、スムーズに在宅勤務へ移行できています。
-
中小企業:リソース不足などからBCP策定が遅れている企業が多く、場当たり的な対応になりがちです。国や自治体も補助金などで支援していますが、まだまだ浸透していないのが実情です。
あなたの会社がBCPを策定しているか、そしてその中に従業員の安全を守るための具体的な行動(例えば「警戒レベル4で在宅勤務発令」など)が明記されているかどうかが、いざという時の会社の姿勢を測る一つのバロメーターになります。
-
就業規則を確認する:まずは会社の就業規則に、災害時の対応に関する項目があるかチェックしてみましょう。「非常災害時の措置」といった項目があるはずです。
-
社内ポータルや通達を探す:過去の台風の際に、会社からどのような通達があったか確認してみるのも有効です。
-
上司や総務部に質問する:「防災の観点からお伺いしたいのですが、弊社では台風などの災害時における出退勤の基準はございますか?」と、角が立たないように聞いてみましょう。
-
労働組合に相談する:労働組合があれば、会社と従業員の安全についてどのような取り決めがあるか確認できます。
「休むのは甘え」という空気の正体|台風出勤を強いる日本の職場文化

法的な問題や会社の体質だけでなく、私たちの心の中に根付いている「見えない圧力」も、危険な台風出勤を引き起こす大きな要因です。「休むのは甘え」と感じてしまう、その空気の正体を探ってみましょう。
なぜ周りの目が気になる?「同調圧力」という見えない力
「上司や先輩が行くなら、自分も行かなければ…」
「自分だけ休んだら、周りに迷惑をかけるんじゃないか…」
このように感じてしまうのは、日本社会に根強く存在する「同調圧力」の影響です。明確な命令がなくても、周りの雰囲気や暗黙の期待に合わせて行動してしまう心理のことです。
-
空気を読む文化:日本では、言葉にされない意図を汲み取り、それに沿って行動することが求められがちです。
-
和を乱したくない気持ち:集団の調和を重んじるあまり、一人だけ違う行動をとることに罪悪感や恐怖を感じてしまいます。
-
「甘え」への嫌悪感:困難に耐えることが美徳とされ、安全を優先する行為が「弱さ」や「甘え」と見なされかねない風潮も、この圧力を強めています。
会社の「自己判断で」という曖昧な指示は、この同調圧力を最大限に増幅させます。明確な「休め」という指示がなければ、「出勤する」ことがデフォルト(標準)の行動となり、休む人が「空気が読めない」「和を乱す」存在になってしまうのです。
「逸脱の常態化」という最も危険な罠
台風出勤がなぜ繰り返されるのか。そこには「逸脱の常態化」という心理的な罠があります。
-
台風が来る → 会社は「自己判断で」と指示
-
同調圧力で多くの人が出勤する
-
幸い、多くの人は何事もなく会社に着く
-
休んだ少数の人が、なんとなく罪悪感を抱く
-
このサイクルが繰り返される
このサイクルを繰り返すうちに、「台風の中、出勤する」という本来は異常(逸脱)で危険な行動が、だんだんと「いつものこと」「当たり前」に感じられるようになってしまいます。これが「逸脱の常態化」です。
そして、いつか本当に予測を超えるような「ブラックスワン(ありえないほど巨大な災害)」が襲来したとき、人々はいつも通り常態化した危険な行動(出勤)をとってしまいます。その結果、取り返しのつかない悲劇が起こるのです。それは単なる天災ではなく、危険を「当たり前」にしてしまった組織や社会が生み出した人災と言えるでしょう。
【実践ガイド】台風出勤を回避し、自分の身を守るための具体的な行動
では、実際に台風が迫ってきたとき、私たちはどう行動すればいいのでしょうか。法律や権利を知っているだけでは不十分です。ここでは、あなたの安全を確保するための具体的なアクションプランを解説します。
あなたの命を守るためのセルフチェックリスト
台風が接近してきたら、会社の指示を待つ前に、まず自分で客観的な状況を確認しましょう。判断の基準は「同僚が行くかどうか」ではありません。
-
公的情報の確認
-
気象庁のウェブサイトで、台風の強さ、進路、自分の地域への影響を確認したか?
-
自治体(市町村)のウェブサイトや防災アプリで、避難情報(高齢者等避難、避難指示)が出ていないか確認したか?
-
-
交通機関の確認
-
利用する鉄道路線やバスの運行状況(計画運休・運転見合わせ)を確認したか?
-
道路情報(通行止めなど)を確認したか?
-
-
身の回りの危険度の確認
-
自宅の周りに、浸水や土砂災害の危険があるエリア(ハザードマップで確認)はないか?
-
避難が必要になった場合に、安全に避難できるか?
-
これらの情報を総合的に見て、少しでも「危険だ」と感じたら、出勤をためらうべきではありません。
会社に「休みます」と伝えるときのポイント
危険だと判断した場合、それを会社に伝えることが次のステップです。伝え方一つで、相手の受け取り方も変わってきます。
ステップ1:記録に残る方法で、速やかに連絡する
電話だけでなく、必ずメールやビジネスチャットなど、やり取りが記録として残る形で連絡しましょう。
ステップ2:主観ではなく「客観的な事実」を伝える
「雨風が強いので、なんとなく不安で…」といった曖昧な理由ではなく、具体的な事実を伝えましょう。
【例文】
件名:【勤怠連絡】台風接近による自宅待機のお願い(〇〇部 氏名)
〇〇部長
おはようございます。〇〇部の〇〇です。
台風〇号の接近に伴い、本日の出勤についてご相談させてください。
現在、私が利用しております〇〇線が計画運休となっており、復旧の目処が立っておりません。また、居住している〇〇市には大雨洪水警報に加え、警戒レベル3の高齢者等避難が発令されております。
つきましては、誠に恐縮ですが、本日は安全確保のため自宅にて待機させていただきたく、お願い申し上げます。
業務の進捗につきましては、状況が落ち着き次第、改めてご報告いたします。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
氏名:〇〇 〇〇 所属:〇〇部
ステップ3:すべてのやり取りを記録・保存する
会社からの返信や、もし不当な圧力を受けるようなことがあれば、そのやり取りもすべて保存しておきましょう。万が一の際の証拠になります。
台風による損害(車破損・死亡事故)と労災・補償の話
考えたくないことですが、もし無理な出勤が原因で事故に遭ってしまったらどうなるのでしょうか。「台風は天災だから自己責任」と思われがちですが、そんなことはありません。ここでも法律があなたを守ってくれます。
通勤中の事故は「通勤災害(労災)」
会社への行き帰りに起こった事故は、「通勤災害」として労働者災害補償保険(労災保険)の対象となります。
これは、自宅と会社の間の「合理的な経路」で起きた事故であれば、補償が受けられる制度です。例えば、台風で電車が止まったために、普段とは違うルートで車で通勤したり、迂回したりするのも「合理的」と見なされる可能性が高いです。
もし事故でケガをすれば治療費が、万が一後遺症が残ったり、最悪のケースとして死亡に至ったりした場合には、本人や遺族に年金や一時金が支払われます。台風のような自然災害が原因であっても、それが通勤という業務に関連する行為の最中に起きたのであれば、業務との関連性が認められ、労災が適用されるのが一般的です。特に、会社からの指示で無理に出勤していた場合は、その関連性はより強く認められるでしょう。
台風で車が破損…修理代は会社に請求できる?
台風による強風で飛んできた看板が当たって車がへこんだ、道路が冠水して車が水没してしまった…。このような車破損のケースも非常に深刻です。
これが会社の指示による出勤途中の出来事であれば、会社の「安全配慮義務違反」を問い、修理代などの損害賠償を請求できる可能性があります。会社が危険を予見できたにもかかわらず、適切な指示(自宅待機など)を出さずに出勤を命じた結果、車が破損した、という因果関係を証明することがポイントになります。
すぐに法的な請求をするのはハードルが高いかもしれませんが、少なくとも「会社の指示で出勤した結果、車が壊れた」という事実は、きちんと会社に報告し、相談するべきです。
【FAQ】台風出勤に関するよくある質問
最後に、台風出勤に関して多くの人が抱く疑問に、Q&A形式でお答えします。
Q1. 台風で出勤しないのは「甘え」だと言われないか心配です。
A1. 心配になるお気持ちはよく分かります。しかし、命の安全を最優先することは決して「甘え」ではありません。それは法律で認められたあなたの正当な権利です。もし誰かにそう言われたとしても、それは個人の感想であり、法的な正当性はありません。自信を持って、客観的な事実に基づいて安全な行動をとってください。
Q2. 台風で会社を休んだら、給料はもらえないのですか?
A2. ケースによります。会社が「休業」を命じた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます。あなた自身の判断で休んだ場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、その日の給料は支払われないのが基本です。ただし、会社が有給休暇の取得を強制することはできません。
Q3. テレワークができない職種の場合は、どうすればいいですか?
A3. 医療、インフラ、小売など、現場に出なければならない仕事は確かに存在します。しかし、そうした職種であっても、会社の安全配慮義務がなくなるわけではありません。会社は、従業員の安全な通勤手段を確保したり、必要であれば事業所近くのホテルを手配したり、危険が去るまで出勤時間を調整したりするなど、最大限の配慮をする義務があります。
Q4. 台風で遅刻した場合、評価に響きますか?
A4. 台風のような公共交通機関の乱れなど、本人に責任のない理由での遅刻を、不当に評価を下げる理由にすることは許されません。もしそのような扱いを受けたら、人事部や労働組合に相談しましょう。
Q5. 会社に何も言わずに休んでも大丈夫ですか?
A5. それは絶対にやめましょう。無断欠勤と見なされ、あなたにとって不利な状況になってしまいます。危険だと判断したら、必ず本記事で紹介したような方法で、速やかに会社に連絡し、その理由を明確に伝えてください。
結論:あなたの「おかしい」は正しい。命を守る行動を。
「台風出勤はおかしい」――この記事を通して、その感覚が法律的にも、倫理的にも、そして論理的にも正しいということがお分かりいただけたと思います。
曖昧な指示で責任を従業員に押し付け、同調圧力によって危険な出勤を強いる文化は、もう終わりにすべきです。あなたの命より大切な仕事などありません。
次に台風が来たとき、あなたはもう迷う必要はありません。
-
公的な情報を確認し、冷静にリスクを判断する。
-
危険を感じたら、勇気を持って「休む」という決断をする。
-
客観的な事実に基づき、記録に残る形で会社に連絡する。
この記事が、あなたの命と権利を守るための「お守り」になれば幸いです。ぜひこのページをブックマークして、いざという時に見返せるようにしておいてください。そして、もしあなたの職場がまだ危険な慣行を続けているなら、この記事をきっかけに同僚と話し合ってみるのも一つの手です。安全な働き方が当たり前になる社会を、一緒につくっていきましょう。