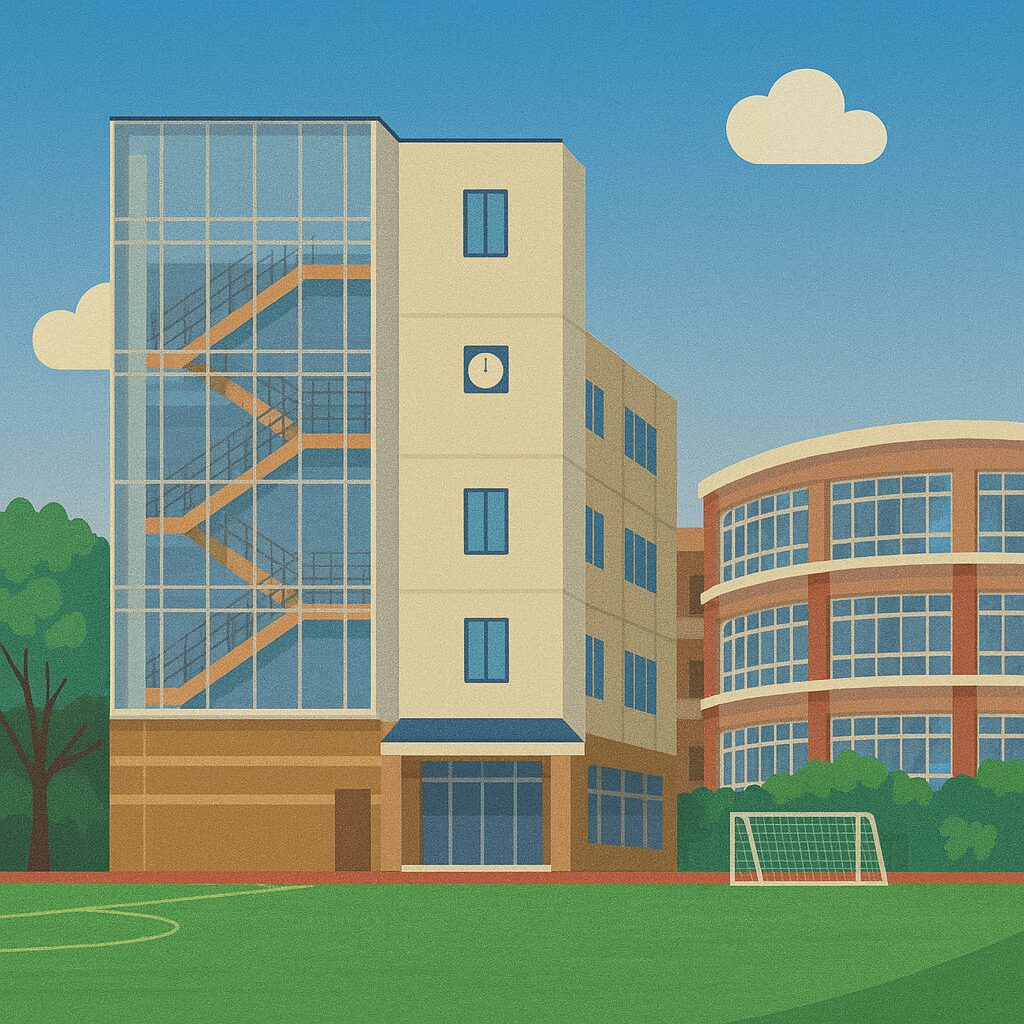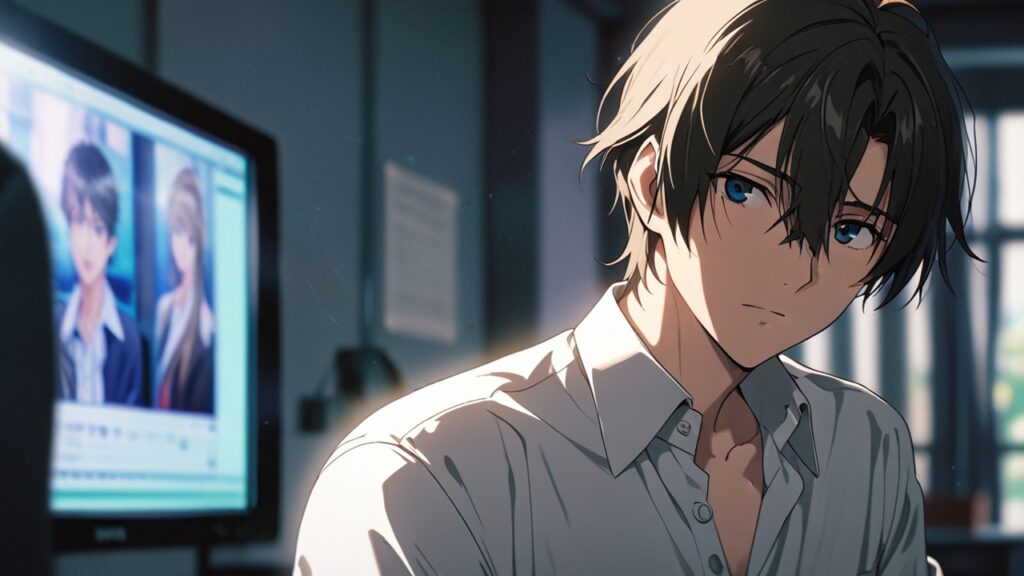
学校に行けない日々が続くと、「このまま社会に出られないかもしれない」と胸がざわつく。保護者も当事者も同じ不安を抱えるのが 「不登校からニート(若年無業者)になる確率」 だ。
本記事では最新の統計をかみ砕きながら、「実際どれくらいの割合でニート化するのか」「要因は何か」「どうすれば回避できるのか」を丸ごと解説する。数字だけでなく現場の声、支援策、成功事例まで網羅したので、読み終わるころにはモヤモヤが霧散しているはずだ。
不登校とニート、それぞれの最新データ
不登校児童生徒は過去最多
文部科学省の2024年度調査(令和5年度)によれば、小中学校で 不登校と認定された児童生徒は計34万6,482人。前年度より約4万7,000人増え、11年連続で過去最多を更新した。児童生徒1,000人当たりの割合は37.2人で、この10年で約3倍に膨らんでいる。(文部科学省)
ニート人口は59万人
総務省労働力調査等を踏まえた研究資料では、15〜34歳の若年無業者=ニートは2023年時点で59万人、若年人口の2.4% と算出されている。(リクルートワークス研究所)
不登校経験者がニートになる確率はいくらか
37.3%という衝撃的な数字
慶應義塾大学・太田聰一教授の分析によると、不登校経験者の37.3%が一度は若年無業者状態を経験 している。就職が売り手市場と言われる現在も、この割合は下がっていない。(東洋経済オンライン)
どうやって割り出すのか
-
教育機関・自治体が保有する不登校者リストと、労働力調査における非労働力人口データを突き合わせる
-
学校卒業後5〜10年の追跡調査で就労・進学・無業のステータスを確認
-
正規・非正規や家事従事者を除き、就学も職業訓練も受けていない層を「ニート」と定義
こうした手順で確率を推定している。そのため年度ごとに多少のブレはあるが、3〜4人に1人以上がニート化する という傾向はほぼ不変だ。
不登校がニートへつながりやすい5つの要因
① 学習機会の断絶
長期欠席による学力遅れが、進学・資格取得の足かせになる。結果として就職の選択肢が狭まり、無業期間が伸びやすい。
② 社会的スキルの空白期間
学校は勉強と同時に「時間を守る」「人と協働する」といった基礎スキルを磨く場でもある。不登校期間が長いと、社会参加の練習機会がごっそり抜け落ちる。
③ 心理的ハードル
登校できなかった後ろめたさ、自己肯定感の低下が就活の一歩目を阻む。「どうせ採用されない」という思い込みが無業状態を固定化しやすい。
④ 家庭内要因
経済的にギリギリの家庭ほど、通信制高校や個別指導型支援など有料サービスを利用しにくい。逆に経済的に余裕がある家庭では「何とか食べていける」安心感が行動を遅らせる。
⑤ 支援ネットワークの遅れ
地方ほどスクールカウンセラーや教育支援センターが不足し、ICT学習や居場所事業も脆弱。結果、孤立が長期化しやすい。
数字で読み解くリスクシミュレーション
下表は「不登校期間」「最終学歴」「家計状況」をかけ合わせ、ニート化リスクを3段階で示したものだ。
(★低/★★中/★★★高)
| 不登校期間 | 最終学歴 | 家計状況 | ニート化リスク |
|---|---|---|---|
| 6か月未満 | 大学卒 | 中〜高 | ★ |
| 1年以上 | 高校中退 | 低 | ★★★ |
| 3年以上 | 中学卒 | 低 | ★★★ |
| 1年未満 | 高校卒 | 中 | ★★ |
| 3年以上 | 通信制高卒 | 高 | ★★ |
ポイント
期間が長いほどリスク上昇。特に90日以上連続欠席者は55%が90日超えで、復帰が極端に難しい。(文部科学省)
最終学歴は依然根強い選考条件。履歴書に空白が多いほど門前払いが増える。
家計が苦しい場合、進学・職業訓練への投資が難しく、結果的に無業が長引く。
ニート化を防ぐ7つの実践策
1. 早期に「学籍」を確保する
フリースクール、夜間中学、通信制高校など学籍を持つだけで選択肢は激増。単位制なら在宅学習中心でも卒業資格が取れる。
2. スモールステップで社会参加
週1のオンライン講座→週1の学習会→週3の通学、と階段を細かく刻む。急にフルタイムを目指すより成功率が高い。
3. 第三者を挟む
親子だけで抱え込むと感情が絡まりやすい。スクールソーシャルワーカー、NPO、自治体ひきこもり支援センターなど外部の大人を早めに入れると調整がスムーズ。
4. 国家資格を味方に
ITパスポート、介護初任者研修など短期取得可能で求人が多い資格を先に取ると、履歴書の“空白”が資格欄で埋まり心理的負担が減る。
5. オンライン就労体験
クラウドソーシングなら在宅で実務経験を獲得でき、ポートフォリオづくりにも直結。最初は報酬より“実績づくり”を重視しよう。
6. ピアコミュニティへの参加
同じ経験を持つ仲間と悩みを共有すると、自己効力感が跳ね上がる。SNSだけでなくオフラインの自助グループも有効。
7. 家計調整と支援制度活用
就学支援金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活保護の高校就学費特例など学び直しを金銭面で後押しする制度が想像以上に多い。役所の窓口で遠慮なく相談を。
事例で学ぶ「ニート化しなかった不登校」
-
Aさん(19)
中2から完全不登校。中3でフリースクール+オンライン英会話を開始し高認合格。現在はWeb制作会社でリモートアルバイト。 -
Bさん(24)
高1で起立性調節障害を発症し休学。通信制高校→専門学校→ゲーム系スタートアップ就職。在宅勤務可の職種を選択したことで体調と仕事を両立。 -
Cさん(26)
小5から不登校。小6で地域NPOのプログラミング教室と出会う。高卒認定後、IT企業の職業訓練プログラムに参加し正社員化。
共通項は「学習機会の再接続」「第三者支援」「小さな成功体験」の3点だ。
まとめ
-
不登校児童生徒は過去最多の34万6,000人超。(文部科学省)
-
ニートは59万人、若年人口の2.4%。(リクルートワークス研究所)
-
不登校経験者の37.3%がニートを経験。3人に1人以上の高確率だ。(東洋経済オンライン)
-
リスクを押し上げる主因は学習・社会経験の断絶と心理的ハードル。
-
早期の学籍確保、段階的な社会参加、外部支援の活用で確率は大きく下げられる。
-
成功事例に共通するのは「学び直し」と「伴走者」の存在。
「不登校=将来はニート」ではない。
進路は分岐が多いほど可能性が広がる。まずは小さな一歩で社会との接点を取り戻し、数字に振り回されない“自分だけのルート”を描こう。