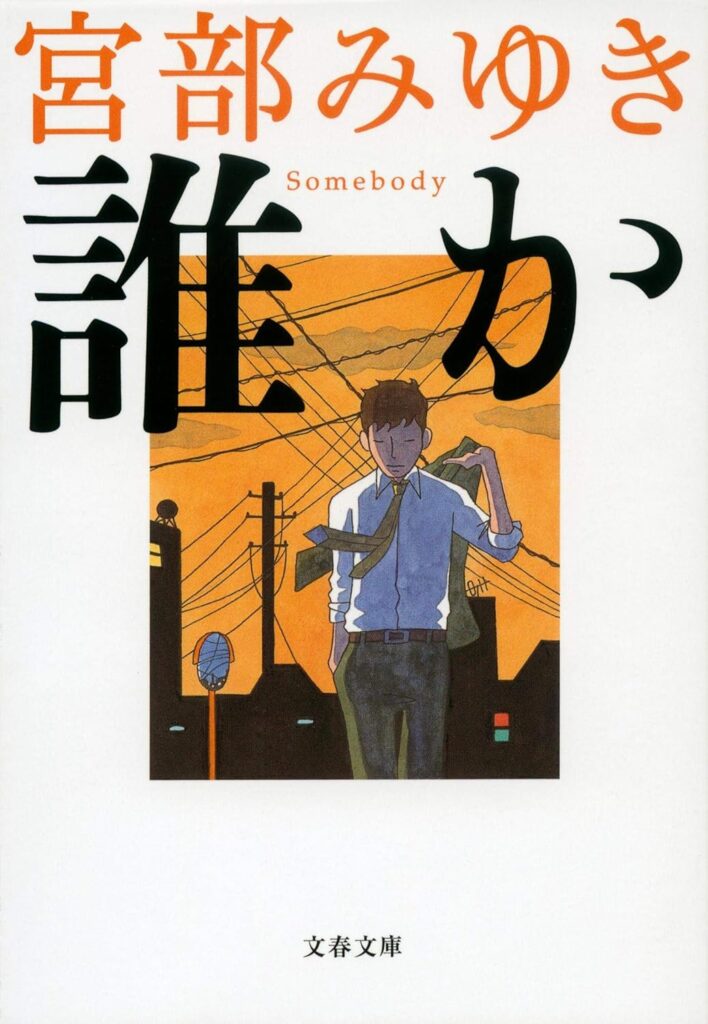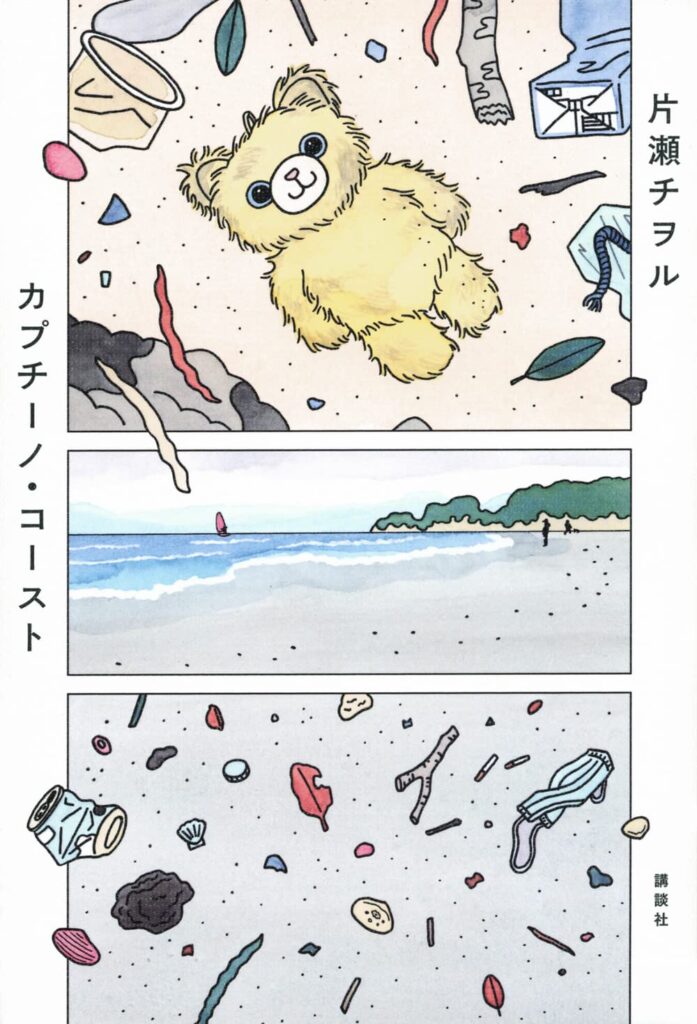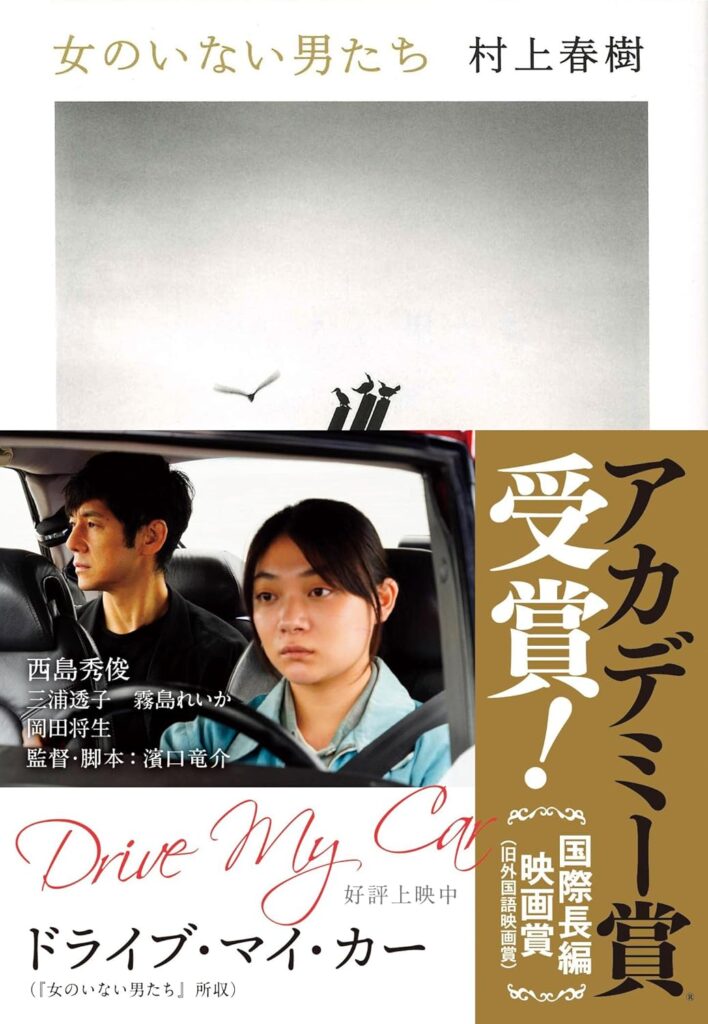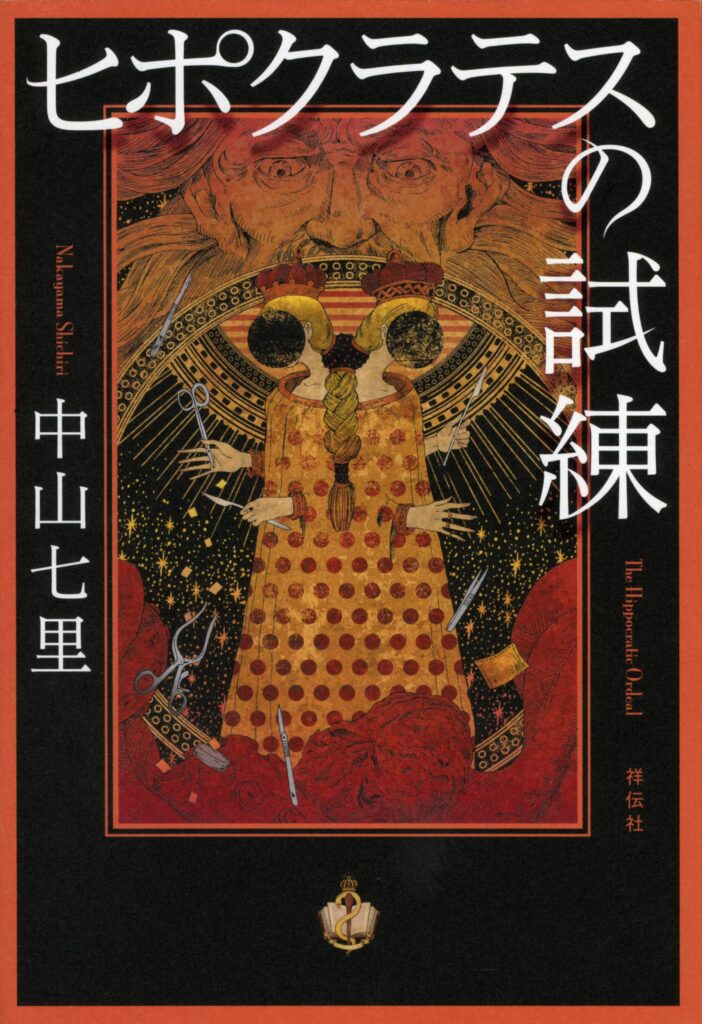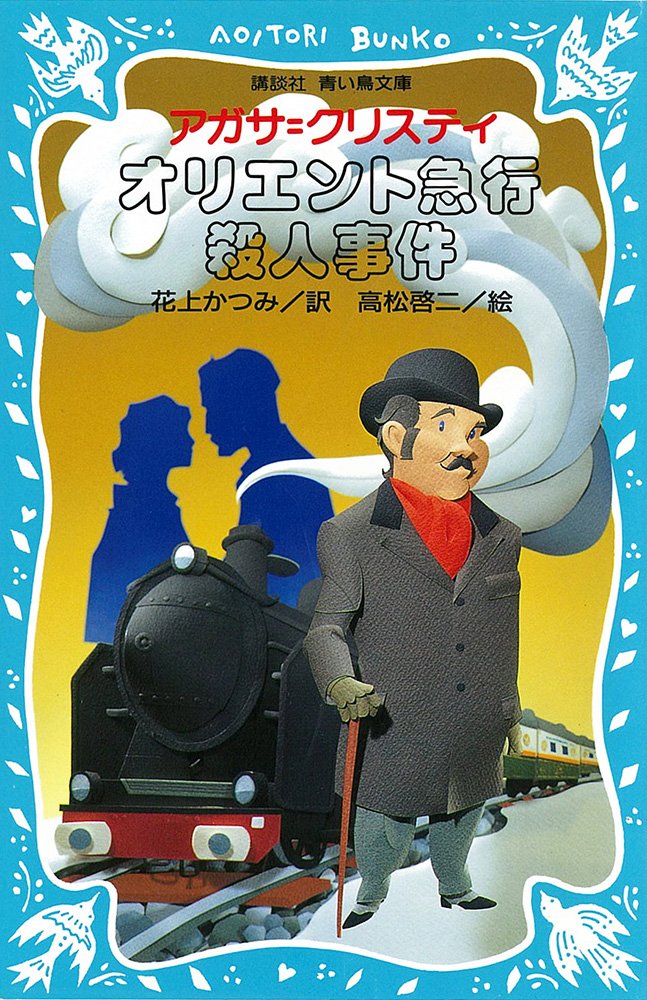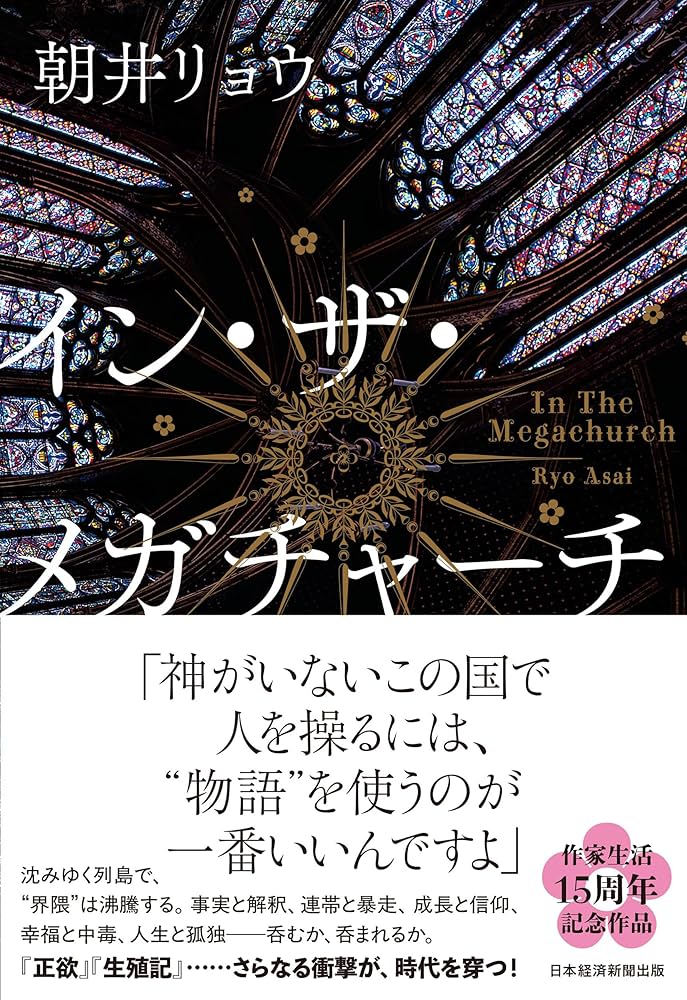
「イン・ザ・メガチャーチ」のあらすじ(ネタバレあり)です。「イン・ザ・メガチャーチ」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。
本作は、推し活と宗教的熱狂が交差する現代日本を舞台に、三人の視点が入れ替わりながら進みます。レコード会社勤務の中年男性・久保田慶彦、大学生の武藤澄香、かつて俳優のファン活動に没頭していた隅川絢子。立場も年齢も異なる三人が、それぞれ「物語」に吸い寄せられ、救われ、そして揺さぶられていく姿を描きます。
要となるのは、オーディション番組発のアイドルをめぐるファンダム運営。久保田は“熱量”を増幅する専門チームに加わり、澄香はそのアイドルに日々の不安から逃れる拠り所を見いだし、絢子は“かつての推し”を失った空洞を別の集団で埋めようとします。
作中のマーケティング担当・国見が言う「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いい」という思想が、三人を同じ装置に巻き込んでいきます。応援は共同体と目的を与えますが、同時に視野を狭くし、人間関係を切り離す作用も持ちます。
作品は新聞夕刊連載を経て単行本化された長編で、連載時から“現代の熱”を克明に封じ込めたと話題になりました。読後に残るのは、安易な断罪ではなく「自分もまた物語を求める存在なのだ」という手触りです。
「イン・ザ・メガチャーチ」のあらすじ(ネタバレあり)
久保田慶彦は、家族と離れて暮らすレコード会社の社員。社内で、アイドルグループのファンダムの熱量を高め続ける専任チームに異動します。彼は経験のない領域に踏み込む高揚と、どこか取り返しをしたいという焦りを自覚します。
新プロジェクトの中心は、オーディション番組発のアイドル・ミチヤ。久保田はSNSの動線、拡散企画、ライブ体験の設計を担い、“熱の循環”をつくる役割を果たしていきます。運営側にいながら、彼自身の心の空洞もまた、そこで埋まっていきます。
一方、大学生の武藤澄香は、教室でもオンラインでも居場所を見つけられず、内向的な気質に疲れています。そんな彼女がミチヤの発言や仕草に“自分の痛み”を重ね、ファンのコミュニティで歓迎される体験を得ると、日常の色が変わり始めます。
動画の再生協力、ハッシュタグ回し、握手会のための資金づくり——澄香は仲間と動くことで“役に立てている”実感を得ます。彼女のカレンダーはイベント中心に再編され、生活の優先順位が“推すこと”に合わせて組み替わっていきます。
隅川絢子は、かつて若手俳優のファン活動に没入していた女性。突然の報道で“推し”を失い、仲間と共有していた意味づけが崩れると、空白は彼女の毎日を侵食します。
彼女に近づくのは、別の物語を掲げる人々です。彼らは失われた出来事を“筋の通ったストーリー”に再配置し、絢子の痛みに役割と言葉を与えます。絢子はそこで再び、全力で動ける自分を取り戻していきます。
国見は語ります。「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いい」。チームは心理とデータを駆使し、疑いを生みにくい体験の連続で“視野を狭く保つ”設計を進めます。成果は出ますが、その設計は運営の内側にいる久保田自身にも作用していきます。
やがて久保田は、運営と“信じる気持ち”の境界を踏み越えます。判断は少しずつ独りよがりになり、職務倫理から外れていく。結果、彼はプロジェクトの中核から外され、観客としてイベント会場に立つことになります。
その会場には、澄香もいました。二人は同じ舞台に視線を向けながら、互いの存在に気づきません。かつて家族だった二人は、同じ物語の熱の中で、別々の孤独を深めているのです。
一方の絢子は、ある章で“すみちゃん”と呼ばれる語りの中に入っていきます。誰かのためにバイトを重ね、懸命に時間を注ぐ自分——その熱心さの構造は、以前と何も変わっていません。最後に彼女は街の雑踏で自分と似た存在を見つけ、ここから変わるのだと静かに決意します。
「イン・ザ・メガチャーチ」の感想・レビュー
物語の核は、「意味に飢えた時代に、人は何を信じるのか」です。仕事、家庭、学業といった生活の足場がぐらつく瞬間、私たちは“物語”に手を伸ばします。誰かを応援すること、誰かを正すこと、何かの一部になること——そのどれもが、自己の空洞を埋める装置として機能します。
三人の視点が丁寧に回転する構成は、立場が違っても同じメカニズムに絡め取られることを分からせてくれます。仕掛ける側の久保田、のめり込む側の澄香、別の器へ流れ込む絢子。彼らは「見たいものしか見ない」安全地帯を、それぞれの事情で手に入れてしまいます。
印象的なのは、国見の言葉です。「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いい」。ここで言う“操る”は、単なる搾取の語彙ではありません。ファンダムは、居場所・目的・貢献感という“生きるための栄養”を供給します。その代わりに、思考の幅と時間とお金を差し出すのです。
久保田の転落は、仕掛ける側が熱の回路に自ら接続されたときに起きるショートの物語です。“顧客の熱狂”を職能としてデザインしていたはずが、気づけば誰よりも熱心な信者になっている。彼の焦燥は、組織の成果と個人の救いが同じ回路で結ばれてしまう現代の危うさを体現しています。
澄香の章は、居場所を得ることの甘美さを徹底して描きます。彼女は“役に立つ自分”として承認を受け、行動→反応→さらなる行動というループの中で自己効力感を回復します。広い視野は彼女を疲れさせましたが、狭い視界は彼女を救います——少なくとも、今は。
絢子の線は、喪失の意味づけがいかに別の物語へと移植されるかを見せます。失ったものの“なぜ”は、理性ではなく共同作業の中で、より強い言葉に編み直される。慰めと確信は同時にやって来ます。その快さが、彼女をもう一段奥の部屋へと進ませるのです。
この三つの線が交わる地点に、父娘の“すれ違い”があります。会場で同じ熱を共有しながら、互いを認識できない結末は、本作の主張を凝縮しています。物語は繋がりをもたらす——しかし、それはしばしば、他の繋がりへの盲目と背中合わせです。
“すみちゃん”という呼称の仕掛けは巧みです。澄香と隅川、二人の“すみ”が重なり合うことで、推し活と別種の共同体が地続きであることが可視化されます。どちらも「すべてを注げる場所」を与え、「自分を使い切っている」という実感を与える。名称が一つに重なるとき、構造の同一性が浮かび上がるのです。
さらに言えば、本作は読者の身体にも同じ構造を発動させます。ページを繰る手が止まらなくなるあの感じ——私たちもまた、作中の登場人物と同じように、強い物語に自発的に接続してしまう。読み終えたあと、少しばかりの“放心”が残るのは、その接続を自覚したからでしょう。
連載という形式で鍛えられた密度も効いています。日々更新される“現実”の言語を的確にすくい取り、SNSやオーディション番組の空気感、ファンダムの作法を、過不足なく編み込みます。結果として、物語は“いま”の質感を失いません。
倫理の線引きに関する描写も冴えています。運営側の意思決定は、成果と正しさの間で揺れ続ける。指標が伸びるほど、疑いは後景に退く。久保田の逸脱は、個人の弱さだけでは説明できません。設計図そのものに、熱の過負荷を招く仕組みが最初から組み込まれていたのです。
本作が厳しいのは、簡単な出口を認めない点です。父娘は近くにいながら遠いまま、絢子は“別の光”の下で燃え尽き、澄香は限定された幸福の中に立っています。どの選択も、たしかに生を楽にする。しかし、その楽さは、別の代償を徴収するのです。
それでも、本作は読者に「やめろ」とは言いません。むしろ「よく見ろ」と促します。自分を動かす物語がどこから来て、どこへ自分を連れていくのか。どの瞬間に視野を絞り、どの瞬間に少しだけ広げるのか。その“調整”を取り戻すことが、いま必要なのだと感じました。
最後に、帯にも使われる国見の言葉をもう一度。これは脅しではなく、観察です。物語は人を動かします。ならば私たちは、その力学を自覚しながら使うしかありません。使う側も、使われる側も、同じ人間です。
「イン・ザ・メガチャーチ」は、推し活という狭いテーマに見えて、実は“どの物語に人生を預けるか”という普遍の選択を描いた作品でした。誰もが何かに所属し、何かの名の下に判断をくだす時代に、その選択の重みを静かに返してくる——そんな一冊です。
まとめ
-
レコード会社の久保田が、アイドルの“熱量”を高める専門チームに参加する。
-
大学生の澄香は、ミチヤの発言や振る舞いに救いを見いだし、ファン活動に没入する。
-
かつて俳優を推していた絢子は、喪失の空洞を別の集団で埋めようとする。
-
国見の“物語”論が運営の設計思想となり、視野を狭く保つ体験が連鎖する。
-
久保田は“運営”と“信者”の境界を越え、職務から外れて観客席に立つ。
-
澄香の生活はイベント中心に再編され、承認と役割が行動を加速させる。
-
絢子は別の物語へ献身を移し替え、全力で動ける自分を回復する。
-
会場で父娘は同じ舞台を見つめながら互いに気づかず、別々の孤独を深める。
-
“すみちゃん”の仕掛けが、推し活と別種の共同体の同一構造を照らす。
-
安易な解決は提示されず、読者に“自分を動かす物語”との付き合い方を問う。