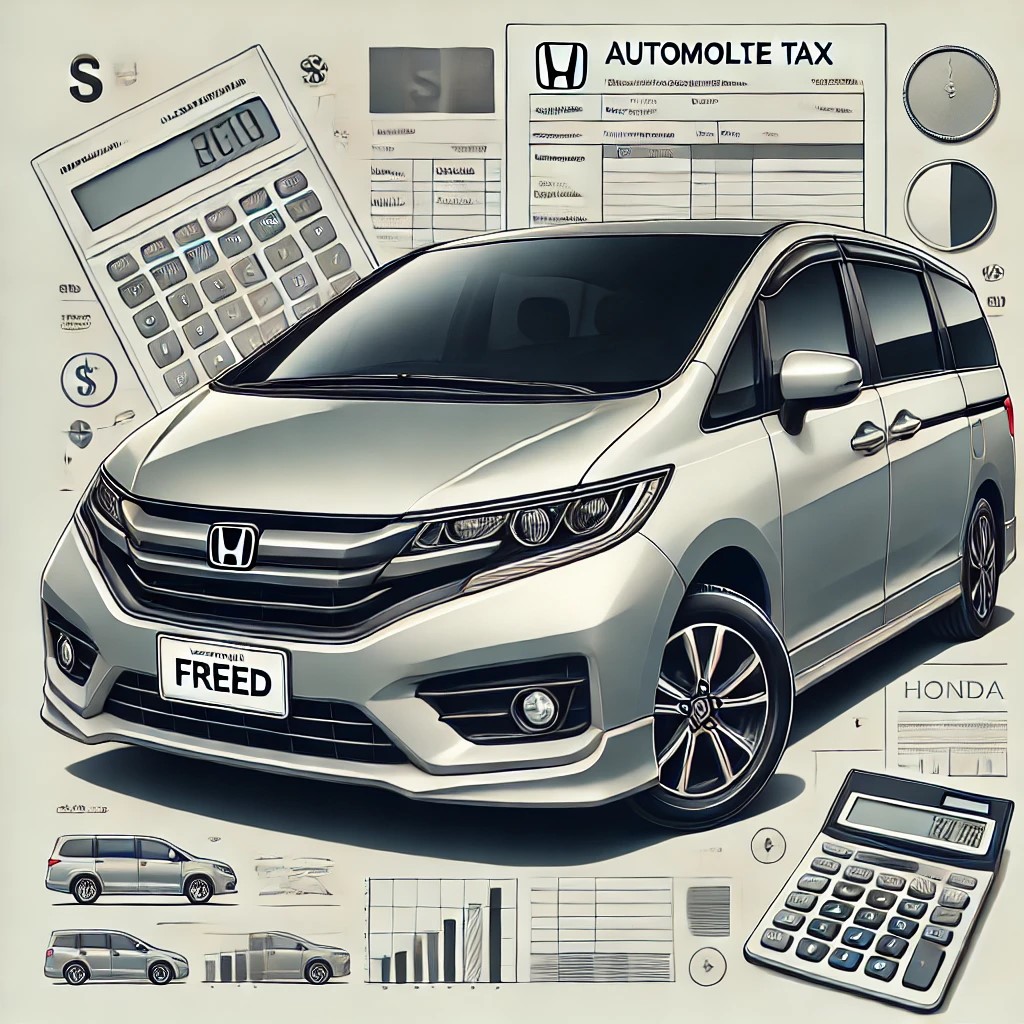
フリードの自動車税は、クルマを所有するうえで避けて通れない大きな支出のひとつである。ホンダの人気ミニバン「フリード」は、コンパクトながら室内空間が広く、家族連れやアウトドアを楽しむ人たちにとって頼れる存在だ。しかし、クルマを維持するためには燃料費や保険料だけでなく、この自動車税もしっかり理解しておかなければならない。フリードのオーナーやこれから購入を検討している人にとって、どのタイミングでどのくらい支払う必要があるのかは非常に気になるポイントだろう。
本記事では、フリードの自動車税にまつわる詳細を徹底的に掘り下げる。排気量区分やエコカー減税、法改正の動向など、知っていると得する情報を総合的にカバーするので、読後には「自分がどれくらい負担するのか」「どうすればコストを抑えられるのか」が明確になるはずだ。この記事を最後まで読むメリットは以下のとおりである。
- フリードの自動車税のしくみがわかる
- 実際に必要なコスト感を把握できる
- 自動車税を抑えるためのヒントを得られる
- 法改正や減税制度の動向がつかめる
それでは、フリードの自動車税について一緒に確認していこう。
■フリードの自動車税とは?
フリードの自動車税とは、クルマを所有している人が毎年支払う地方税のことである。正式には「自動車税(環境性能割・種別割)」と呼ばれるが、一般的には「自動車税」として認識されている場合が多い。この税金は排気量やクルマの環境性能によって金額が変わるのが特徴で、所有者が住んでいる都道府県に納める仕組みだ。
フリードは小型ミニバンという位置づけで、排気量は1.5L前後である。ガソリン車とハイブリッド車がラインナップされており、それぞれの環境性能やグレードによって自動車税の金額も異なってくる。また、フリードには「フリード+」と呼ばれる派生モデルも存在するが、基本的にはエンジンの排気量が同じであるため、大きな違いはない。重要なのは、排気量の区分がどこに当てはまるかだ。
■フリードの自動車税の計算方法
フリードの自動車税を考える際に押さえておきたいのは、「排気量区分」「取得時の税金」「翌年以降の毎年課税」の3つである。この3つをしっかり理解することで、フリードの所有にかかる税金がどのように決まるかがわかる。
排気量区分と税額
自動車税(種別割)の基本部分は、クルマの排気量によって決まる。フリードは1,500ccに該当するので、1,000〜1,500cc超〜2,000cc以下の区分に当てはまる。自家用乗用車の一般的な区分は以下のとおりだ。
- 1,000cc以下
- 1,000cc超〜1,500cc以下
- 1,500cc超〜2,000cc以下
- 2,000cc超〜2,500cc以下
- 2,500cc超〜3,000cc以下
……といった具合で区切られている。
ただし、排気量の細かい数字でギリギリ変わることもあるため、念のため車検証で「総排気量」をチェックするとよい。フリードの場合、多くが1,496ccなどに設定されており、税制上は「1,500cc超〜2,000cc以下」に該当する。結果として毎年おおむね3万5千円前後(地域による変動や制度改正による微調整はあるが)を支払うケースが多い。
なお、4WDモデルなど車両重量が増加しても自動車税には直接影響しない。あくまで排気量が基準であり、重量は自動車重量税の計算に関わる部分なので混同しないよう注意が必要だ。
取得時の税金
クルマを購入するときには、環境性能割(旧自動車取得税)が発生する可能性がある。フリードの場合、燃費性能やグレードによっては減税対象になることがあるため、購入前にはディーラーからしっかりと説明を受けるべきだ。ハイブリッドモデルやエコカー認定を受けているグレードは、一部または全額が免税または軽減される場合がある。これについては、車両価格や燃費基準の達成度などさまざまな要因が組み合わさるので、必ず確認しておきたいポイントである。
■フリードハイブリッドの場合はどうなる?
近年、低燃費で環境に配慮されたハイブリッド車への需要が高まっている。フリードにもハイブリッドモデルが存在し、ガソリン車よりも燃費が優れるため長期的に見れば燃料費の節約も期待できる。また環境性能が高いことから、減税措置を受けやすいのもメリットだ。
具体的には、ハイブリッドモデルは排気量こそガソリン車と同じ1.5L前後だが、環境性能割(取得時)で減税率が高く設定されている場合がある。さらに、エコカー減税によって一定期間、自動車税の減免を受けることができるケースもある。これはモデルイヤーや燃費基準の達成度によって変動するため、実際に支払う金額は購入年度や各種基準の改定具合によって異なる。ただし、ハイブリッド車であっても排気量区分は変わらないため、毎年の自動車税は3万5千円前後が目安だ。しかし、エコカー減税やグリーン化特例が適用されると少し安くなるので、結果的にガソリン車より多少おトクになることが多い。
フリードハイブリッドの実燃費は市街地走行や高速道路で異なるが、一般的にはガソリン車より数km/L程度良いとされている。長距離ドライブや休日のレジャーなどでよく使う人にとっては、燃費の差が積み重なって大きなコスト削減につながる点も見逃せない。
■支払い時期や方法
フリードの自動車税は、原則として毎年4月1日時点でクルマを所有している人に対して課税される。そして、自治体から納税通知書が届き、通常は5月末までに支払う流れだ。具体的な支払い方法としては以下のような手段がある。
- 金融機関や郵便局の窓口で支払う
- コンビニエンスストアで支払う
- クレジットカードやインターネットバンキングを利用する
- 口座振替を設定して自動引き落としにする
最近では、納税通知書に付帯されるバーコードやQRコードを読み取ってスマホアプリから支払いができる自治体も増えている。自分のライフスタイルに合った方法を選べるようになったのは便利な点である。とはいえ、納期を過ぎると延滞金が発生し、車検時に納税証明書が必要となるため、うっかり忘れないよう注意が必要だ。
もし引っ越しや転勤などで住所が変わった場合は、自治体からの通知書が届かない恐れもある。その場合は、自発的に管轄の税事務所へ連絡し、納付書を送付してもらうか窓口で再発行してもらうのが賢明だ。
■フリードの自動車税を抑えるポイント
毎年数万円単位で発生するフリードの自動車税は、なるべく負担を軽くしたいと考える人が多い。そのための方法としては、大きく分けて「新しくクルマを買うときの選び方」と「現在所有しているクルマの減税制度活用」が挙げられる。
エコカー減税の活用
エコカー減税は、環境性能の高いクルマを普及させるために設けられた優遇措置である。フリードのハイブリッド車はこの恩恵を受けやすく、一定の燃費基準を達成していれば環境性能割や自動車税(種別割)が減免される。さらに、最新の基準を満たすモデルであればグリーン化特例(グリーン税制)が適用され、一時的に税額が軽減される場合もある。これらの制度は年ごとに改正されることが多いため、購入前には最新情報をチェックしておきたい。
車検証のチェックポイント
意外と見落としがちなのが、車検証に記載されている排気量や初度登録年月、車両重量などの情報だ。これらの項目は税金計算に直結する場合がある。特に初度登録年月が古いクルマだと、エコカー減税やグリーン化特例を受けにくいことがある。逆に、新しいモデルや特別仕様車だと、燃費性能が向上して優遇率がアップしているかもしれない。もし中古車でフリードを購入するなら、車検証をじっくり見比べるとよいだろう。
また、ハイブリッド車でもバッテリーの劣化が進むと燃費が悪化し、環境性能が下がる場合がある。法定点検や車検時には、ハイブリッドシステムのコンディションもチェックしてもらうと安心だ。
■自動車税の見直しや法改正
フリードの自動車税を考えるうえでは、法改正や税制改正の動向に注意する必要がある。近年は環境負荷を軽減するクルマが優遇される方向性が強く、ガソリン車やディーゼル車から電気自動車、ハイブリッド車などへの移行を促すような制度設計が進んでいる。過去には「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」に移行したように、名称やしくみが随時変化しているのだ。
さらに、二酸化炭素(CO2)の排出量を基準にした課税方式へ移行する動きも世界的に見られる。日本国内においても、排気量だけでなくCO2排出量をベースに税金額を決めるしくみに変わる可能性がある。そういった場合、フリードのハイブリッドモデルは税率が下がり、ガソリン車はやや高めになるといった改定が行われるかもしれない。
また、地方自治体ごとに独自の補助金制度や優遇制度を導入している場合もある。特にEVやPHV(プラグインハイブリッド)など、一部地域では購入時や充電設備の設置に対して補助が出ることもある。フリードの場合は純粋なEVモデルは存在しないが、これから先に導入されるかもしれない。長期的な視点で、次期モデルの動向などにもアンテナを張っておくといいだろう。
■よくある疑問Q&A
ここでは、フリードの自動車税に関してよくある疑問をいくつか取り上げる。
Q1. フリードは1,500ccなのに、どうして自動車税が3万5千円前後になるのか?
A. 自動車税は1,500cc以下で一括りになっているわけではなく、「〜1,000cc」「1,000cc超〜1,500cc以下」「1,500cc超〜2,000cc以下」などのように段階的に区分されている。フリードの実排気量は1,496cc前後だが、税制上は「1,500cc超〜2,000cc以下」に該当するため、その区分の税額が課される。
Q2. フリード+(プラス)でも税金は同じなのか?
A. フリード+とフリードは同じ排気量のエンジンを積んでいるケースが大半なので、基本的に自動車税は同じ区分に当てはまる。ただし、グレードや駆動方式、燃費性能が若干異なる場合があるため、環境性能割やグリーン化特例の適用率は違う可能性がある。
Q3. 新車購入時に一時的に払う税金はどうなる?
A. 新車購入時には、環境性能割や重量税など、複数の税負担が発生する。フリードの自動車税以外にも、車両本体価格以外の諸費用として計上されることが多い。ハイブリッドモデルならば一定の減税措置が受けられるので、支払額はガソリン車と比較して低くなる場合が多い。
Q4. もし廃車や売却をした場合、自動車税は返金されるのか?
A. 自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、年度の途中でクルマを手放しても税金そのものは原則返金されない。自治体によっては、軽自動車税や一部の税金で月割りで還付される制度があるが、普通車の自動車税では基本的に月割り還付はない。
Q5. 法改正でフリードの税額が大幅に変わる可能性は?
A. 近い将来、排気量ベースからCO2排出量ベースに移行するなど、大きな制度変更が行われる可能性はゼロではない。しかし、実際の導入時期や具体的な税率は未定であり、国の方針を随時注視することが重要だ。
Q6. フリードをキャンピングカー仕様に改造したら税額は変わる?
A. 一般的に、車両区分が「8ナンバー(特殊用途車)」になると税制度が変わる場合がある。ただし、フリードを大がかりに改造してキャンピングカー登録にする事例はあまり多くない。仮に改造して車検証の用途が変わる場合は、改造内容によって税額が上下する可能性があるので、事前に陸運局や専門業者に相談するのが望ましい。
Q7. 新古車や登録済み未使用車の場合はどうなる?
A. 新古車や登録済み未使用車は、既に初度登録されているためエコカー減税やグリーン化特例が適用される期間が短くなっている場合がある。購入する時点でどのくらい減税を受けられる余地が残っているかを販売店に確認し、場合によっては新車と比較してトータルコストがどう変わるか計算してみるとよい。
■特別仕様車やオプションによる違いは?
フリードには、純正アクセサリーを装着した特別仕様車や、カスタマイズパーツを取り入れたModulo Xなどのグレードが設定されることがある。こうしたグレードであっても排気量が同一ならば、自動車税の区分は変わらない。ただし、車両本体価格が上がる分、環境性能割の課税額に影響する可能性がある点は要注意だ。たとえば、カスタムパーツの追加で車両重量が変化し、重量税の区分が変わる場合もあるので、総合的な維持費を見積もるときには細部まで考慮しておくことが大切である。
■まとめ
フリードの自動車税は、毎年の出費として見過ごせない金額である。特にフリードの排気量は1,500cc前後に分類され、税区分は「1,500cc超〜2,000cc以下」となるため、年間3万5千円前後が一般的だ。また、環境性能が高いハイブリッドモデルでは減税措置が適用され、多少なりとも節約が期待できる。
支払い時期は毎年4月1日時点の所有者に対して課せられ、5月末までに納めるのが基本である。口座振替やコンビニ払いなど支払い手段は多様化しているものの、期日を過ぎれば延滞金が発生するので要注意だ。もしこれからフリードを購入しようと考えているなら、エコカー減税やグリーン化特例などの最新情報をチェックし、もっとも有利なタイミングとグレードを選ぶといい。
また、自動車税に関する制度は時代の流れに合わせて変わっていく。CO2排出量を基準とする新しい税制への移行など、ここ数年は環境面への配慮が強く求められている。フリードのようなハイブリッド車は、これらの改正によって今後さらに優遇される可能性もある。だからこそ、常に最新の情報を追いかけておくことが大切だ。フリードの自動車税に限らず、自動車関連の税制度全般を定期的に見直すことで、長期的な維持費を抑えつつ快適なカーライフを送れるだろう。
最後にもう一度、ポイントをまとめておこう。
- フリードの排気量は1.5L前後で、税区分は「1,500cc超〜2,000cc以下」
- 新車購入時には環境性能割が課されるが、ハイブリッド車なら減税措置あり
- 毎年4月1日時点の所有者に対して課税、5月末までに納付
- エコカー減税やグリーン化特例を最大限活用してコスト削減
- 法改正で今後はCO2排出量課税への移行が進む可能性も
こうした情報を踏まえつつ、フリードの自動車税を賢く扱いながらカーライフを楽しんでほしい。





