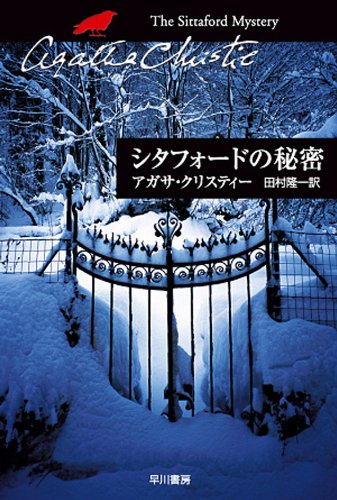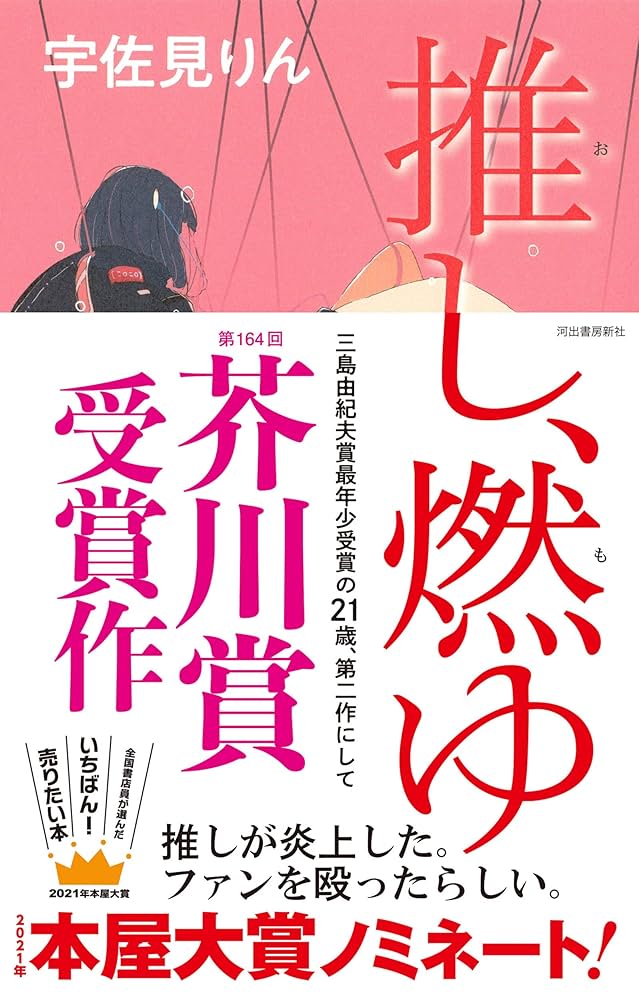
「推し、燃ゆ」のあらすじ(ネタバレあり)です。「推し、燃ゆ」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。
高校生の「あかり」は、男女混合アイドルグループ「まざま座」の上野真幸を“推す”ことに人生の軸を置いています。ところがある日、真幸がファンを殴ったという報道で炎上し、あかりの日常は大きく揺らぎます。
学校やバイトでつまずき続けるあかりは、ネットでの応援や記録に没頭し、彼の言動を細かく“解釈”して心の支えにします。しかし炎上後、真幸は支持を落とし、あかり自身も留年の決定など現実が重くのしかかります。
追い打ちのように「まざま座」の解散、真幸の引退が報じられ、あかりの支柱は崩れ落ちます。ラストのライブを見届けた彼女は、流出した住所を手掛かりに真幸の住む集合住宅を訪ねてしまいます。
そこで見たのは、洗濯物を抱える女性の生活の気配――“推し”の私生活の現実でした。あかりは、自分が積み上げてきた大量のファイルや記録と、誰かの日常の一片との落差に打ちのめされます。
帰宅後、衝動のまま綿棒ケースを床にぶちまけ、彼女は散らばった一本一本を拾い集めます。それは、なくなった“背骨”を自分の手で拾い直すような、静かな再起の身振りとして描かれます。
「推し、燃ゆ」のあらすじ(ネタバレあり)
物語は「推しが燃えた」という衝撃の書き出しで始まります。主人公のあかりは、男女混合アイドル「まざま座」の上野真幸を徹底的に応援している高校生です。
あかりは学校でも家庭でも居場所を失いがちで、学業やバイトの要領も悪い。けれど推し事だけは別で、彼女はブログを書き、発言をノートに書き写して生きる根拠を得ています。
ところが真幸がファンを殴ったという事件で大炎上。ネット上の支持は急落し、グループ内での序列にも影が差します。
あかりの現実も悪化します。提出物の不備や欠席が重なり、留年が決定。家族との関係も冷え込み、家を出て祖母の家で一人暮らしを始める展開が示されます。
友人の成美は地下アイドルを応援し、触れ合いを求める推し方をしている一方、あかりは距離のある“解釈”へ傾き、両者のスタンスの差が浮かび上がります。
やがて真幸はインスタライブなどで動きを見せ、最終的に「まざま座」の解散が公式化。あかりは“背骨”を失くす不安に飲み込まれます。
解散ライブの日、あかりは終わりを見届けながら「推しのいない人生」を想像し、空洞を抱えたまま帰路につきます。
その後、ネットに流れた住所情報を頼りに、あかりは真幸の住居があるマンションへ。そこでは洗濯物を抱えた女性の姿があり、私生活の生々しい痕跡に心が裂かれます。
家へ戻ったあかりは、綿棒ケースを床に叩きつけて散らし、無数の白い棒を一つずつ拾い集めます。この反復は、砕けた自分の“背骨”を拾い直す所作として読めます。
物語は、失った支えを他者任せにせず、生活の手触りを少しずつ取り戻していく予感の中で幕を閉じます。
「推し、燃ゆ」の感想・レビュー
はじめに率直にお伝えします。この作品は、推しという語の軽やかさと、依存でも逃避でも片付けられない切実さを同時に抱えています。読んでいる最中、あかりの視界の狭さと鋭さに、何度も胸が詰まりました。
あかりは「推すこと=自分の背骨」と言い切るほど、生活の中心を外部に託しています。だからこそ炎上は単なる“ショック”ではなく、体の芯をひねられるような痛みとして迫ります。この強度が作品の核です。
物語の語りは説明を極力削ぎ、出来事や感触を前面に出します。それが、あかりの思考の跳躍や過集中、そして社会的段取りへの不器用さを、読者の身体感覚に近いところへ引き寄せてくれます。
学校・家族・労働という三つの領域で、あかりは常に成果や要領を求められます。しかし、彼女が本当にうまくやれているのは推し事だけ。ノートの記録やブログの更新は、彼女にとって社会で機能する練習の場でもあり、祈りでもあります。
友人・成美との“推し方”の差は象徴的です。触れ合いを志向する成美に対し、あかりは距離を保ちながら“わかりたい”と願う。この二項の間で揺れる視線が、推しという営みの多様性を立体化していました。
とはいえ、距離のある応援は安全圏ではありません。炎上は、スクリーンの向こう側の人間性――暴力の事実や生活の気配――を否応なく突き付けます。推しを偶像のまま保っていた膜が破れる瞬間の寒気が、全編を貫きます。
解散・引退の連鎖は、ファンダムにとって“喪失儀礼”です。舞台装置が片付けられると同時に、あかりの内側から音を立てて抜け落ちていくものがある。ここで描かれるのは、娯楽の終演ではなく、自我の組み替えの始まりです。
ラストのマンション場面は、倫理的な違和感を意図的に孕みます。住所特定情報に導かれて現場へ向かう行為は危うい。それでも作者は非難の台詞で裁かない。洗濯物という生活の断片が、説明より雄弁に線引きを教えます。
そして綿棒を拾う所作。派手な救済を拒み、手の届く半径で自分を立て直す。あかりが選ぶのは、他者の認知ではなく、自分の手の働きです。ここに、再起のリアリズムがあります。
作中で繰り返される“背骨”という自己定義は、現代の“推し文化”に普遍性を与えます。私たちは皆、何かを拠り所にしています。対象が人でも作品でも制度でも、それが折れたとき、何を拾い直すのか。この問いが読後に残ります。
作品は、炎上の是非を裁く物語ではありません。むしろ、推す側の責任と限界、そして関係の片務性を引き受けたうえで、どう自分の生活を作り直すかを問います。だから読後の感情は、悲嘆だけでなく、静かな決意へと移行します。
文体面についても触れたいです。説明を抑え、具体の物や行為を積み重ねることで、読者が意味を能動的に掴みにいく読書体験をつくっています。これが、短い分量でも濃密な余韻を生む仕掛けです。
家族の描写は冷たいようでいて、断絶の彼方に愛着の影も見えます。祖母の家での独居にせよ、親との距離にせよ、完全な断絶ではなく“うまくいかないまま続いてしまう関係”として提示される点が、現実に近い。
他方で、ファンコミュニティやランキング文化、可視化される支持の数値が、あかりを支え、同時に追い詰めます。物語はその構造的圧力を責め立てず、ただ照射します。その中で彼女は、可能な責任を自分の手に戻していくのです。
まとめとして――「推し、燃ゆ」は、現代の推し文化を素材にしながら、喪失と再生の物語を描き切っています。燃えたのは偶像だけではなく、彼女の内側にあった支柱でもある。残灰の中から何を拾うか。最後の無言の動作が、その答えでした。
まとめ
-
高校生のあかりは「まざま座」の上野真幸を全力で応援している。
-
真幸がファンを殴ったという報道で炎上が起こる。
-
あかりは学校やバイトで躓き、記録とブログだけが拠り所になる。
-
友人・成美との“推し方”の違いが浮かび、あかりの視点が際立つ。
-
留年が決まり、家族との関係も悪化し、祖母の家で暮らし始める。
-
「まざま座」の解散と真幸の引退が明らかになる。
-
解散ライブを見届けたあかりは、空洞を抱えたまま帰路につく。
-
ネットに出回った住所を頼りに真幸のマンションを訪ねる。
-
洗濯物を抱える女性の姿に、私生活の現実を突き付けられる。
-
帰宅後、綿棒をぶちまけ、一本ずつ拾い集める所作で終幕。