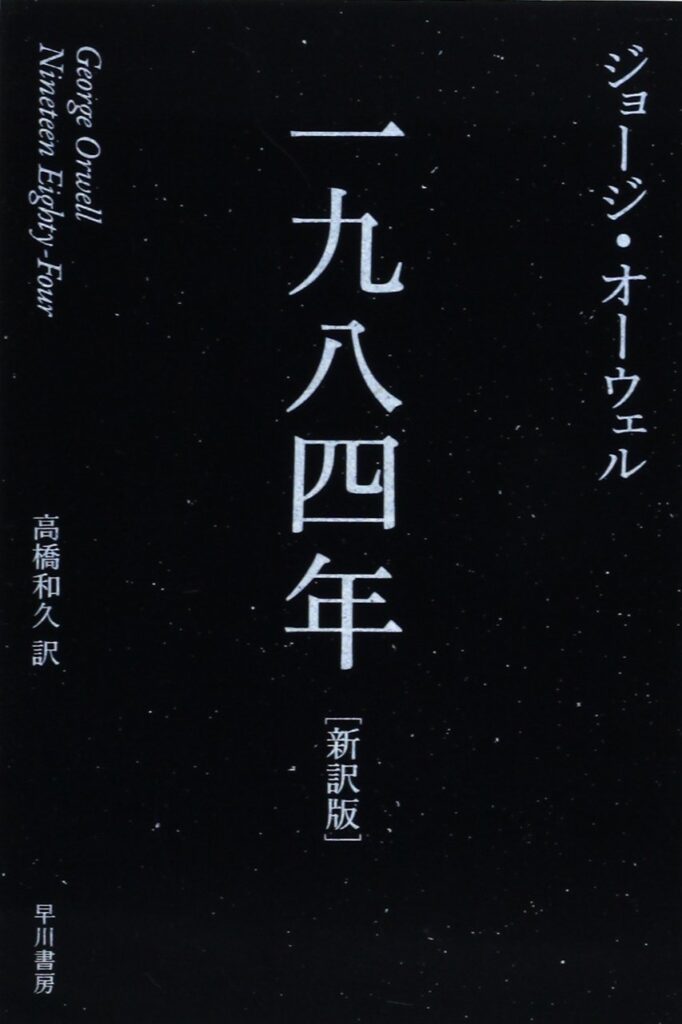『嘔吐』のネタバレを含むあらすじをご紹介します。
ジャン=ポール・サルトルの『嘔吐』は、20世紀フランス文学における実存主義を体現した作品です。主人公アントワーヌ・ロカンタンは、架空の町ブーヴィルに住み、18世紀の政治家マルキ・ド・ロールボンに関する伝記を執筆しています。しかし、次第に自らの存在に意味を見出せず、不安と虚無感に苛まれます。日々の出来事や物体に触れる中で、存在そのものの重さを意識し、耐え難い感覚に襲われます。この“嘔吐”という不快感は、人生の無意味さを浮き彫りにし、アントワーヌは自分の生き方を見直すきっかけとなります。
物語は彼が自身の存在を受け入れ、虚無と闘いながら新たな意義を見つける決意で終わります。
- 主人公アントワーヌ・ロカンタンの苦悩について
- 実存主義の概念について
- 虚無感とその克服について
- 小説の象徴的なシーンについて
- アントワーヌの自己発見の過程について
「嘔吐(サルトル)」の超あらすじ(ネタバレあり)
ジャン=ポール・サルトルの小説『嘔吐』は、20世紀フランス文学の代表的な存在で、実存主義の哲学を反映した作品です。主人公のアントワーヌ・ロカンタンは、人生に深い不安と意味の無さを感じ、存在そのものに対する苦悩を描写しています。物語は彼がフランスの架空の町ブーヴィルで過ごす日々を通じて展開され、彼の内的な思索と現実の出来事が緊密に結びついています。
ロカンタンは独身の歴史学者で、18世紀の政治家で探検家のマルキ・ド・ロールボンに関する伝記を書いています。彼は研究のためにブーヴィルに滞在していますが、次第に自身の生活や仕事に意味を見出せなくなり、心の平穏を失っていきます。物語の中でロカンタンは、過去に愛した女性アニーを思い出しますが、再会しても彼女との再接触は虚無感を払拭することができません。アニーとの会話は、二人の間の溝と、時間がもたらした変化を際立たせるものでした。
物語が進むにつれて、ロカンタンは町での観察や偶然の出会いを通じて次第に現実に対する感覚を失っていきます。彼は公園での散歩中、石や木の根などの物体に直面し、それが彼にとって耐え難いほどの実存的な不快感を引き起こすきっかけになります。ここで彼は、これらの物体が存在そのものを無意味に感じさせる「嘔吐」の感覚をもたらすことを悟ります。物の存在は確固たるものであり、そこに意味を見出そうとする自分の試みが無意味であることに気づきます。存在そのものの重たさが彼を圧倒し、彼はその感覚に飲み込まれるように感じます。
一方、ロカンタンは町の住民たちを観察し、彼らの生活に同様の虚無を感じます。カフェで出会う「自嘲的な哲学者」との会話や、図書館での古くからの職員とのやりとりは、彼の孤独を一層強めます。これらの交流はすべて、彼の実存的な孤立と、それを取り囲む社会との疎外感を強調します。
最も象徴的な場面は、ロカンタンがカフェでジャズ音楽「サム・オブ・ジーズ・デイズ」を聴いたときです。この音楽は一瞬だけ彼に救済と意味を提供するように感じられます。しかしその瞬間は儚く、ロカンタンは再び虚無感に戻ります。この経験は、彼が言葉によっては表現できないほどの実存的な「嘔吐」を感じることを決定づけます。
最終的に、ロカンタンは自身の存在を受け入れ、世界に内在する無意味さを理解しようとします。彼は、人生には意味がないことを認めつつ、自分の物語を生きることで、自分なりの意味を創造しようと決意します。彼の伝記を書くというプロジェクトも無意味に感じられるようになりますが、彼は小説を書くことで自分自身を超越する試みを模索します。これは実存主義の哲学における、存在を自覚し、その中で自らの意味を構築する行為を象徴しています。
全体を通して『嘔吐』は、人間が外部の世界との関わりを通じて自己の存在を意識し、そこに直面する根源的な不安や不快感を鋭く描き出しています。この小説は、日常的な現実の背景に潜む根本的な問いを浮かび上がらせ、存在そのものへの問いを読者に投げかけます。
「嘔吐(サルトル)」の感想・レビュー

ジャン=ポール・サルトルの『嘔吐』は、実存主義の哲学を深く掘り下げた作品です。この小説は、主人公アントワーヌ・ロカンタンが自身の存在と向き合い、虚無感を抱く過程を描写しています。舞台はフランスの架空の町ブーヴィルで、ロカンタンは18世紀の政治家マルキ・ド・ロールボンの伝記を書きながら、自らの人生の意味を模索します。日常生活で感じる不安や孤独は、彼の思索を実存的な領域に導き、彼は周囲の物や出来事に対して次第に強烈な嫌悪感を抱くようになります。
特に象徴的なのは、彼が公園で経験する“嘔吐”の感覚です。このときロカンタンは、石や木の根などの日常的な物の存在に圧倒され、その存在の無意味さを自覚します。これらは彼に、世界が持つ客観的な重さと自分の孤立を突きつけるものでした。サルトルはこの描写を通じて、人間がどのように存在の重荷を感じるかを描いており、それは単なる不快感ではなく、人生そのものに対する哲学的な問いを提起しています。
また、物語を通じて、ロカンタンは過去の恋人アニーとの再会を試みますが、その再会は彼の虚無感を和らげるものではありませんでした。これにより、他者との関係や過去への郷愁が自分の存在の不安を救うものではないことが示されます。彼の内面の孤独は、自らの中でしか解決できないものであることを強調しています。
一方、カフェでジャズ音楽「サム・オブ・ジーズ・デイズ」を聴くシーンは、一時的に彼に安堵を与えます。この音楽は、意味のない日常に美を感じさせる瞬間の象徴であり、存在の重さを忘れさせるものとして描かれています。しかし、音楽が終わるとともにロカンタンは再び虚無へと戻ります。この場面は、意味を外部に求めても儚いことを象徴しています。
物語の最後で、ロカンタンは人生の意味が外部から与えられるものではなく、自らが創造するものだと理解します。彼は新たな生き方を模索し、存在の重さと向き合いながらも、自分だけの意味を見つける決意をします。サルトルはこの結末を通じて、実存主義の中心的なテーマである“自己の選択と自由”を提示しています。
こうして『嘔吐』は、人間が自身の存在に直面したときの深い不安と、それを乗り越えるための個人の葛藤を鮮烈に描き出しています。
まとめ:「嘔吐(サルトル)」の超あらすじ(ネタバレあり)
上記をまとめます。
- アントワーヌはブーヴィルで伝記を執筆している
- 孤独と疎外感に苛まれる
- 公園の散歩で“嘔吐”という不快感を体験する
- 物の存在に圧倒される
- アニーとの再会は虚無を払拭しない
- ジャズ音楽に一瞬の安らぎを見出す
- 自分の存在に対する気づきを得る
- 人生に意味を見出せなくなる
- 存在の重さに耐えられなくなる
- 自己の意味を創造しようと決意する