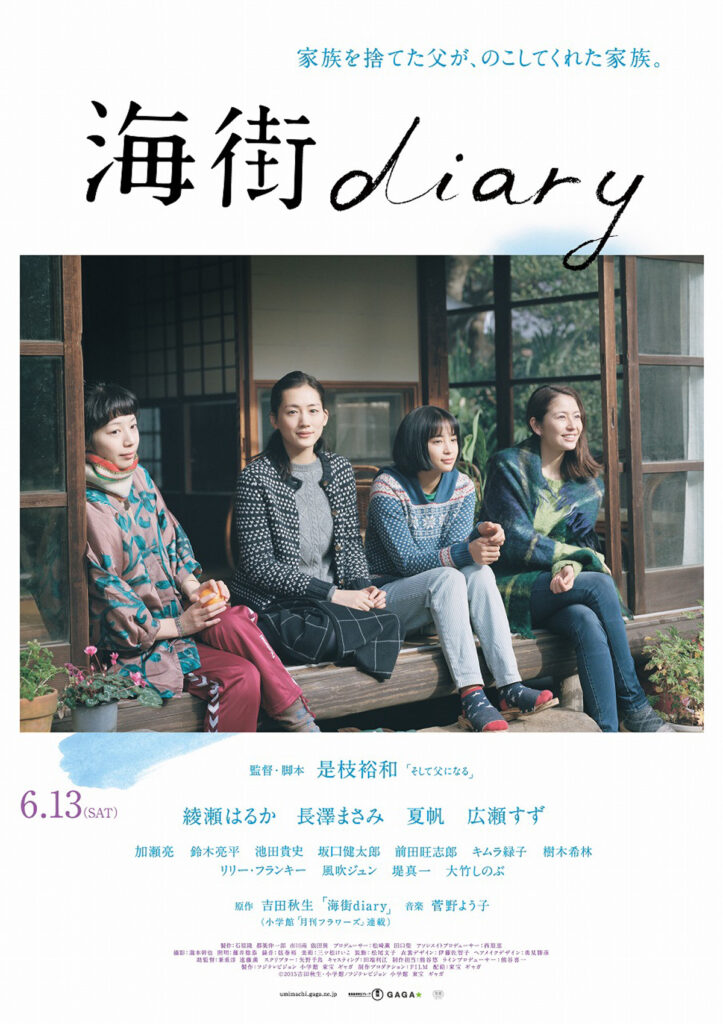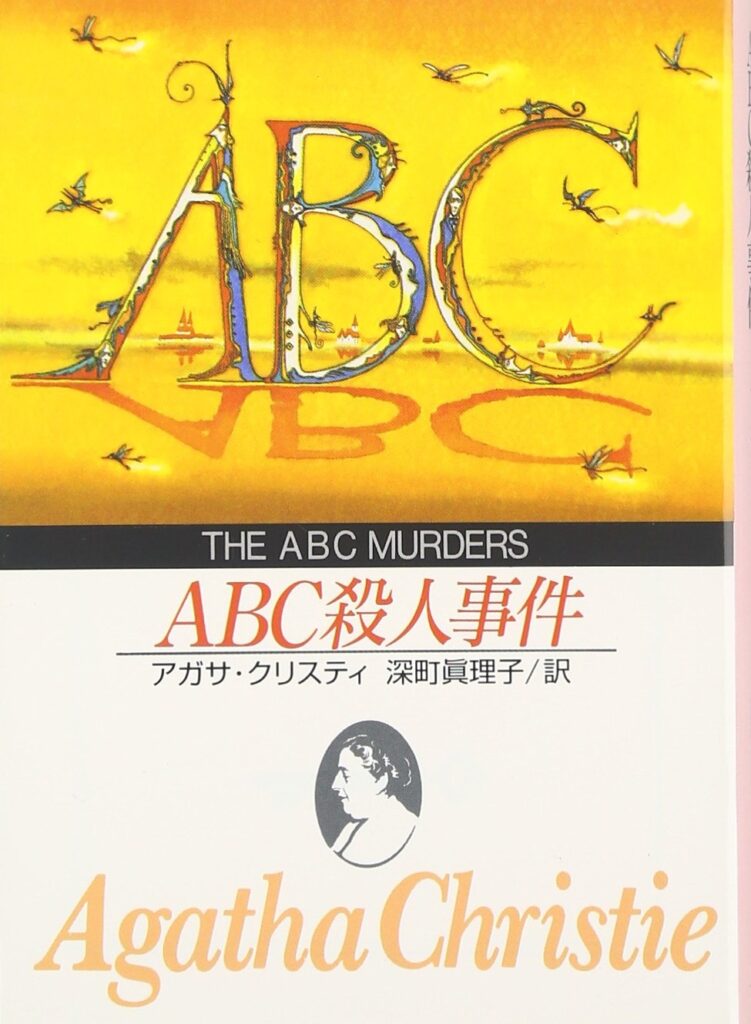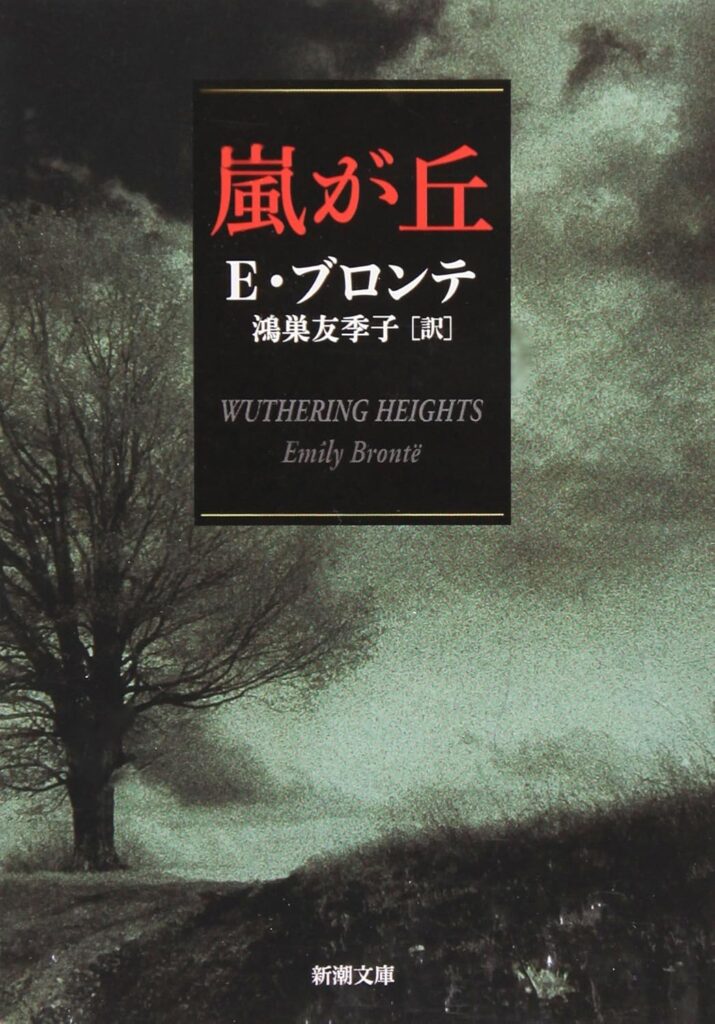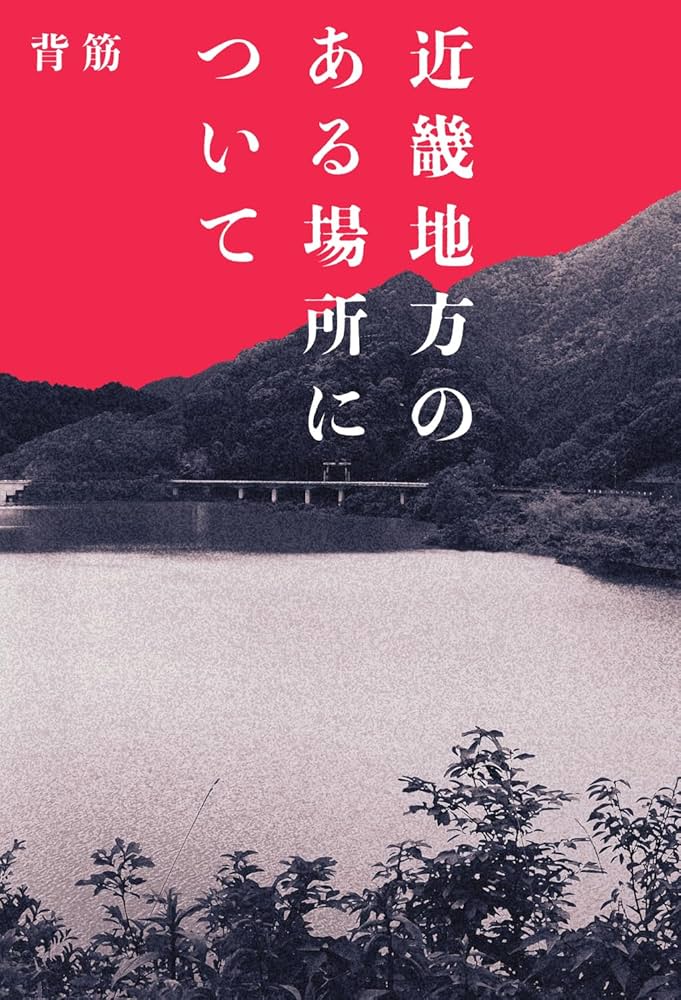
「近畿地方のある場所について」のあらすじ(ネタバレあり)です。「近畿地方のある場所について」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。
本作は、一般的な小説とは一線を画す形式で構成されています。物語は、雑誌記事の切り抜き、インタビューの録音を文章化したもの、インターネット掲示板の書き込みといった、客観的資料とされる断片の集合体として提示されます。
これらの無関係に見える資料は、すべて近畿地方に実在するとされる、ある一点を指し示しています。読者は、散らばった記録を読み解き、事件の背後にある恐ろしい真実を自ら繋ぎ合わせていく調査員のような役割を担うことになるのです。
しかし、本作の本当の恐怖は、記録された事件そのものに留まりません。むしろ、これらの情報を「読み、理解する」という行為自体に、巧妙な罠が仕掛けられています。
この記事では、バラバラにされた物語のピースを時系列に沿って再構築し、すべての点が線で結ばれたときに浮かび上がる、戦慄の真相に迫っていきたいと思います。
「近畿地方のある場所について」のあらすじ(ネタバレあり)
物語の根源は、明治時代のある村の悲劇にあります。村に住む「まさる」という男が、山に棲む何者かに唆され、村人から凄惨なリンチの末に命を落としました。この出来事が、土地に根付く呪いの始まりとなります。
まさるの怨念か、あるいは彼を操った存在の力か、その呪いは白い猿の姿をした神「ましらさま」として土地に定着します。ましらさまは、生贄や「お嫁さん」を山へ求める、土着の恐ろしい神として語り継がれていきました。
時代は下り昭和後期。呪いは「まっしろさん」という、身代わりを立てて鬼から逃れる子供たちの遊びへと形を変えます。そして平成の世、この遊びの中で「あきら」という少年が、人間の身代わりにされた末に命を落とすという悲劇が起こります。
息子の死に絶望したあきらの母は、自身が所属していたカルト教団「スピリチュアルスペース」から、ご神体である「石」を盗み出します。彼女は、その石を使い、息子を蘇らせるための禁断の儀式に手を染めました。
しかし、儀式は惨憺たる失敗に終わります。呼び出されたのは、息子の姿を借りた全く別の邪悪な存在「あきらくん」でした。
全てを失った母は自ら首を吊って命を絶ちますが、その深い怨念は、新たな怪異「ジャンプ女」としてこの世に生まれ変わります。彼女は、夜な夜な子供部屋を窓から覗き込み、飛び跳ねるように移動する恐ろしい存在となりました。
土地に縛られていた「ましらさま」とは異なり、「ジャンプ女」は現代の技術を理解していました。彼女はインターネットの掲示板や動画サイトを利用し、自らの呪いを地理的な制約を超えて爆発的に拡散させ始めます。
フリーライターである語り手の「背筋」は、編集者の小沢からの依頼を受け、この近畿地方にまつわる一連の怪異の調査に乗り出します。しかし、それは呪いの深みへ自ら足を踏み入れる行為に他なりませんでした。
調査の最中、小沢は呪いの中心地であるダムで遺体となって発見されます。そして語り手の「背筋」もまた、知らず知らずのうちに「ジャンプ女」の精神汚染を受け、彼女の計画の最終段階を担う駒とされていたのです。
彼が執筆するこの本、「近畿地方のある場所について」こそが、呪いを最も効率的に、そして広範囲に拡散させるために「ジャンプ女」が設計した、最終兵器だったのです。
「近畿地方のある場所について」の感想・レビュー
本作「近畿地方のある場所について」が読者に与える恐怖は、単に恐ろしい話が書かれているから、というだけではありません。その根源は、物語を語る「形式」そのものにあります。本作は、雑誌記事、インタビュー記録、ネットの書き込みといった、一見すると客観的な資料の集合体という体裁をとっています。このモキュメンタリー(擬似ドキュメンタリー)形式が、フィクションと現実の境界線を曖昧にし、書かれている内容が「本当にあったことかもしれない」という、肌にまとわりつくような不気味さを生み出しているのです。
この形式がもたらすもう一つの効果は、読者の立ち位置を強制的に変えてしまう点にあります。私たちは物語を受け取るだけの観客ではありません。散逸した資料を手に、事件の年表を組み立て、点と点を繋ぎ合わせ、真相を推理することを強いられる「調査員」なのです。この能動的な参加が、他に類を見ないほどの没入感を生み、気づいた時にはもう、物語の呪われた世界から抜け出せなくなっています。
本作の恐怖を解体していくと、そこには性質の全く異なる二種類の呪いが存在していることがわかります。一つ目は、古来より土地に根付く「ましらさま」の呪いです。これは、村の因習や山岳信仰といった、民俗学的な背景を持つ伝統的な恐怖と言えるでしょう。特定の場所に縛られ、身代わりを立てるなどの儀式的な作法が通用する、いわば「アナログ」な呪いです。
それに対し、もう一つの呪いである「ジャンプ女」は、全く質の異なる現代的な恐怖を体現しています。彼女は土地に縛られません。インターネットや動画サイトといったメディアを巧みに利用し、自らの呪いを情報として拡散させます。彼女の恐怖は、特定の場所ではなく「ネットワーク」に宿るのです。これは、悪意ある情報が瞬時に世界へ広まっていく現代社会の不安を映し出した、「デジタル」な呪いと言えます。
そして本当に恐ろしいのは、この二つの呪いの関係性です。「ジャンプ女」という新しい呪いは、古い「ましらさま」の呪いを上書きしたわけではありません。むしろ、人々がその土地に対して抱いてきた古来の恐怖心や伝承を土台、つまり栄養分として利用し、自らの呪いをさらに増幅させているのです。古い恐怖が、より悪質で感染力の高い新しい恐怖を生み出すための苗床となる。この「呪いの生態系」とも呼べる構造が、本作の恐怖に底知れない深みを与えています。
ここまでの考察を経て、私たちは本作の最も核心的な恐怖にたどり着きます。それは、今あなたが手にしている、あるいは読んでいるこの「近畿地方のある場所について」という本そのものが、呪いを拡散させるために作り上げられた「呪物」であるという事実です。これは呪いの記録ではなく、呪いそのものなのです。
この仕掛けは、読書という行為の意味を根底から覆します。物語の謎を解き明かそうと資料を読み解き、点と点を繋ぎ、恐怖を感じる。その一連の知的作業こそが、実は「ジャンプ女」が仕掛けた呪いの感染プロセスそのものなのです。真実を知る行為が、汚染される行為と直結している。作者「背筋」は、彼女によって精神を巧みに誘導され、最も効果的なミーム汚染兵器を創り上げるための筆記者にされてしまったのです。
物語の語り手である「背筋」の存在も、この恐怖を増幅させます。彼は当初、冷静な調査者として登場しますが、物語が進むにつれてその精神の均衡は明らかに崩れていきます。彼は真実を暴く英雄ではありません。呪いを広めるための計画に組み込まれ、その最終媒体として利用される、哀れな操り人形に過ぎなかったのです。彼の視点を通して物語を追体験する読者は、彼の精神崩壊をすぐ隣で目撃することになります。
さらに、続編にあたる『穢れた聖地巡礼について』では、物語に更なる絶望が加えられます。背筋に協力していた研究者「K」の正体は、実は彼の成功を妬むライバルの小林という男でした。彼の目的は背筋を助けることではなく、呪いを利用して彼の精神をさらに追い込み、その地位や仕事を奪い取ることだったのです。
この人間的な悪意の存在は、背筋の置かれた状況を完全に救いのないものにしています。彼は、呪いを拡散させようとする超自然的な捕食者「ジャンプ女」と、彼の社会的生命を喰らおうとする人間的な捕食者「小林」という、二つの脅威に挟まれているのです。超自然的な呪いが彼の精神を蝕み、人間的な悪意がその弱みに付け込んで彼を社会的に抹殺しようとする。この二重の絶望が、物語世界にはいかなる救いも安息も存在しないことを、読者に冷徹に突きつけます。
複雑に絡み合った呪いの歴史を理解するために、ここで一度、出来事を時系列で整理してみましょう。
| 年代/元号 | 主要な出来事 | 関与した怪異 |
| 明治時代 | 「まさる」が村人に殺害され、土地の呪いが始まる。 | 山の存在(ましらさまの原型) |
| 1984年 (昭和59年) | ダム建設地付近で女児が行方不明になる。 | ましらさま |
| 1987年 (昭和62年) | 「まっしろさん」という身代わりを立てる遊びが流行。 | ましらさま |
| 1999年 (平成11年) | 少年「あきら」が「まっしろさん」の犠牲者となり死亡。 | ましらさま |
| 2000年 (平成12年) | あきらの母が儀式に失敗し、「あきらくん」と「ジャンプ女」が誕生。 | あきらくん、ジャンプ女 |
| 2003年 (平成15年) | 「了」の印がついた鳥居の画像など、デジタルでの呪いの拡散が始まる。 | ジャンプ女 |
| 2011年 (平成23年) | 動画配信者がお札屋敷で呪物の「石」を発見させられる。 | ジャンプ女 |
| 2019年 (令和元年) | 「背筋」が調査を開始し、編集者の小沢が死亡する。 | 全ての怪異 |
| 2023年 (令和5年) | 「背筋」が本書を出版し、「ジャンプ女」の計画が完成する。 | ジャンプ女 |
本作の結末には、いかなるカタルシスも用意されていません。悪霊が祓われることも、呪いが封印されることもなく、物語は最悪の形でその目的を達成して終わります。つまり、この本が出版され、私たちの手元に届いた時点で、呪いは見事に拡散を成し遂げたのです。最後の恐怖は、物語を読み終えたあなた自身が、今や呪いの新たな運び手になってしまったのかもしれない、という身も蓋もない事実認識です。
ここで、混乱を避けるために極めて重要な点を明記しておく必要があります。2024年に公開された映画版は、この原作小説とは全く異なる物語である、ということです。原作の持つ構造的な恐怖とは違う、より視覚的なエンターテインメントとして再構築されています。
映画版では、菅野美穂さん演じる千紘という新たな主人公が登場し、赤楚衛二さん演じる小沢を操って、亡き息子を蘇らせようとします。クライマックスでは、小沢を生贄に捧げることで、「やしろさま」と呼ばれる異形の怪物を召喚します。これらは全て映画版独自の展開であり、原作には一切登場しません。
映画版が提供するのが、スクリーンの中で完結するスペクタクルな恐怖であるとすれば、小説版が提供するのは、読者の内面へと静かに侵食してくる、より陰湿で知的な恐怖です。物語を読み終え、本を閉じた後も、その呪いはあなたの思考の中に残り続けるかもしれません。なぜなら、この小説における本当の怪物は、あなたの頭の中で、あなた自身の知性によって組み立てられてしまったのですから。
まとめ
-
明治時代、村人に殺された「まさる」の怨念が土地の呪いの始まりとなる。
-
呪いは白い猿の神「ましらさま」として伝承され、身代わりや生贄を求めるようになる。
-
昭和後期、呪いは「まっしろさん」という子供の遊びに形を変え、少年「あきら」が犠牲者となる。
-
あきらの母はカルト教団からご神体の「石」を盗み、息子を蘇らせる儀式を行う。
-
儀式は失敗し、息子の姿をした悪魔的な存在「あきらくん」を召喚してしまう。
-
絶望した母は自殺し、子供部屋を覗き込む怨霊「ジャンプ女」へと変貌する。
-
「ジャンプ女」は土地に縛られず、ネットや動画を使い、自らの呪いを拡散し始める。
-
ライターの「背筋」は編集者・小沢の依頼で調査を開始するが、小沢は呪いのダムで死体となって発見される。
-
「背筋」は「ジャンプ女」に精神を汚染され、呪いを最も効率的に広めるための「本」を執筆するよう操られる。
-
読者が手にしている『近畿地方のある場所について』という本こそが、呪いを拡散させるために作られた最終成果物である。