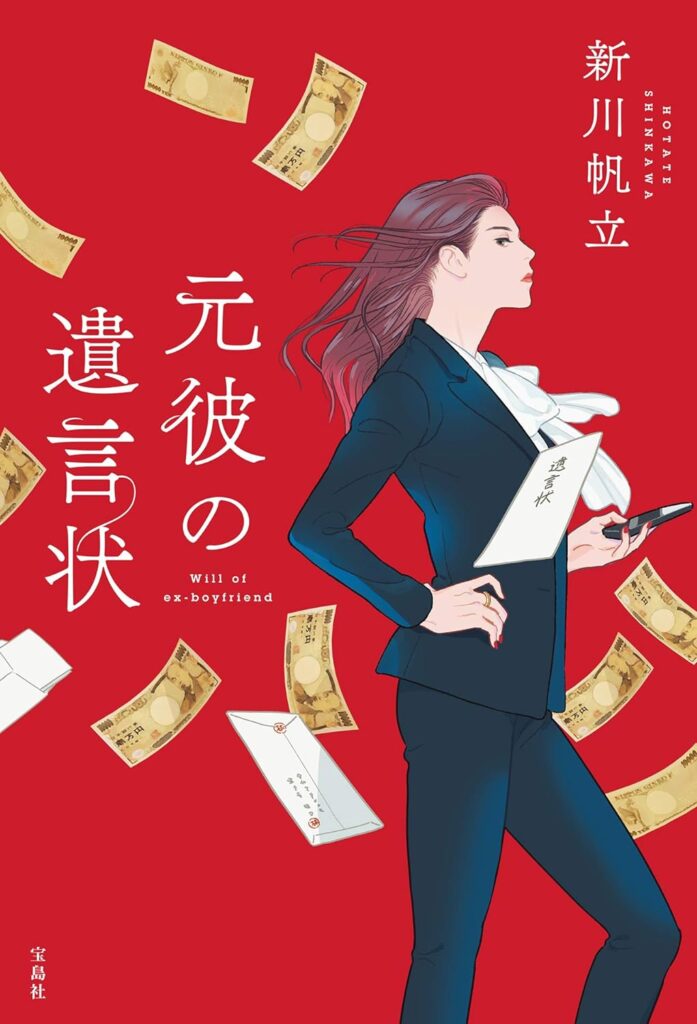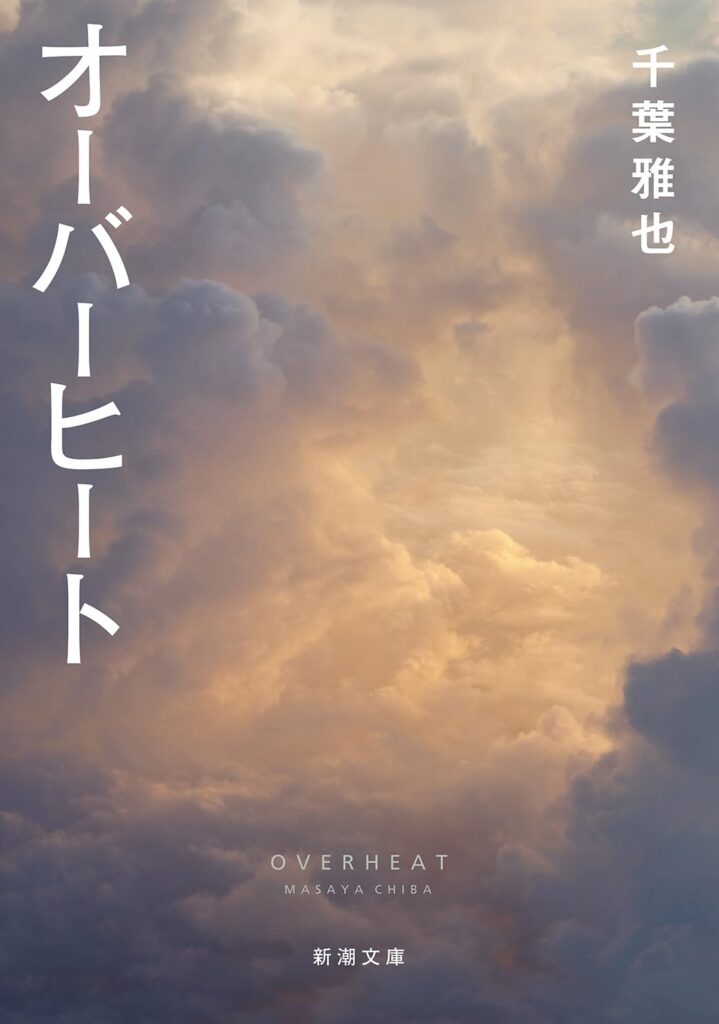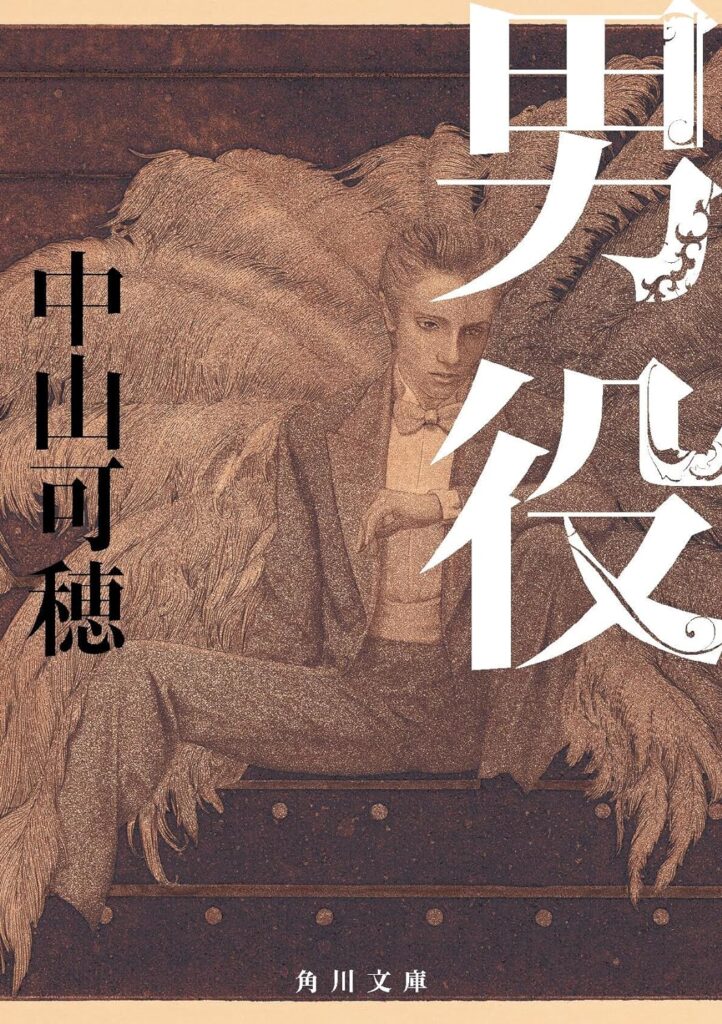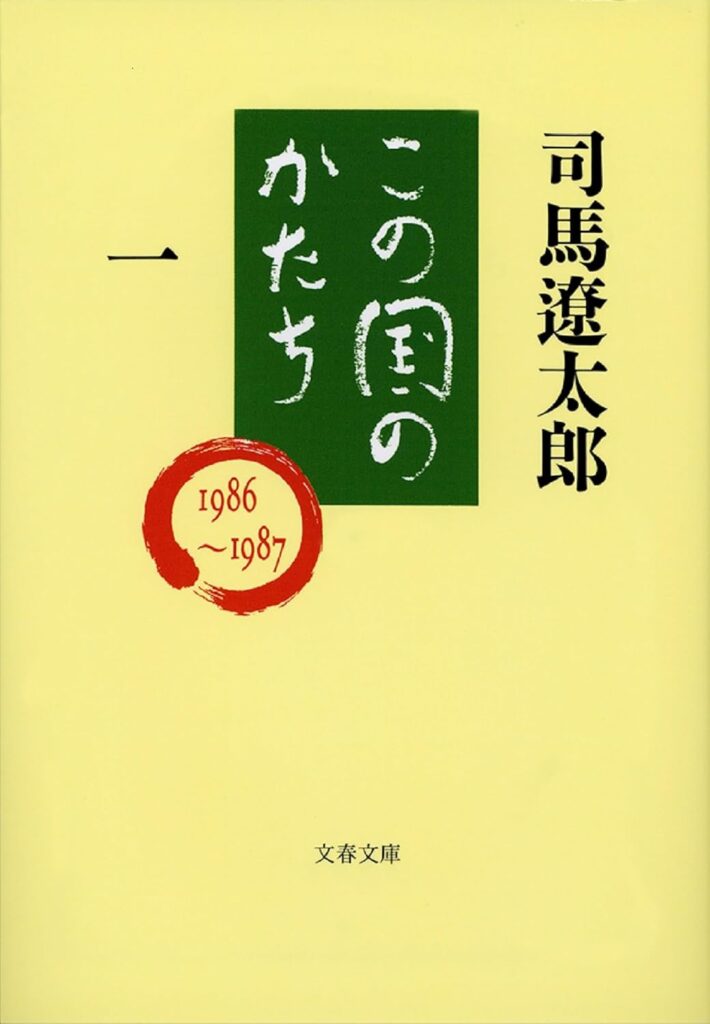
「この国のかたち」のあらすじ(ネタバレあり)です。「この国のかたち」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。この作品は、司馬遼太郎さんが長年にわたり、週刊誌で連載していた随筆をまとめたものです。一話完結の話もあれば、数回にわたって一つのテーマを掘り下げる話もあります。
古代から近代、特に司馬さんが強い問題意識を持っていた昭和前期に至るまで、日本の歴史や文化、日本人の精神性について、様々な角度から光を当てています。単なる歴史解説ではなく、司馬さん自身の体験や思索が色濃く反映されているのが特徴です。なぜ日本はあの戦争へ突き進んだのか、という問いが通奏低音のように流れています。
例えば、「”雑貨屋”の帝国主義」という衝撃的な題名のエピソードがあります。ここでは、欧米列強の帝国主義と、当時の日本の状況を対比させながら、日本の近代が抱えた歪な構造を鋭く指摘しています。タオルやマッチのような雑貨を売るために国を危うくした、という見方は、まさに司馬さんならではの視点と言えるでしょう。
他にも、「恥を知る」という日本人の美徳とされる精神性や、江戸時代の社会システム、そして絶筆となった海軍の話など、テーマは多岐にわたります。これらの考察を通して、司馬さんは私たちに「日本とはどういう国なのか」「日本人とは何なのか」を問いかけ続けているように感じられます。読み進めるうちに、日本の輪郭が少しずつ見えてくるような、そんな感覚を覚える作品です。
「この国のかたち」のあらすじ(ネタバレあり)
この作品は、特定の主人公がいて物語が進行する、いわゆる「小説」とは少し趣が異なります。司馬遼太郎さんが、日本の歴史や文化、国民性について、様々なテーマを取り上げて考察した随筆集です。連載期間は1986年から1996年におよび、全6巻にまとめられています。各巻には、「はじめに」や「あとがき」のような形で、連載当時の司馬さんの思いが記されていることもあります。
内容の中心となるのは、やはり日本の近代、特に明治維新から太平洋戦争敗戦に至るまでの時期への深い洞察です。司馬さん自身が戦争を体験していることもあり、なぜ日本があのような道を歩んでしまったのか、という問いが繰り返し語られます。日露戦争の勝利がもたらした国民の高揚感、その後の軍部の独走、そして破滅的な戦争への突入。その過程を、司馬さんは時に冷静に、時に強い憤りをもって分析していきます。
特に印象的なのは、「”雑貨屋”の帝国主義」や、日露戦争勝利から太平洋戦争敗戦までの「四十年」を擬人化し対話する形式など、独特の切り口です。また、「恥を知る」という概念を軸に日本人の精神性を探ったり、江戸時代の合理的な社会システムを再評価したり、あるいは日本独特の神道のありように触れたりと、テーマは非常に幅広いです。
最終巻の最後のテーマは「歴史のなかの海軍」でした。日本の海軍がどのように生まれ、なぜ国力に見合わない規模にまで拡大し、そして無謀な戦争へと突き進んだのか。その核心に迫ろうとしたところで、残念ながら筆は止まってしまいました。しかし、遺された文章からも、司馬さんがこのテーマに込めた並々ならぬ思いが伝わってきます。全体を通して、司馬史観と呼ばれる独自の歴史観に基づき、「この国のかたち」を多角的に描き出そうとした作品と言えるでしょう。
「この国のかたち」の感想・レビュー
司馬遼太郎さんの作品といえば、「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」といった長編歴史小説を思い浮かべる方が多いかもしれません。もちろん、それらの作品も素晴らしいのですが、私が個人的に、繰り返し読み返したくなるのが、この随筆集「この国のかたち」なんです。
この作品との出会いは、数年前に遡ります。日本の近代史、特に太平洋戦争について、もっと深く知りたいと思っていた時期でした。教科書的な知識だけでなく、当時の人々が何を考え、どんな空気が流れていたのか、そういった生々しい部分に触れたいと感じていたんです。そんな時、本屋でふと手に取ったのがこの「この国のかたち」でした。「この国のかたち」という、あまりにもストレートで、そして大きな問いを投げかけるような題名に惹かれたのを覚えています。
読み始めてまず感じたのは、そのテーマの幅広さです。古代の神話の世界から、中世の武士の精神、近世の江戸文化、そして近代の激動まで、まさに日本の通史を辿るような構成になっています。しかし、単なる歴史のダイジェストではありません。一つ一つのテーマについて、司馬さんならではの深い洞察と、時にユニークな視点が提示されます。
例えば、第一巻の冒頭近くに出てくる「”雑貨屋”の帝国主義」。この表現には、度肝を抜かれました。一般的に帝国主義といえば、産業革命を経た欧米列強が、過剰な資本と商品を輸出するために植民地を獲得・支配した、というイメージがあります。しかし司馬さんは、当時の日本には欧米のような圧倒的な工業力も、輸出するほどの余剰生産物もなかったと指摘します。せいぜい、タオルやマッチ、砂糖、人絹といった日用雑貨を朝鮮半島や中国大陸に売っていたに過ぎない。それなのに、欧米列強の真似事をして「帝国主義」を掲げ、結果的に国を滅ぼしかねない道を進んでしまった。この「雑貨屋」という、どこか物悲しく、滑稽ですらある表現に、当時の日本の歪んだ状況と、それに対する司馬さんの痛烈な批判が込められていると感じました。
また、日露戦争勝利から太平洋戦争敗戦までの、いわゆる「昭和前期」への考察も、この作品の重要な柱です。司馬さんは、この約四十年を<巨大な青みどろの不定形なモノ>と表現し、それと対話するという、非常にユニークな手法をとっています。なぜ、日露戦争という奇跡的な勝利を収めた日本が、その後、道を誤ってしまったのか。司馬さんは、軍部の一部指導者の狂気だけでなく、国民の中にあった熱狂や、時代の空気そのものにも目を向けます。日露戦争後の講和条約(ポーツマス条約)締結の際、賠償金が取れなかったことに激怒した民衆が日比谷焼き討ち事件を起こし、「戦争継続」を叫んだという事実は、読んでいて背筋が寒くなる思いでした。戦争は、一部の狂人が起こすものだと思いたい。でも、歴史を紐解けば、むしろ民衆の熱狂が戦争を後押しした側面もある。この事実は、現代に生きる私たちにとっても、決して他人事ではない問いを投げかけてきます。
司馬さんは、この「四十年」の異常性を繰り返し指摘します。<一人のヒトラーも出ずに、大勢でこんなばかな四十年を持った国があるだろうか>という言葉には、深い絶望と憤りが感じられます。司馬さん自身、学徒出陣で戦争を体験し、多くの仲間を失いました。戦後、「なんとおろかな国にうまれたことか」と思ったことが、歴史を探求する原点になったと語っています。その強烈な原体験が、この「この国のかたち」の根底には流れているのです。彼の筆致は、単なる客観的な分析に留まらず、常に当事者としての痛切な思いが伴っています。だからこそ、彼の言葉は私たちの心に強く響くのかもしれません。
この作品のもう一つの魅力は、「日本人とは何か」という問いに対する、多角的なアプローチです。例えば、「恥を知る」という精神性。司馬さんは、これを坂東武士に由来する、日本人の固有の美徳、あるいは自己抑制の感覚として捉えています。自分の行動が、世間や共同体から見て「恥ずかしい」ものでないか、常に自問自答する。この感覚が、かつての日本社会の秩序や品格を支えていたのではないか、と。しかし、近代化、特に昭和前期の熱狂の中で、この「恥を知る」精神はどこかへ消えてしまったのではないか、と司馬さんは嘆きます。国家全体が品性を失い、恥ずべき戦争へと突き進んでしまった、と。現代社会に生きる私たちも、この「恥」の感覚をどれだけ持ち合わせているでしょうか。経済的な豊かさや効率ばかりが追求される中で、見失われがちな大切な価値観について、改めて考えさせられました。
また、江戸時代に対する再評価も興味深い点です。私たちは、明治維新によって封建的な江戸時代が打ち破られ、近代化が進んだ、と単純に考えがちです。しかし司馬さんは、三百年間、大きな戦争もなく続いた江戸時代の社会システムの中に、現代にも通じる合理性や知恵があったことを見出します。例えば、各藩が独自の文化や経済を持ち、多様性が保たれていたこと。あるいは、武士だけでなく、商人や職人、農民など、それぞれの階層が持つ専門性や倫理観が社会を支えていたこと。こうした視点は、画一的な近代化やグローバリズムの中で失われつつある、日本の多様な文化や伝統の価値を再認識させてくれます。
そして、忘れてはならないのが、最終巻で扱われ、そして絶筆となった「歴史のなかの海軍」です。司馬さんは、「坂の上の雲」で明治期の海軍の栄光を描きましたが、この「この国のかたち」では、その後の海軍が抱えた問題点、そして太平洋戦争へと至る悲劇を深く掘り下げようとしていました。なぜ、日本は国力に見合わない巨大な海軍を持ち続けようとしたのか。なぜ、石油という戦略資源をアメリカに依存しながら、そのアメリカと戦争をするという無謀な道を選んだのか。司馬さんは、世界史的な海軍の役割(商船護衛や植民地支配の道具)と、日本の海軍の成り立ち(純粋な国防目的)の違いを指摘しつつ、日露戦争の勝利が海軍を国民的な「精神的支柱」にしてしまったことの不幸を分析します。機械であるはずの海軍が、いつしか精神論や非合理的な期待によって肥大化し、国家財政を圧迫し、ついには国を滅ぼしかねない戦争へと導いてしまった。このテーマに対する司馬さんの問題意識は非常に強く、もし書き続けられていたら、どのような結論に至ったのか、本当に残念でなりません。遺された文章を読むだけでも、その分析の鋭さと、歴史に対する真摯な姿勢がひしひしと伝わってきます。
もちろん、司馬さんの歴史観、いわゆる「司馬史観」に対しては、様々な批判があることも承知しています。特に、明治時代を肯定的に描き、昭和前期を否定的に捉える傾向がある点や、物語性を重視するあまり史実の解釈に偏りがあるのではないか、といった指摘です。しかし、私は、そうした批判があることを踏まえた上でなお、この「この国のかたち」を読む価値は非常に大きいと感じています。なぜなら、司馬さんの文章には、単なる歴史的事実の羅列を超えた、深い洞察と、読む者の心を揺さぶる力があるからです。彼の問いかけは、過去の出来事を解説するだけでなく、常に現代に生きる私たち自身に向けられています。「私たちは、この国の歴史から何を学び、未来へどう繋いでいくべきなのか」と。
司馬さんの文章は、決して難解ではありません。むしろ、時にユーモラスな表現を交えながら、非常に分かりやすく、読者を引き込む魅力があります。元新聞記者であった経験からか、事実に基づいた緻密な調査と、それを物語として再構成する力が、見事に融合していると感じます。一つ一つの随筆は比較的短いものが多いので、通勤電車の中や、寝る前のちょっとした時間に少しずつ読み進めることができるのも、この作品の魅力の一つかもしれません。
全6巻を読み通して感じるのは、司馬遼太郎という一人の知識人が、生涯をかけて「日本」という存在と格闘し続けた、その凄まじい情熱です。戦争体験という原点から出発し、膨大な資料を読み込み、日本各地を歩き、そして思索を重ねる。その過程で紡ぎ出された言葉の一つ一つが、私たちに多くの示唆を与えてくれます。「この国のかたち」は、単なる歴史の知識を得るための本ではありません。日本人として、この国に生きる一人として、自分たちの足元を見つめ直し、未来を考えるための、かけがえのない道標となる作品だと、私は確信しています。まだ読んだことがないという方には、ぜひ一度手に取ってみていただきたい、心からそう思う一冊です。
まとめ
司馬遼太郎さんの「この国のかたち」は、日本の歴史や文化、そして日本人の精神性について、深く考えさせてくれる随筆集です。古代から近代、特に昭和前期の戦争に至る道程を、司馬さんならではの鋭い視点と、時にユーモラスな筆致で描き出しています。「”雑貨屋”の帝国主義」や「恥を知る」文化、そして絶筆となった海軍の話など、印象的なテーマが満載です。
単なる歴史解説に留まらず、司馬さん自身の戦争体験に基づく問題意識が色濃く反映されており、読む者の心に強く訴えかけます。司馬史観への批判も認識しつつ、それでもなお、現代に生きる私たちが日本の過去と未来を考える上で、多くの示唆を与えてくれる貴重な作品と言えるでしょう。