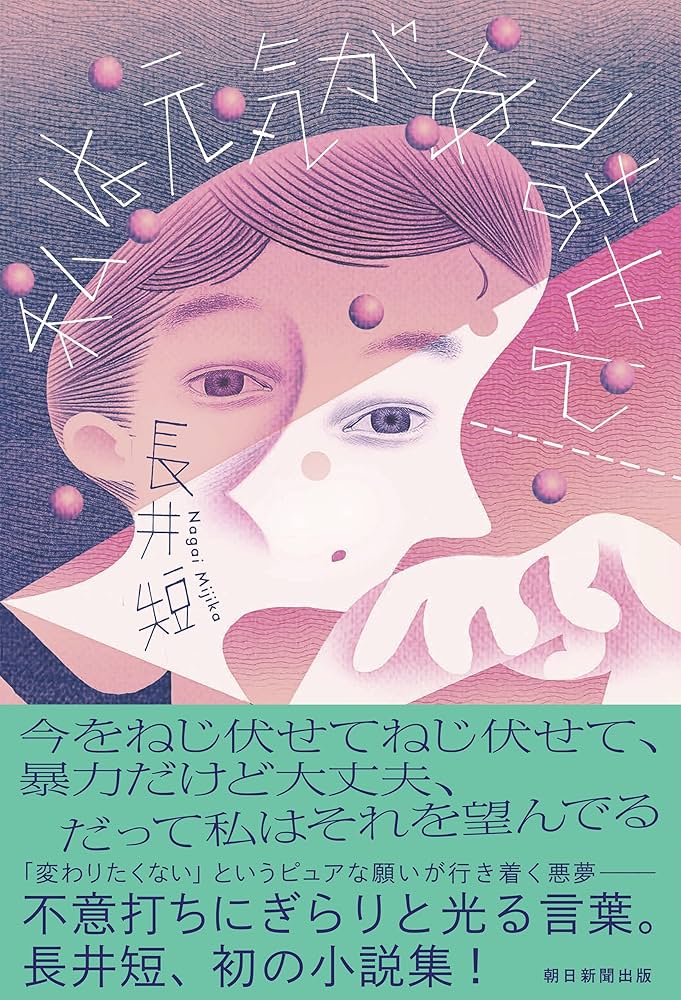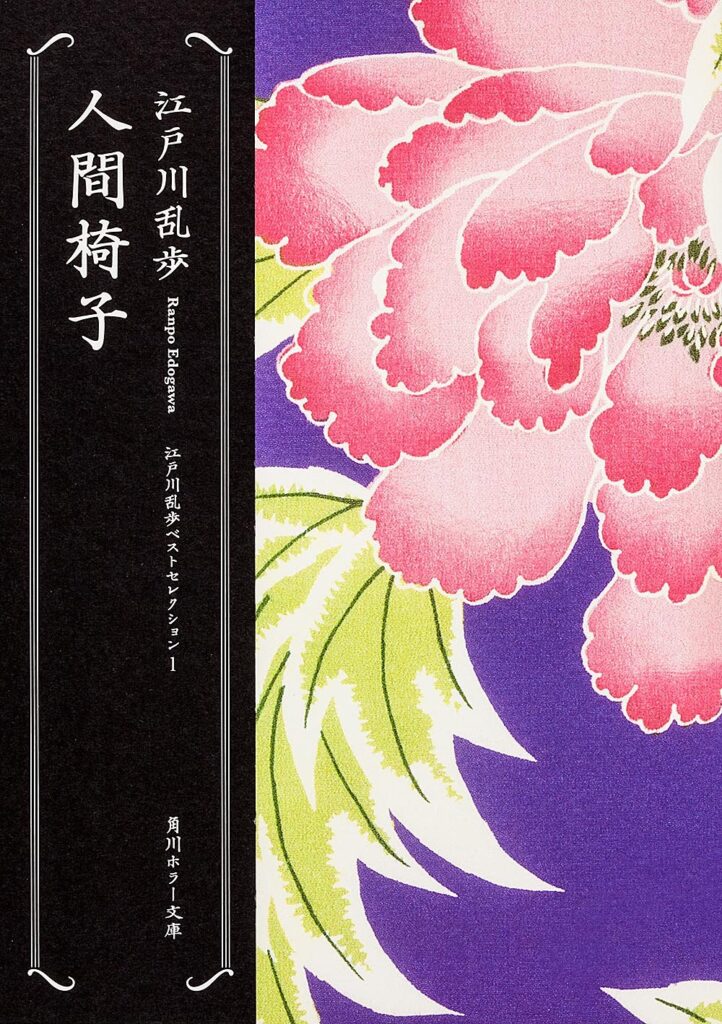「あきらめません!」のあらすじ(ネタバレあり)です。「あきらめません!」未読の方は気を付けてください。ガチ感想も書いています。
東京で子育てと仕事をやり切った霧島郁子は、定年後、夫の提案で夫の故郷・栗里市へ移住します。ところが、待っていたのは古い慣習と男尊女卑が濃く残る地域社会。郁子は市議会を傍聴し、女性議員が浴びる低俗なヤジに衝撃を受けます。
やがて出会ったのが、銀髪のベテラン議員・市川ミサオ。彼女に背中を押され、郁子は市議選に挑戦。初戦は敗れるものの、補欠選で当選します。しかし議場では「引っ込め」などの罵声が飛び、理不尽の壁は想像以上に厚いものでした。
同じ町で暮らす三十代の落合由香もまた、保育や家事・介護のしわ寄せに苦しみ、郁子の活動に共鳴して動き出します。世代を超えた女性たちの“連帯”が、静かに芽吹きます。
それでも議会の多数派は高齢男性中心。郁子は「このままでは何も変わらない」と痛感し、ついに市長選へ。公約は議会の男女比を定めるクオータ制の導入。全国から注目が集まる中、郁子は勝利をつかみ、改革の第一歩を踏み出します。
なお本作は映画化も発表され、永作博美さんが郁子を演じる予定です。監督は大九明子さん。舞台は石川県の能美市・小松市で撮影が進められる見込みとのことです。
「あきらめません!」のあらすじ(ネタバレあり)
定年を迎えた霧島郁子は、夫・幹夫の希望で故郷の栗里市へ移住する。そこは、冠婚葬祭から地域行事まで“昔ながら”が幅を利かせる土地だった。市議会をのぞいた郁子は、女性議員が容姿や服装まで貶められる場面に居合わせ、胸をざわつかせる。
議場の外でふさぎこむ女性議員に「言い返すべき」とつい厳しく言ってしまった郁子の前に、老練な市議・市川ミサオが現れる。ミサオは郁子の芯の強さを見抜き、「後継に」と立候補を勧める。
郁子は逡巡のすえ、市政の勉強会を開きながら準備を進める。地域の女性たち—姑の世代、子育て世代—が台所と茶の間に集まり、暮らしの困りごとを言葉にする。その輪に落合由香も加わった。
選挙戦は思った以上に厳しい。地縁・血縁がつよい町で、“よそ者の女性”は不利だ。初挑戦は敗北。だが、補欠選で再挑戦し、ついに当選を果たす。
議員になってからが本当の闘いだった。質問のたびに飛んでくる品位を欠くヤジ。不要不急の箱モノ計画や観光視察名目の海外出張など、旧態依然の支出がまかり通る。
郁子は折れそうになる。だが、由香やミサオ、家族の支えが踏ん張らせる。夫・幹夫も、次第に「議員の数が変わらねば、構造は変わらない」と理解を深めていく。
郁子は決断する。市長選に打って出るのだ。掲げた柱は、議会にクオータ制を導入し、意思決定の場に多様な当事者を送り込むこと。町じゅうで勉強会を重ね、賛否の声がぶつかり合う。
対立候補は既得権益に根を張る現職。郁子は、保育、介護、医療、防災など暮らしの課題を一つひとつ可視化し、「私たちの声を政策へ」と訴える。
投開票日、郁子は接戦を制し、市長に就任。まずやったのはクオータ制の実現に向けた条例整備だ。女性議員が増え、議会の空気は少しずつ変わり始める。
由香もまた、家族の関係を見直し、地域で子どもを育てる仕組みに参加していく。ミサオは次の世代にバトンを渡し、郁子は「ここで生きる全員のための政治」を続ける決意を固める。
「あきらめません!」の感想・レビュー
一つ目に心をつかまれたのは、郁子の“普通さ”です。カリスマでも活動家でもない彼女が、台所テーブルの延長で政治に手を伸ばす。これがとてもリアルで、読んでいるこちらの「自分にもできるのでは」という感覚を確かに刺激します。とりわけ、勉強会での会話や買い物帰りの立ち話が、そのまま政策の芽になっていく導線は見事でした。
次に印象深いのは、議場の“温度”の描き分けです。傍聴席での初期衝撃、初質問で浴びる罵声、帰宅後に台所で落ちる肩。抑えた筆致で積み上げるからこそ、ヤジの一言が胸に刺さります。「怒っているのに声が出ない」瞬間の悔しさが、じわじわ再現されていました。
三つ目の読みどころは、世代のリレーです。ミサオ—郁子—由香という縦のラインが、それぞれの立場から“諦めない”理由を示します。ミサオは長年の蓄積で背中を押し、郁子は制度を動かし、由香は生活の現場から声を上げる。一人では届かない領域を、三者で包囲する構図が心地よい。
クオータ制をめぐる描写も評価できます。制度の仕組みをことさらに教科書的に解説するのではなく、勉強会や反対派とのやりとりを通じて、読者に“必要性”を体感させてくれます。「人数が変われば、会話が変わる。会話が変われば、決定が変わる」という当たり前が、物語の進行とともに腑に落ちるのです。
また、郁子と幹夫の関係の推移がよくできています。移住を主導したのは夫で、郁子はついていった形。それが途中で反転し、幹夫が郁子の活動を後押しする側に回る。家族の“役割”が固定ではないことを、静かな筆さばきで示しています。対立もすれ違いもある。でも、理解の地点まで歩み寄る。長年連れ添った夫婦像としても納得度が高いです。
里の“顔役”たちの描写は痛烈です。個人攻撃に走るヤジ、見栄のための箱モノ、説明責任を回避する慣行。ここに誇張を入れすぎないので、読み終えてからも「どこにでも起こりうる」という寒気が残ります。対照的に、変化の兆しはいつも生活の側から立ち上がる。保育の現場、介護の現場、家計の現場。そこに物語の倫理が横たわっています。
舞台の手触りも良い。回覧板や自治会費、神社の世話、近所の目。地方を記号化せず、面倒と豊かさの両方を描き出す姿勢に誠実さを感じました。郁子が「ここで暮らす以上、内側から変える」と腹をくくる瞬間、土地と人の関係が物語の芯として立ち上がります。
個人的にぐっときたのは、郁子が“言い返せなかった”場面の処理です。強い言葉で叱咤していた彼女が、いざ自分が壇上に立つと凍りつく。この反転は、誰の中にもある弱さを照らします。同時に、そこから立ち上がるための手順—仲間を作り、事実で備え、場数を踏む—が丁寧に示されているのが頼もしい。
由香の線は、生活小説として秀逸です。ワンオペ、義家族との関係、パートの不安定さ。どれも特別な事件ではないけれど、連続すれば人を削る。由香が「このままではダメだ」と立ち上がる瞬間、郁子の物語とぴたり重なります。二人の視線が交差するたび、読者の視界も広がる設計です。
本作の“気持ちよさ”は、破壊ではなく更新を志向する点にあります。敵を打ち負かすカタルシスより、制度を作り替える喜びに軸足がある。クオータ制という仕組みを掲げた時点で、対立は避けられません。それでも議論を公開し、勉強会で理解を積み上げ、選挙という手続きを通す。物語としての正攻法が、読者の呼吸を整えてくれます。
終盤、市長選の“物語性”は高いですが、都合よく進みすぎると感じる読者もいるでしょう。現実の政治はもっと荒いし、時間もかかる。それでも本作が提示するのは、“第一歩”の重要性です。まずは一人が立つ。次に十人が続く。理想は遠くても、具体的な制度に落とすことで、手触りは確かになります。
文章のリズムにも注目したい。家事や買い物のシーンから、議場の緊張へと移るテンポが小気味よく、読み味を軽やかに保っています。軽快さを保ちながら、現実の重さを削らない匙加減がうまい。日常を踏み台にして制度へ届くルートが、読者の身体感覚に沿って描かれています。
脇役の配置も効いています。ミサオの老練、もう一人の女性議員のためらい、無自覚な差別を口走る“善良な市民”、SNSで声を上げる若い父親。多様な立場を置くことで、単純な善悪図式に落ちない奥行きが生まれました。誰もが少しずつ“変わりうる”ことを、人物たちが証明していきます。
映画化の報は、本作のテーマが今を射抜いている証拠でしょう。映像になれば、議場の空気や商店街の匂い、台所の湯気まで可視化されるはず。配役やロケ地のニュースに触れると、活字で感じた温度がスクリーンでどう立ち上がるか、期待が膨らみます。
読み終えて残るのは、「政治は遠いものではない」という感覚です。選挙運動に参加する、議会を傍聴する、自治会に顔を出す。できることは小さいけれど、積み上げれば景色は変わる。タイトルの力強い言葉が、読み手の日常へ静かに連結していく一冊でした。
まとめ
-
郁子と幹夫が栗里市へ移住し、地域の“古さ”に直面する。
-
市議会で女性議員への罵声を目撃し、郁子の中に火がつく。
-
市川ミサオが郁子に立候補を勧め、台所発の勉強会が始まる。
-
初挑戦は落選。補欠選で再挑戦し当選する。
-
議場では低俗なヤジが続き、郁子は挫けそうになる。
-
由香ら生活者が支え、郁子は“数”の重要性を学ぶ。
-
構造を変えるため、市長選への出馬を決断する。
-
公約の柱はクオータ制の導入。町中で勉強会を重ねる。
-
激戦の末に当選し、条例整備で議会の顔ぶれが変わり始める。
-
ミサオは次世代に託し、郁子と由香は“暮らしから政策へ”を続ける。